
長内 厚
ソニーの「テレビ事業分離」に見える極めて合理的な思惑、日の丸家電は“生き残り策”のお手本にせよ
ソニーは中国テレビ大手のTCLと合弁会社を設立し、テレビやホームオーディオの事業を新会社に移行することを発表した。これはテレビ事業において「持たざる強み」を持つソニーにとって、実に合理的な決断だ。「生き残り策」を模索する日の丸家電にとってお手本ともいえる、その協業モデルを考察しよう。

ソニーこそ『国宝』大ヒットの真の立役者、ディズニーもかなわない「黒子的映画ビジネス」の神髄とは
俳優の吉沢亮と横浜流星が出演する映画『国宝』が興行収入110億円を突破した。大成功の立役者は、この映画に黒子的に関わっているソニーだ。実は、同社がこれまで培ってきた「ソニーらしさ」が反映されたビジネスなのである。

ホンダと日産の統合は自動車“大淘汰”の幕開けか?電機業界の轍を踏まない戦略とは
自動車大手のホンダと日産自動車が、経営統合への協議の可能性を探るため、調整に入ったという。いよいよ自動車業界でも、かつて電機業界で起こった再編淘汰が始まるのではないか。焦点となるのは、かつて総合電機メーカーを襲ったデジタル化の波だ。自動車業界が同じ轍を踏まないために、ホンダと日産がこれから向かうべき戦略を提言する。

政府による規制は民間の経済活動を制限するものであり、社会的に妥当な目的があったとしてもイノベーションは制約されるものと考えられがちだ。しかし、驚くかもしれないが、政府による厳しい規制がむしろ民間企業のイノベーションを促進することもある。実際、環境規制が厳しい欧州の企業をはじめ、日本の企業にも規制を逆手にとってビジネスチャンスを拡大している事例がたくさんあるのだ。規制は企業の競争戦略にとっても、大きな意味を持っている。

シャープが堺の液晶パネル生産を終了した。シャープにとって液晶技術とは、コア・コンピタンスである。その拠点だった堺工場は、なぜ「シャープのお荷物」となってしまったのか。本来なら経営復活の起点になれたはずの堺工場が陥った罠とは。

TSMCが日本にもたらす「半導体バブル」以上の価値、ラピダスとの決定的な差とは
TMSCの工場がつくられる熊本では、地価や時給が高騰したり、無人駅でラッシュが起きたりするなど、景気のよさそうな話が聞こえてくる。ただ、そもそもTSMCという台湾企業が日本に進出することは、半導体産業にとってそれ以上の価値をもたらす。それは日本連合のラピダスにはない、イノベーションの視点である。

経済産業省の音頭のもとで、日本の主要企業8社が出資して発足したRapidus(ラピダス)は、2020年代後半にビヨンド2ナノの超最先端ロジック半導体を作ろうと企図している。しかも、少量多品種生産を目指すという。これを見て思い浮かぶのは、『機動戦士ガンダム』の物語だ。一年戦争における地球連邦軍の反転攻勢から、日本の半導体産業が学ぶべきこととは何か。

一般的なイメージとして、東大の校風には真面目なイメージがあり、京大には自由なイメージがある。両校の違いは何だろうか。ビジネス界でバズワードになっている「両利きの経営」に照らして考えると、両校の組織の特徴とこれからの課題が見えてくる。

足もとで日本は韓国向けの輸出管理を解除し、韓国もWTOへの提訴を取り下げることで合意した。崩れた日韓関係の改善は、日本のエレクトロニクス産業にとっても大きなメリットがある。現在の国際情勢では、日韓の諍いが第三者に漁夫の利を与えるような事態に陥りかねないからだ。これから日韓が進むべき、産業面での連携について考える。

EVで波に乗る中国の自動車メーカーBYDが、日本で使用が認められていない六価クロムをボルトのさび止めなどに使用していた問題が明らかになった。日本の自動車産業においては当たり前のように使用が自粛されている物質だ。日本はEVに出遅れているのではないかと言われる中、安心・安全に関与した技術やノウハウのアドバンテージを考える。

ソニーグループは同社の十時裕樹副社長兼CFOを、4月1日付で社長に昇格させる人事を発表した。この人事は2000年代以降のソニーの経営不振とその後のリカバリーという、一連のイベントの集大成といえるかもしれない。それは十時氏が、ソニーの中では珍しく、価値獲得のプロセスを堅実に担える人材であるからだ。

先日、トヨタ自動車やNTTなどが立ち上げたラピダス(Rapidus)は、国産半導体復興を目指した共同出資企業だ。これまでも日の丸連合をつくったケースは多々あるが、競争が激しい半導体産業においてどれだけ戦えるだろうか。ビヨンド2ナノ(回路幅が2ナノクラスの次世代半導体)に向けて、台湾への半導体投資というプランBが必要なのではないか。

最近のホンダや日産の動きを見ていると、EVの主戦場は軽自動車になるのではないか。そうなると、EV大競争時代における彼らの「真のライバル」は、トヨタではないかもしれない。

ソニーの経営は今絶好調なのに対し、パナソニックは不調だ。しかし、平井一夫社長や津賀一宏社長がそれぞれ就任した2010年代の始めは、両社の立場を入れ替えて同じことが言われていた。ソニーもパナソニックも強い経営力を持っているが、今後どのようにグローバル競争を戦っていくのかというビジョンを明確に示すことが、まだ不十分かもしれない。求めらるのは「21世紀の水道哲学」だ。

パナソニックは今年4月に持株会社制に移行し、パナソニックホールディングスへ商号変更した。このタイミングでの組織変更は何を意味するのか。これまでも各カンパニー長が独立して事業責任を負ってきたため、持株会社制に移行しても結局カンパニー制と変わらないのではないかという見方もある。しかし、その背景にはステークホルダーが気付かない、経営改革への「本気度」が見える。

東芝の経営陣に内紛が起こり、危機的状態だという。6月末の定時株主総会に諮る取締役候補に、大株主である海外ファンドの関係者が含まれていたことが波紋を広げており、非上場化に向けてアクティビストを取締役に迎え入れるつもりだと噂されている。本当に東芝に未来はないのだろうか。3月に就任した島田社長の経営手腕を考察する。

ソニー元会長の出井伸之氏が亡くなった。出井氏のソニー経営者としての評価は、大きく分かれる。しかし今思えば、氏の感性は時代を先取りしすぎていたともいえる。元ソニー社員が、その語られない功績を振り返る。
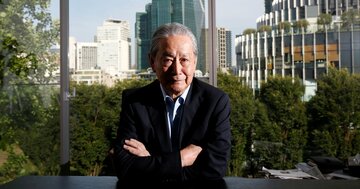
オンキヨーが経営破綻した。40、50代以上のhi-fiブームを知っている世代にとって、この度の破産申請は大きなショックだったろう。オンキヨーが再生を断念した原因は主に3つある。そこからは、日の丸家電メーカーの凋落にも通じる課題が見える。

半導体不足が深刻化し、様々な産業の生産に影響が出始め、各国は半導体の確保競争に乗り出している。そうした中で、日本は熊本にTSMCを誘致することに成功し、ソニーグループとの合弁で22~28nmプロセスの工場を建設する。4~5世代古いクラスの工場を作ることに対して、懐疑的な意見もある。しかしこの日本政府の決定は、日本の半導体産業を救うかもしれない画期的な決断といえる。

トヨタ自動車がバッテリーEV戦略の説明会を行った。「日本はEVで欧州の周回遅れではないか」「トヨタはEVに消極的と思われないように発表会を開いたのではないか」といった憶測もある。しかし、筆者の見立ては全く異なる。EVだけが唯一の環境の味方という考えは、幻想ではないか。日本は教条的なEVシフトへの疑問を、今こそ世界に問うべきだ。
