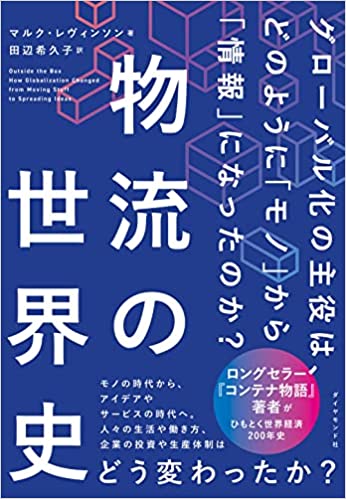ロングセラー書籍『コンテナ物語--世界を変えたのは「箱」の発明だった』(日経BP社)の著者マルク・レヴィンソンの最新刊『物流の世界史--グローバル化の主役は、どのように「モノ」から「情報」になったか?』より、その一部をご紹介する。
2006年8月16日午後5時30分、5隻のタグボートがエマ・マースク号をオーデンセ造船所から導き出し、後ろ向きに沖へと曳いていった。船は新しかろうが古かろうが、前進するものであって後ろに進むものではない。
 「グローバリゼーション」を実質的に後押ししたコンテナ船(イメージ画像。Photo: Adobe Stock)
「グローバリゼーション」を実質的に後押ししたコンテナ船(イメージ画像。Photo: Adobe Stock)
エマ・マースクはすべてが異例だった。全長はサッカー場四つ分、キールから甲板までの深さは35メートル弱。ライトブルーの船体はあまりに巨大で、水深の浅いオーデンセ・フィヨルドを抜け出すのは容易でない。ガベットの隘路をなんとか抜けて、フィヨルドから水深のふかい外海へと進んでいくと、浜辺に集まった何千ものデンマーク人たちの目の前に見事な光景が広がった。進水したその日、貨物も燃料も積んでいないエマ号は水面から高く浮き上がり、喫水線より下の白い船腹を露出させ、波の下で音もなく回転するはずの巨大な銅合金のスクリュープロペラも水面に顔を出していた。誰もがニュースで知っていたとおり、それはかつて製造されたもののなかで最大のプロペラだった。
エマ号にはグローバル化への期待が託されていた。デンマークの由緒ある海運コングロマリット、A・P・モラー・マースクの子会社マースクラインが所有するこの船を前にすると、半世紀におよぶコンテナ船の歴史に登場したどんな船も小さく見える。一握りの石油タンカーを除けば、これほど巨大な船はかつてなかった。エマ号とそれに続く7隻の同型船の建造費は、従来のコンテナ船を大きく上回る1隻当たり1億5400万ドルという高額だったが、それでも安上がりに思えた。一連の新型船が貨物を満載すれば、どんな船より国際物流を低コストにできるからだ。世界経済が拡大して長距離貿易が増えれば、こうしたコスト優位がシェア拡大につながるはずと、マースクラインの経営陣は計算していた。
コンテナ船はグローバル化の強力な担い手として、洗濯機から古紙に至るあらゆる貨物を入れた鉄の箱「コンテナ」を積み込み、遠く離れた港と港を結ぶ定期航路を展開している。貨物はそこからさらにトラック、列車、バージ船などに積み替えられ、何キロも内陸の都市まで運ばれる。急いで送りたいもの、あるいはダイヤモンドやディスクドライブのように高価な国際貨物なら空路が普通だが、それ以外の工業製品や農産物の多くは、長さ40フィート・幅8フィートの標準コンテナで運ばれる。20世紀最後の数十年間に、コンテナのおかげで物をどこで製造し、どこで栽培し、どうやって顧客に届けるかを決めるのに輸送コストはほぼ無視できるようになった。コンテナは世界貿易を変貌させ、十数カ国から部品を集めて完成車をつくることも、オーストラリア=カリフォルニア間1万5000キロを、ワイン1本当たりわずか15セントで送ることも可能になった。中国が世界最大の工業国へと驚くべき変身を遂げたのも、高い輸送コストに守られてきた各国の国内市場が国境なきグローバル市場へと呑み込まれ、デトロイトからドルトムントに至る歴史ある工業地帯が衰退していったのも、コンテナのおかげである。
1956年、最初のコンテナ船がニューアークからヒューストンに向けて出航して以来、次々と新世代のコンテナ船が登場して、大型化とコスト効率の向上を実現していった。エマ号と一連の同型船が発注された背景には、こうした流れが継続し、一般家庭で冬に新鮮なイチゴを楽しめるようになり、メーカーが何千キロも離れた工場と物流拠点をつなぐ、より長大で複雑なサプライチェーンを構築できるようになるとの期待があった。その後もさらなる大型船の建造が何十隻も続き、なかには長距離輸送トラック1万1000台分以上の積載量を誇る船もあった。だが超高層ビルの建設ラッシュがしばしば不況の予兆となるように(1920年代後半に世界一を目指して建設されたエンパイアステートビルは、1930年代の大恐慌で多数の空室を抱えることになった)、世界のほとんどの港に入港できないほど巨大な船の建造もまた、過剰な熱狂の前触れだった。エマ号の進水時には誰も気づいていなかったが、貿易が拡大し続ける時代は終わろうとしていた。第二次大戦以後のグローバル化の流れがそのまま続くと信じた人々は、多大な代償を支払うことになった。
***
「グローバル化(globalization)」は新しい概念ではない。最初に使われたのは1929年のベルギーと言われる。医師で教育者のJ・O・ドクロリは、幼児が自分以外の広い世界に関心を持つようになることをglobalizationと呼んだ。やがてこの言葉は、いろいろな意味に使われるようになった。例えば企業が大きくなり、国別モデルでなく世界共通の製品を売るようになること、国から国へとアイデアが伝わること、トップ選手が外国人の英国のサッカーチームを、米国人やケニア人、中国人が熱狂的に応援すること、等々。宗教の世界的伝播もグローバル化のひとつだし、病気の流行、人々が安全や政治的・社会的自由、あるいは経済的な機会を求めて大規模に移住することなどもそうだ。そして言うまでもなく、国境を越えた経済交流が活発になることもグローバル化である。
見方によっては、世界はとうの昔から高度にグローバル化されていた。歴史家のユルゲン・オースタハメルやニルス・P・ピーターソンは言う。「ある意味、ドイツの『米国化』は1945年に始まったのではなく、18世紀に(新大陸から)ジャガイモが持ち込まれたときに始まっていた」。とはいえ、今日言われるような意味でのグローバル化が急速に広まったのは19世紀に産業資本主義が誕生したときだ。植民地主義のヨーロッパ列強がアフリカ・アジアに通商網を張り巡らせ、陸海軍や植民地官僚によって自分たちの利権を守ろうとした時代である。インドをはじめ、かつて製造業がさかんだった国はヨーロッパの工場の生産性に太刀打ちできず、繊維製品は外国製品との競争に敗れ、一次産品の輸出国の地位へと落ちていった。
この第一のグローバル化では金融も国際化し、多くの国で輸出入が経済活動の大きな部分を占めるようになった。何千万人もが国境を超えて移住し、中国やタヒチのデザインがヨーロッパのアートに取り入れられた。世界は互いに強く結びつき、戦争はありえないかに見えたが、1914年8月の第一次大戦勃発で第一のグローバル化はあっけなく終わりを迎えた。
グローバル化の進行は1914年から1947年頃までストップした。二度の世界大戦、相次ぐ地域紛争、そして大恐慌が起こった時代である。この間も多国籍企業の成長は続いたが、国境を越えた金融・商業・人的つながりはほとんど失われた。こうしたグローバル化の後退を喜ぶ人々もいた。1943年、米下院議員のクレア・ブース・ルースは、国際派を自任するウォレス副大統領を批判して、「グローバロニー(グローバル化というたわごと)」をまき散らしていると痛烈に皮肉った。批判されて前言撤回し、「グローバル・ナンセンス」と言い換えたものの、彼女のこの造語をきっかけに、globalistic(グローバル主義の)、globalitis(グローバル病)、globalism(グローバル主義)などの言葉が米国人の語彙に加わり、移民受け入れや対外貿易、さらには国際協力などを揶揄するのに使われるようになった。
第二次大戦で連合軍が勝利すると、1940年代後半から再びグローバル化が息を吹き返した。この動きを後押ししたのが、金ドル本位制為替レートの柔軟化、そして原材料や工業製品の貿易障壁を引き下げようとする各国の努力だった。その結果、世界中のすべての富裕国、そして貧しい国の多くも、四半世紀にわたる力強い経済成長を遂げることになる。1970年代には何度も経済危機が起きたが、工業品の貿易量は1950年から1986年にかけて約15倍の成長を遂げた。原油高のなか、スーパータンカー、具体的にはULCC(30万トン以上の超大型原油タンカー)の登場で、石油市場は完全にグローバル化された。大型タンカーはペルシャ湾からヨーロッパ、日本、北米の製油所まで、1回の航海で数百万バレルの原油を運ぶことができる。こうして産油国に流れ込んだオイルマネーは、ロンドン、ニューヨーク、東京の金融機関に蓄積され、これらの国から発展途上国政府への大型融資や、多国籍企業の世界展開への融資に使われていった。
それでも第二のグローバル化は、第一のグローバル化と同じく、本当の意味でグローバルとは言えなかった。企業の対外進出は活発だったが、アイデンティティはあくまで母国にあり、経営陣もその国の出身者がほとんどだった。対外投資は急増したが一握りの富裕国に限られ、対外貿易も同様だった。貧しい国の多くは多額の債務を抱え、富裕国の投資家からの借り入れや、石油・コーヒーなどの一次産品の輸出によって、細々と国際貿易に参加するに過ぎなかった。
だから1947年から1986年の40年間におけるグローバル化への最大の批判は、貿易自由化で豊かな国が貧しい国を搾取しているというものだった。移民受け入れも搾取と見なされることが多く、富裕国が看護師や教師を貧困国から移住させて、「頭脳流出」を起こしていると非難された。貧困や後進性を脱却するにはグローバル化などせず、独自に活動したほうが得策だというのが反対派の主張だった。事実、中国、インド、ソ連など、国土も人口も大きな国の多くがアウタルキー(自給自足経済)を選択し、貿易・投資・移住・観光・学術交流・宗教思想など、指導者が危険とみなす国際交流に厳しい制約を課した。
1979年のマーガレット・サッチャーの英首相就任、それに続く1981年のロナルド・レーガンの米大統領就任に象徴されるように、富裕国で新自由主義が台頭すると国際貿易に新たな可能性が広がった。ホンダは1982年、日本企業として初めて四輪組立工場を米国に設立し、海を越えて何千キロも離れた本国からエンジンやトランスミッションを納期通りに取り寄せ、競合他社を脅かすようになった。1980年代後半になると、こうした長距離サプライチェーンが当たり前となり、第三のグローバル化が始まった。
国際貿易は、根本から劇的に変化した。小売業者や製造業者にとっては、部品をある国で設計し、別の国で製造し、さらに別の国で完成品に組み立てるなど、国境とは関係なく半製品を動かすほうが効率的になった。物理的な立地と国籍が一致する必要はなくなった。マサチューセッツ州に本社を置き、27カ国に工場を持つ工業用研磨剤メーカーが、パリに本社を置き、オランダの年金基金・英国の投資信託・中東の政府を主要株主とする企業の子会社だとしたら、それは「フランスの会社」なのか「米国の会社」なのか、それとも単に「多国籍企業」なのか、誰も決められない。1989年に社会主義が崩壊すると、資本主義が最終的に勝利したかに思われた。市場経済を疑っていた国々が急速にこれを受け入れるようになり、国際貿易は世界経済全体の3倍近いスピードで成長していった。
搾取を批判する声は止まなかったが、今回のグローバル化の被害者は貧しい国の労働者ではなく、豊かな国の労働者である。1994年、英国の大富豪の投資家で、完璧な「国際派」一族に属するサー・ジェームズ・ゴールドスミスが、ベストセラー『落とし穴(The Trap)』で国境をなくすことの愚かさを批判した。フランスの作家ヴィヴィアンヌ・フォレステルは、1996年の著書『経済の恐怖』(邦訳・丸山学芸図書、1998年)で現代経済のあり方を非難、3年後の1999年には、英国の社会学者アンソニー・ギデンズが『暴走する世界』(邦訳・ダイヤモンド社、2001年)でグローバル化に警鐘を鳴らした。
アンチ資本主義の人々、環境保護活動家、失業に不安を覚える人々、あるいは単にけんかっ早いだけの人々も含め、何万人もがシアトルに押し寄せて、世界貿易機関(WTO)閣僚会議への抗議行動を展開した。経済学者はこぞって自由貿易が世界を繁栄させると主張したが、ほとんど支持されず、自分たちも自由化して世界経済に参入したい貧困国の意向もほぼ無視された。2000年、2人の英国人ジャーナリストがグローバル化の将来を検討する共著を出版したが、『完璧なる未来(A Future Perfect)』というタイトルはいかにも的はずれに響いた。
2001~2008年のたった7年で世界の工業品貿易は120%増加し、中国では工業生産が急成長する一方、同じ7年間にカナダと米国で製造業の雇用の8分の1、英国では4分の1が失われた。当然、両者の関連が疑われた。製造業に続き、ITやサービス産業でも雇用が国外に流出した。世界中のオフィスビルがインターネットでつながり、ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)という新業種も登場した。フランクフルトやパリの企業が会計業務を低賃金のワルシャワやプラハなどに移し、北米の銀行が顧客向け電話対応をマニラの代理店に委託した。2003年までに、米国のトップ企業500社のうち285社が事務作業をインドに移した。米国のある下院議員は2004年、「ホワイトカラーの仕事が大量に国外に流出している」と警告し、「米国が第三世界の経済システムを採用しようとしている明白な証拠」と指摘した。
だが第三のグローバル化は、エマ・マースク出航の直後から人知れず後退を始めていた。2008年夏にはサブプライム危機に端を発した世界的金融危機が起こり、国際貿易は大きく低迷。それまで5年間で3倍に増えた企業の対外投資もたちまち落ち込んだ。嘆かわしい変化だが、決して想定外ではなかった。過去の不況でも貿易や投資は不振に陥ったが、その後は回復に転じており、今回もこのパターンに倣うだろうと思われた。
ところが世界経済が2010年に底を打っても、貿易と投資はこれまでのような立ち直りを見せなかった。経済指標や海運統計上の変化が徐々に国際企業の現実の動きに表れて、サプライチェーンや国外事業の縮小が相次いだ。ヨーロッパでも米国でも反移民の動きが強まり、グローバル化への激しい反発が続いていたが、一方でグローバル化そのものも変化しつつあった。2016年、大統領候補のドナルド・トランプが「行きすぎたグローバル化と労働者の権利剥奪」を批判し、その数カ月後にはフランスの政治家マリーヌ・ル・ペンが「我々の文明を危険にさらす、行きすぎたグローバル化」を批判。
だがこうした怒涛の変化を引き起こした時代の流れは、すでに終わりを迎えようとしていた。2019年末にCOVID-19(新型コロナウィルス)と呼ばれるウイルスが中国の武漢から広がり(訳注:中国はこれを認めていない)、営業停止や自宅隔離など、ノルウェーからニュージランドに至る全世界で商取引や移動が制限された。だが第三のグローバル化は、すでにまったく異なる国際関係のあり方へと変貌しつつあったのだ。(続く)