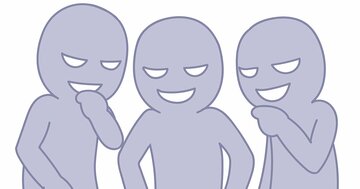「強いもの」への恐怖と、反抗できない悔しさ
「ちょっと、こっち来なさい」
え? 私たち、何か悪いことした?
ものすごい恐怖が一気に背中を駆け巡り、火照っていた体も一気に冷めていくのがわかった。
何せ、小学校に入学してから一度も怒られたことがないような子どもだったのだ。地獄に落ちるような気分だった。
私たちは、職員用に使っているであろう和室に連れられ、そして並んで正座させられた。
「どうして、他のお客さんが入っているのに大浴場に入ったんだ?」
眉間にしわを寄せ、先生が言う。本気で怒っているようだった。
でも、私は何も言い訳出来なかった。だって本当に何も思いつかなかったのだ。自分たちが悪いことをした意識もなかったし、どうして怒られているのかも疑問だった。さっさと怒っている理由を教えてほしいと思った。それは班のメンバーも同じようで、私たちは全員、何も言えずにただ黙りこくって正座をしていた。ひたすら、この時間が早く終わることを祈っていた。
「今回は他のお客さんもいるから、注意しなさいと言っただろう。どうして一般のお客さんしかお風呂に入ってはいけない時間帯に入ったんだ? しおりにも書いてあっただろう、××組のお風呂の時間帯は5時から5時半だって」
え? だって、そ、それは……。
「ちゃんとしおりを見てなかったのか? だめだろう、ルールを守らなければ、困る人がいる。もう小学3年生なんだから、しっかりしなさい」
だって、だって、それは……。
それは、5分前行動しなさいって、先生が言ったから。
言わなきゃ。言わなきゃ。言わなきゃ。
私たちは何も悪くないって、言わなきゃ。
わかっているのに、喉元が痙攣したみたいに、うまく動かなくなっていた。
「……ごめんなさい」
そして、やっと出てきた言葉は、それだけだった。
言い訳するんじゃない、とさらに怒られるのが怖くて、何も言えなかったのだ。何も言えない自分が悔しいのか、先生に怒られたのが怖かっただけなのか。よくわからないもやもやで心の中がいっぱいになって、涙が出た。
私が、悪かったのか。
その夜、幼い頭でずっと、必死になって考えていた。
どうして私は怒られたんだろう。先生に確認してから行くべきだったのだろうか。
ふと見ると、夕食を食べたあと、はしゃいで旅館の廊下を走り回っている腕白小僧たちが「こーらー。走らないよ!」と先生に笑いながら注意されていて、「はーい」「ほらぁ、だから走ったらダメだっつったじゃん」なんて、適当に返事をしていた。
あの子達は怒られないのに、私は怒られるんだ。
あの子達は、「廊下を走ってはいけない」って、「悪いことをしてる」ってわかった上で走っていても怒られないのに、「先生の言う通りにしなきゃ」と思って、5分前行動していた私は、あんなに怒られるんだ。
早とちりしないで、ちゃんとぴったりに行けばこんなことにはならなかった。バカ正直に言うことを聞いていたからこうなったんだ。だったら先生の言うことなんか初めから聞かなければよかったじゃないか。
大人になった今では、その程度の理不尽いくらでもあるさ、なんなら、理不尽のうちにも入らないくらいだよと軽く流せるけれど、8歳か9歳程度の幼い私にとっては、それは大問題だった。
多様性の時代、何にでもなれる自分に喜ぶべきはずなのに
その後、私は年齢を重ねるにつれ、それは「当たり前」にあることなのだと知った。その程度のことで嘆くような自分はむしろ、とても幸運だったのだという事実も、徐々に理解するようになっていた。
けれども、頭で冷静に理解するのと、心で納得するのは、また別の問題だった。あのとき感じた「大人」という存在への憤りを、そして何もできない自分への悔しさを、私はいまだに捨てきることができないでいる。
「やっぱり大人に認めてほしい」という怒りと、「どうせ努力なんかしても認めてくれるわけがない」という、諦め。
矛盾した感情が揺れ動いていて、気持ちが悪い。
心の中の幼い自分はまだ、あの閉塞感のある和室に正座させられたままなのだ。解放してあげたいのに、その方法がわからない。
あたし、今、どこにいるんだろう。
そういうことを、よく考えるようになった。
「わかったような口を聞かれるのは御免だ」「レッテルを貼られるのは嫌だ」なんて尖っていた時期もあったのに、今となっては、気がつけば、やたらと何かしらのレッテルを求めている。「社会人◯年目」「ライター」「独身女子」……。「レッテルを貼って偏見でものごとを見る大人ってむかつく」と思っていたはずなのに、今はむしろ、何かにカテゴライズされたがっている。勝手に決め付けてステレオタイプに当てはめる「大人」に腹を立てていたくせに、特定の何かに分類されることで享受できる安心感を、捨てきることができない。
この多様性の時代、何にでもなれる自分に喜ぶべきはずなのに、何にもなれないのではないかということの方がむしろ、怖くてたまらない。どこにも所属することができないのではないかという不安。自分で自分の居場所を一から作り上げるよりも、何かに分類され、どこかに所属することの方がよっぽど簡単だということを、私は本能的に察知してしまっている。
レッテルを貼られるのも嫌だけど、どこにも属すことができないのは、もっと嫌。
そんな矛盾した感情がどんどん湧き出てくる。あるいは、「大人はわかってくれない」というのは、私にとってある種の呪文みたいになってしまっているんじゃないかと思うこともある。「大人」や「社会」を便宜上の敵としてこしらえて、心の苦しみを一時的にでも、やり過ごそうとしているのだ。自己責任で片付けるには辛すぎることから、少しでも心を防御するための呪文だ。