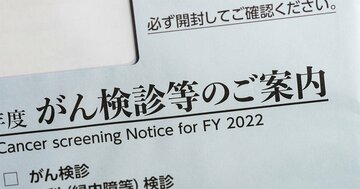前頭葉を使う生き方へとシフトチェンジすれば、人生が変わります。「毎日が実験」だと思って生きることです。「やってみないとわからない」という精神で、郵政民営化という日本中を巻き込む実験を行った人が、小泉純一郎元首相です。前頭葉を使えている人だと思います。おそらく小泉氏はうつにもなりにくいでしょう。
※本稿は、和田秀樹『50歳からの「脳のトリセツ」』(PHPビジネス新書)の一部を抜粋・編集したものです
「毎日が実験」と思えば、人生が楽しくなる
前頭葉を使う生き方へとシフトチェンジすれば、人生が変わります。今の生活だけでなく、60代以降の毎日が楽しく、充実したものになります。歳をとって頭が衰えるどころか、むしろ若い人よりも高い知性、広い視野、柔軟な思考を備えた、魅力あふれる人になれます。
 小泉純一郎元首相 Photo:Junko Kimura/gettyimages
小泉純一郎元首相 Photo:Junko Kimura/gettyimages
そのために、今日からできることは何でしょうか。それは、「毎日が実験」だと思って生きることです。
たとえば、ランチを食べに行くとします。このとき、いつも行く店ではなく、知らない店に入ってみましょう。いつもの店はおいしいとわかっているのに対し、知らない店はおいしいかどうかわかりません。その未知の領域に、足を踏み入れてみましょう。
映画を見るとき、いつもは見ないようなジャンルのものを試してみるのもいいでしょう。見る前から「この手の映画は苦手」「きっとつまらない」と決めるのは禁物です。人の嗜好は、本人も知らないうちに変化するもの。若いころは理解できなかったタイプの映画を、楽しめるようになっているかもしれません。
読書やスポーツにも、同じことが言えます。「この人とは気が合う」「合わない」といった相性もしかりです。
もちろん、実験してみて「この店はまずかった」「やっぱりつまらなかった」「合わなかった」と思うことも多々あります。しかし事前に決めつけるのと、試して体感するのとでは、前頭葉の働き方が大きく違います。
失敗するかもしれないから試さない、という発想は実験精神の大敵です。わからないからこそやってみる、という姿勢を持ちましょう。
そうすると、人生から「退屈」がなくなります。おいしいかまずいか、楽しいかつまらないか、合うか合わないか、いつも勝負をかけているのですから、退屈の入り込みようがありません。
そして実験が成功したときは、これまで知らなかった楽しいことや、面白いことと出会えます。自分の新たな一面を知ることもできます。意外な特技を見つけて、それをさらに伸ばしていく、といったこともできるでしょう。実験の毎日は、いくつになっても成長する人の基盤でもあるのです。