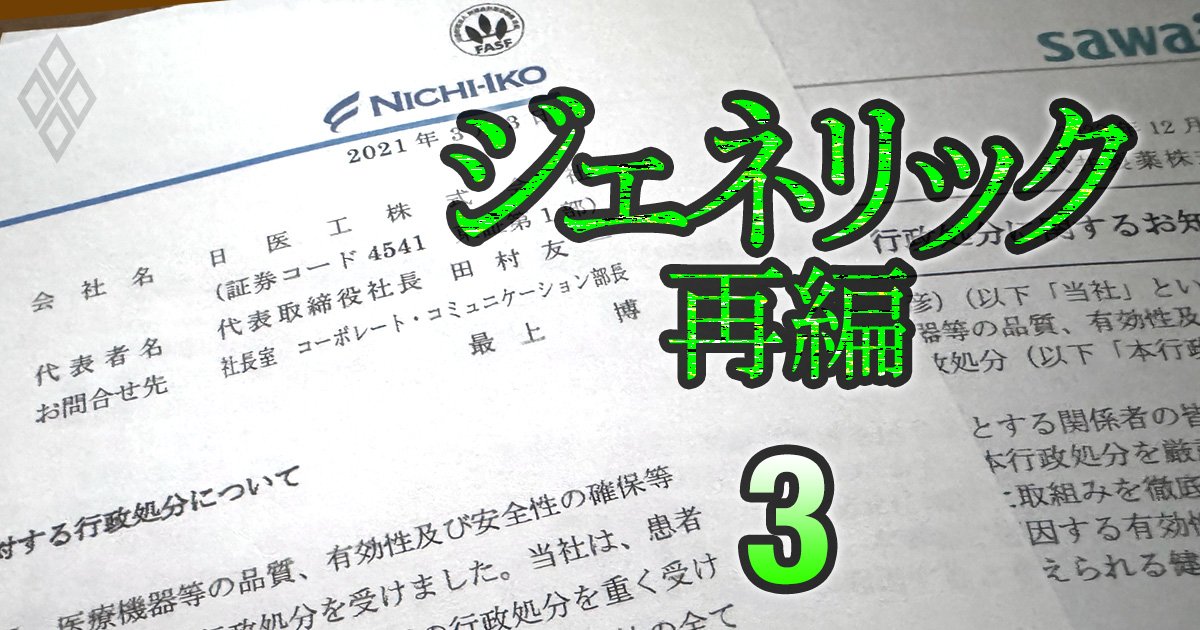◇「自分、今日辞めた会社に戻りや」
清掃員は、実はインドの神様ガネーシャであった。ガネーシャには様々なご利益があるが、特に重要なのは「障害を取り除く神」であるということだ。ガネーシャはこれまでも数々の偉人の前に現れ、その夢を叶えてきたのだという。しかし、神様の世界で「もとから才能のある人間にのっかってるだけ」と評されたことに腹を立て、ゼロから偉人を育てるために、「平凡力」の抜きんでた主人公のもとに降臨したのだ。失敗すればガネーシャはゾウに生まれ変わり、名前にゾウのつく食べ物しか食べられなくなってしまう。
ガネーシャはさっそく主人公を偉人へと育て上げるため、主人公の夢を聞く。ところが、主人公には夢と呼べるものが一切ない。さしものガネーシャでも、かなえるべき夢のない人間相手では手の打ちようがない。
とんでもない大飯喰らいのガネーシャはその食費を賄うためにも、衝撃的な一言を放つ。「自分、今日辞めた会社に戻りや」。
◇「夢って必要なものでしょうか」
翌日、主人公が恐る恐る出社すると、包帯を巻いた課長の姿があった。課長は前日の記憶を失くしていたようだったが、主人公への当たりの強さは変わらない。それどころか、怪我をした課長の補佐のため、デスクを課長の目の前に変えられてしまう。
主人公が意気消沈して帰宅すると、ガネーシャのペットであるバクが現れる。バクは小動物のようなかわいらしい姿に似合わず口が悪く、「気安く触ろうとすんじゃねえよ、夢なし芳一が」と主人公を罵倒する。バクは夢を食べて生きているが、“本物の夢”にはなかなか出会えないと嘆いていた。
そんなバクとガネーシャに、主人公は「夢って必要なものでしょうか」と疑問を口にする。主人公は子供のころからずっと周囲に「夢を持て」とプレッシャーをかけられてきた。そうして持った夢は、結局周囲の期待に応えるためのものにすぎなかった。
その主人公の疑問に対し、ガネーシャはさらりと「ワシ、夢を持たなあかんなんて一言も言うてないで」と答えた。拍子抜けする主人公に、ガネーシャは“本物の夢”の幻を見せる。夢がないときには面倒で苦痛にしか感じられなかった仕事が、夢を持った途端に輝き出して見えた。仕事はやりがいに満ち、すべての作業が自分の夢につながっているような感覚は、驚くほど魅力的だった。
「夢にはな、ものごとの『意味』を変えてしまう力があるんや」とガネーシャは語る。「それはつまり、人生が輝き出す、ちゅうことや」。
“本物の夢”の力を知った主人公に、ガネーシャは、夢を見つけるための課題を課す。