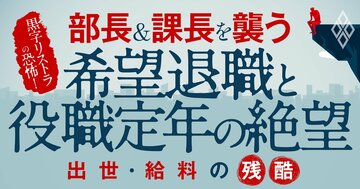マルクス『資本論』の枠組みは通用するか
こうなると、何が起こるか。それは資本の「野生化」だ。筆者はそう考えている。
自由奔放に、勝手気ままに国境を越えて動く資本に対して、資本主義の枠組みは制御力を失った。野生化した資本の狂暴性を抑え込めるものがなくなっているのである。
今日の資本は、『資本論』が執筆された時のようには動いていない。ただし、労働に対する搾取(さくしゅ)の基本原理が崩れたわけではない。『資本論』の中でマルクス先生が、当時の工場現場の実態を描出し、そこで行われている「剰余価値創出」のカラクリを解明してくれる時、そこで語られていることは、まるで今日の労働現場に関するルポルタージュのようである。
だが、野生化した今日の資本は、当時の工場現場とは比べるべくもなく多様で広範な職場で、当時とは比べるべくもないあの手この手で、人々から余剰価値を吸い取っている。
こうなってくると、資本と対峙する関係にある労働についても、その21世紀的有り方を追求する研究や分析が展開される必要があるのではないか。つまり、「21世紀の資本」、その生態に焦点を当てた画期的著作が書かれている以上、それと対をなす姉妹編として、「21世紀の労働」が書かれるべきだと考えられるのである。
アダム・スミスは労働をどうとらえていたか
ここで経済学の生みの親、アダム・スミス先生の労働観を見てみよう。この人の労働観はなかなか厄介だ。なぜなら、そこには大いなる二面性があるからだ。スミス先生における労働観の二面性は、一方で「労働犠牲説」の観点を打ち出しながら、その一方で、「労働こそ、全ての商品の真の価値の尺度だ」と言っているところにある。
『国富論』の中でスミス先生が労働を語るに当たって、“toil and trouble”(労苦と手間)という表現を使っていることは、よく知られている。この言い方からすれば、労働を願わくは避けるべき苦役だと見なしていたように思われる。しかも先生は、労働者が一定量の労働に携わることは、それに見合って、自分の自由と安楽と幸福を犠牲にすることを意味しているとも言っている。これが労働犠牲説の労働犠牲説と言われるゆえんだ。
ところが、一方で先生は、「労働価値説」の創始者だ。この論理の下に、当時の重商主義者たちの金銀財宝至上主義を厳しく糾弾したのである。
先生は、労働は苦役だと主張して労働を毛嫌いしているようでありながら、それに携わる者たちには高い賃金が払われるべきだと主張した。
それが、スミス先生の「高賃金論」である。
我々は「労苦」にふさわしい報酬を得ているか?
働く人々がその「労苦と手間」にふさわしい報酬、すなわち高賃金を得ることは、大いに正当性があると思われる。ところが、『国富論』刊行当時においてはそうではなかったのである。
高賃金論にことのほか強く異を唱えたのが、重商主義者たちだった。
彼らは、本質的に怠け者である労働者たちをしっかり働かせるためには、賃金は低くなければダメだと考えていた。また、労働者の所得が増えれば、彼らは贅沢品にカネを無駄使いする。すると贅沢品の輸入が増えて、貿易収支が悪化する。高賃金は生産コストを高めて、輸出品の国際競争力を低下させる。これまた貿易収支悪化原因だ。貿易による金銀財宝の確保を至上命題とした重商主義者たちにとって、高賃金は、あらゆる意味で天敵だったのである。
こんな状況だったからこそ、スミス先生は高賃金論を主張したのである。高賃金にすれば労働者は高賃金を喜び、一段の高賃金化を目指してさらに懸命に働く。すると労働生産性は上がり、国際競争力は低下するどころか、強化されますよ。スミス先生はそう主張した。労働観を前近代から近代へと導くことが、スミス流高賃金論に込められた先生の思いだったと言えるだろう。
少なくとも日本に関する限り、現状は、スミス先生の高賃金論に適っていない。かれこれ30年間にわたって賃金低迷状態が続いている。この状態は、スミス先生が敵対した重商主義者たちをさぞや喜ばせることだろう。日本の賃金低迷は、21世紀の資本による、21世紀の重商主義の表れだと言えるかもしれない。