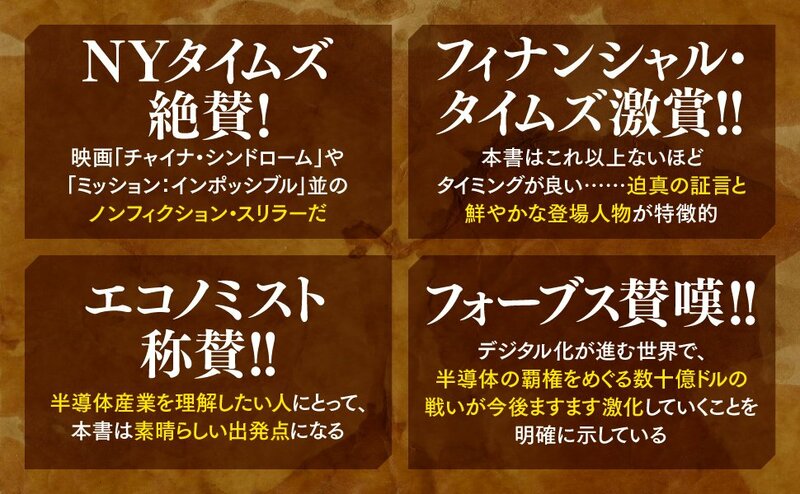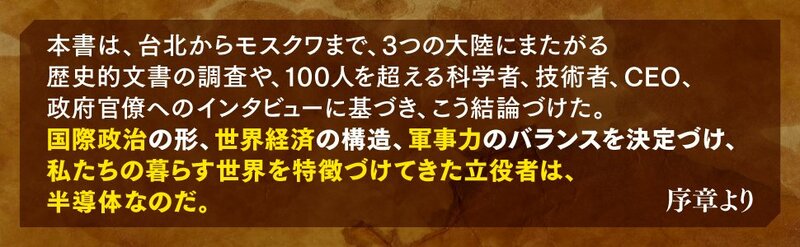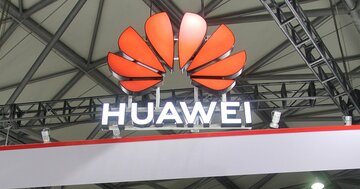NYタイムズが「映画『チャイナ・シンドローム』や『ミッション:インポッシブル』並のノンフィクション・スリラーだ」と絶賛! エコノミストが「半導体産業を理解したい人にとって本書は素晴らしい出発点になる」と激賞!! フィナンシャル・タイムズ ビジネス・ブック・オブ・ザ・イヤー2022を受賞した超話題作、Chip Warがついに日本に上陸する。
にわかに不足が叫ばれているように、半導体はもはや汎用品ではない。著者のクリス・ミラーが指摘しているように、「半導体の数は限られており、その製造過程は目が回るほど複雑で、恐ろしいほどコストがかかる」のだ。「生産はいくつかの決定的な急所にまるまるかかって」おり、たとえばiPhoneで使われているあるプロセッサは、世界中を見回しても、「たったひとつの企業のたったひとつの建物」でしか生産できない。
もはや石油を超える世界最重要資源である半導体をめぐって、世界各国はどのような思惑を持っているのか? 今回上梓される翻訳書、『半導体戦争――世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』にて、半導体をめぐる地政学的力学、発展の歴史、技術の本質が明かされている。発売を記念し、本書の一部を特別に公開する。
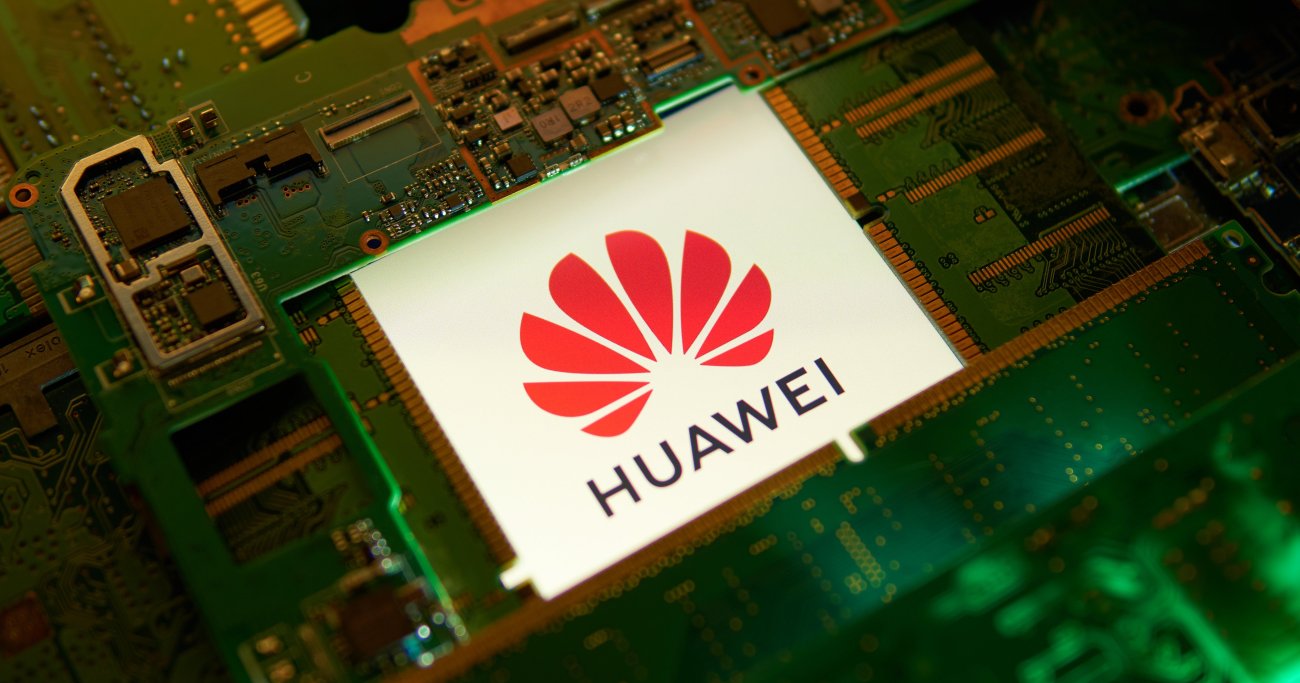 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
ファーウェイの機器を使わずに
携帯電話が利用できる国はほぼない
糊のきいた背広にスラックス、ボタンをはずした襟元、快活な笑み。自身の創設した中国のテクノロジー企業、ファーウェイの本社でメディア・インタビューに応じる任正非(ジンセイヒ)は、どこにでもいるシリコンバレーの経営幹部と変わらなく見える。
ある意味では、実際そのとおりだ。ファーウェイの通信機器、つまりスマートフォンと通話、写真、メールの送受信を行なう基地局の無線機は、今や世界のモバイル・インターネットの屋台骨だ。一方、ファーウェイのスマートフォン部門は、つい最近まで、携帯電話の出荷台数でアップルやサムスンと肩を並べ、世界最大級だった。
また、同社は、海中の光ファイバー・ケーブルからクラウド・コンピューティングまで、その他の種類の技術インフラも提供している。
多くの国々では、ファーウェイの機器をいっさい使わずして携帯電話を利用すること自体が不可能だ。それはマイクロソフト製品を使わずにPCを利用したり、(中国以外で)グーグルを使わずにインターネットを閲覧したりするのと同じくらい難しいのだ。
しかし、ファーウェイはひとつの大きな点で、世界のほかの大手テクノロジー企業とは異なる。アメリカという国家安全保障国家〔国家安全保障への懸念が優勢となり、国内の諸目的がそれに従属している国家〕との20年にわたる闘いだ。
ファーウェイが中国政府のスパイ活動において果たした役割について報じたアメリカの新聞の見出しを読むと、同社は中国の治安当局に付随する形で始まったと結論づけるのは簡単だろう。
ファーウェイと中国国家のつながりは十分に立証されているが、同社が世界規模の事業を築くに至った経緯を説明するにはほとんど足らない[1]。
ファーウェイとサムスンの共通点とは
ファーウェイの拡大について理解するには、同社の軌跡を、別のテクノロジー系複合企業、韓国のサムスンと比較するほうがわかりやすいかもしれない。任は、サムスン創設者の李秉喆(イビョンチョル)より世代がひとつ下だが、ふたりの経営モデルは似ている。
李は3つの戦略を用いて、サムスンを干物業者から、世界最先端のプロセッサやメモリ・チップを量産するテクノロジー企業へと成長させた。
ひとつ目に、熱心に政治的人脈を築き、規制面の優遇や安価な資本を得ていった。ふたつ目に、欧米や日本で開拓された製品に目をつけ、同品質の製品をより安価につくるすべを学んでいった。3つ目に、新規顧客を開拓するだけでなく、世界の一流企業との競争を経験に変えるため、徹底的にグローバル化を進めた。
この3つの戦略により、サムスンは韓国のGDP全体の1割相当の収益を上げる世界有数の企業に成長していったのだ。
果たして、中国企業に同様の戦略は実行できるのだろうか? 中国のテクノロジー企業の大半は、そこまで世界重視でない別の戦略を採用した。中国の圧倒的な輸出力とは裏腹に、中国のインターネット企業は収益の大半を、規制や検閲に守られた国内市場に頼っている。
テンセント、アリババ、ピンドゥオドゥオ、メイトゥアンは、国内市場での優位性がなければ取るに足らない存在だろう。実際、国外に進出した中国のテクノロジー企業は、競争に勝てないことが多かった。
対照的に、ファーウェイは最初期の時代から外国との競争を視野に入れてきた。任のビジネスモデルは、アリババやテンセントとは根本的に異なる。外国で発明されたコンセプトの高品質版を、より安価につくり、世界に販売して、世界の競合企業から国際的な市場シェアを奪い取るのだ。
このビジネスモデルを通じて、サムスンの創設者たちは巨万の富を築き、サムスンを世界のテクノロジー業界のエコシステムの主役に据えたのだ。ごく最近までは、ファーウェイも同じ道を歩んでいるように見えた。
電話交換機の転売で大儲け
ファーウェイの国際志向の考え方は、1987年の創設からありありと見て取れた。任は、中国南部の貴州(きしゅう)省の農村部で、高校教員の両親のもとに育った。
四川(しせん)省の重慶(じゅうけい)〔1997年に四川省から分離し、現在は中国の直轄市〕で工学を学んだのち、中国軍に所属し、本人いわく衣類用の合成繊維の生産工場で働いていたという[2]。
中国軍を去ったあと(ただし、その状況や、彼が本当に軍との関係を完全に断ち切ったのかどうかについては、疑問の声もある)、まだ香港国境の真向かいにある小さな町にすぎなかった深センに移住する。
当時、依然としてイギリスの支配を受けていた香港は、全体的に貧しい中国南岸沿いにぽつんと点在する繁栄の地だった。
その10年ほど前、中国指導部は経済改革に着手し、経済成長を促す手段として、個人に民間企業の設立を認める社会実験を始めた。
とりわけ深センは、「経済特区」に選定された数都市のなかのひとつとして、規制が解除され、外国からの投資が促進された。香港マネーが流れ込み、中国の起業家の卵たちが規制からの解放を求めて大挙して訪れると、深センは急成長を遂げていく。
任が目をつけたのは、電話の発信者を相手先に接続する電話交換機を輸入する機会だった。5000ドルを元手に、彼は香港から電話交換機の輸入を始める。国境の反対側の取引先は、彼が電話交換機の転売で大儲けしていることに気づくと、彼との取引を停止してしまった。そこで、彼はみずから交換機を開発することにした。
1990年代初頭時点で、ファーウェイでは数百人が研究開発に従事し、主に交換機の開発に携わっていた[3]。以来、同社の電気通信インフラはデジタル・インフラと融合してきた。
電話の音声を送信する基地局は、ほかの種類のデータも送信する。つまり、ファーウェイの機器は今や、世界中のデータを送信するうえで重要な(そして、多くの国々では不可欠な)役割を果たしていることになる。
現在、ファーウェイは、フィンランドのノキア、スウェーデンのエリクソンと並び、基地局装置を提供する世界の3大企業のひとつに数えられる。
「知的財産権の侵害」だけでは
ファーウェイの成功は説明できない
ファーウェイを批判する人々の多くは、同社の成功は盗んだ知的財産の上に成り立っている、と主張しているが、それは全面的に正しいとはいえない。
確かに、同社は過去のいくつかの知的財産権の侵害を認めているし、それよりはるかに多くの侵害で告発されてきた。
たとえば、2003年、ファーウェイは同社のあるルーター内で使われているコードの実に2%が、アメリカの競合企業であるシスコ・システムズからそっくりそのままコピーされたものであることを認めた[4]。
一方、カナダの新聞各紙は、2000年代にカナダの大手通信会社のノーテルネットワークスに対し、中国政府の支援するハッキングやスパイ活動があったとするカナダの諜報機関の見解を報じた。そのことがファーウェイにとって有利に働いたという[5]。
確かに、知的財産の窃取はファーウェイにとって有利に働いただろうが、それだけでは同社の成功は説明できない。どれだけ多くの知的財産や企業秘密を手に入れたところで、ファーウェイほど巨大な企業を築くには足らないのだ。
同社は、コストを押し下げる効率的な製造工程を開発し、顧客が高品質だと認める製品を生み出した。と同時に、ファーウェイの研究開発費は世界トップクラスであり、中国のほかのテクノロジー企業の何倍にもおよぶ。
ファーウェイの年間約250億ドルという研究開発費と肩を並べるのは、テクノロジー企業のグーグルやアマゾン、製薬会社のメルク、自動車メーカーのダイムラーやフォルクスワーゲンなど、ほんの一握りの企業にすぎない[6]。
知的財産を盗み出した過去を差し引いたとしても、ファーウェイの数十億ドル規模の研究開発費は、ソ連のゼレノグラードの「コピー」戦略や、お金をかけずに半導体産業に参入しようとしてきた多くの中国企業とは、まったく異なる精神を浮き彫りにしている。
ファーウェイの経営幹部たちは、同社が研究開発に投資するのは、シリコンバレーを手本にしてきたからだ、と口を揃える。任は1997年にファーウェイの経営幹部たちを連れてアメリカを視察し、HP、IBM、ベル研究所といった企業を訪問したといわれる[7]。
彼らは研究開発だけでなく、効果的な経営プロセスの重要性も確信して帰ったそうだ。1999年、ファーウェイはIBMのコンサルティング部門を雇い、世界的企業の運営方法を教わった。
IBMの元コンサルタントの話によると、ファーウェイは合計収益が10億ドルにも満たなかった1999年に、5000万ドルのコンサルティング料を支出していたという。
あるときなど、業務プロセスを一から築き直すため、100人ものIBMのスタッフを雇っていた。「彼らが技術的な課題に大きく怖じ気づくことはなかった」と前出のコンサルタントは言う。「しかし、経済やビジネスの知識となると、自分たちが100年遅れていると言わんばかりの態度だった[8]」
IBMや欧米のコンサルタントたちの力を借り、ファーウェイはサプライ・チェーンの管理、顧客需要の予測、一流のマーケティングの開発、世界的な製品販売のスキルを身につけていった。
ファーウェイはその能力を、同社が「狼性文化」〔野(高い野心)、残(困難を生き抜く力)、貪(貪欲さ)、暴(逆境をはねのける荒々しさ)を4つの特徴とする中国の企業文化〕と称する軍国主義的な精神と結びつけた。
『ニューヨーク・タイムズ』紙の報道によれば、同社のある研究所の壁には、「犠牲は軍人の最大の大義であり、勝利は軍人の最大の貢献である」という書が飾られているという[9]。
1 Chairman Mike Rogers and Ranking Member C. A. Dutch Ruppersberger, “Investigative Report on the U.S. National Security Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and ZTE,” Permanent Select Committee on Intelligence, U.S. House of Representatives, October 8, 2012, https://republicans-intelligence.house.gov/sites/intelligence.house.gov/files/documents/huawei-zte%20investigative%20report%20(final).pdf, pp. 11-25.
2 William Kirby et al., “Huawei: A Global Tech Giant in the Cross-fire of a Digital Cold War,” Harvard Business School Case N-1-320-089, p. 2.
3 Kirby et al., “Huawei”; Jeff Black, Allen Wan, and Zhu Lin, “Xi Jinping’s Tech Wonderland Runs into Headwinds,” Bloomberg, September 29, 2020.
4 Scott Thurm, “Huawei Admits Copying Code from Cisco in Router Software,” Wall Street Journal, March 24, 2003.
5 Tom Blackwell, “Exclusive: Did Huawei Bring Down Nortel? Corporate Espionage, Theft, and the Parallel Rise and Fall of Two Telecom Giants,” National Post, February 20, 2020.
6 Nathaniel Ahrens, “China’s Competitiveness,” Center for Strategic and International Studies, February 2013, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130215_competitiveness_Huawei_casestudy_Web.pdf.
7 Tian Tao and Wu Chunbo, The Huawei Story(Sage Publications Pvt. Ltd., 2016), p. 53.
8 のちにファーウェイの従業員となった元IBMコンサルタントへの2021年のインタビューより。
9 Raymond Zhong, “Huawei’s ‘Wolf Culture’ Helped It Grow, and Got It into Trouble,” New York Times, December 18, 2018.
(本記事は、『半導体戦争――世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』から一部を転載しています)