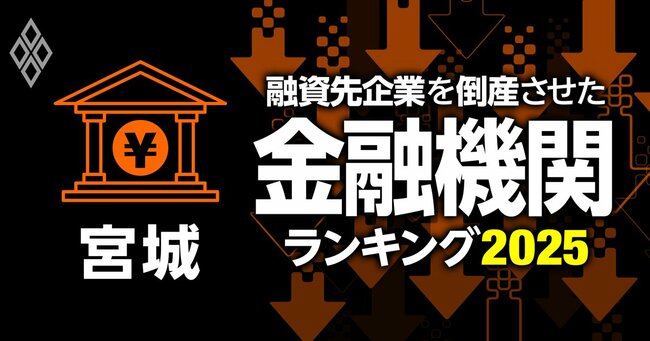公的資金の注入とともに
不採算な保養所は全て売却
現在、このような保養所施設はもうない。
バブル崩壊後、都市銀行各行は不良債権問題であえいでいた。北海道拓殖銀行が破綻したことを皮切りに、国からの公的資金が各銀行に注入された20世紀末。不良債権処理が経営の足かせになり、単独では生き残れなくなると、13行の都銀は合併を繰り返し5行に収れんしていく。
21世紀に入り、小泉政権の構造改革のひとつである竹中プラン(当時の竹中平蔵金融担当相をブレーンに置き抜本的に取り組んだ「金融再生プログラム」が正式名称)で公的資金を注入されながら、不良債権処理は加速。保養所施設に代表される不採算な設備は、全て売却せざるを得なかった。
公的資金注入により実質的に国有化されたも同然の都市銀行にとって、銀行が従業員の余暇充実を自前で用意する余裕など、もはやなかったのだ。都内の一等地にあった施設はオフィスビルやタワーマンションに姿を変え、リゾートにあった施設は開発会社が買い取り、手を加えて営業を続けている。
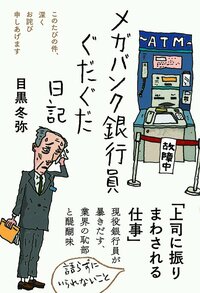 『メガバンク銀行員ぐだぐだ日記』(三五館シンシャ)
『メガバンク銀行員ぐだぐだ日記』(三五館シンシャ)目黒冬弥 著
その代わりに、任意で加入できる民間の福利厚生サービスが用意された。月に数百円の天引きで、提携しているホテルや旅館、レストランを割安な価格で利用できるサービスだ。これなら、嫌な上司や同僚とも会わずに済むだろう。
何万人もの従業員全てが満足できる制度などあり得ないし、そもそも仕事に忙殺され、旅行へ行く時間も心の余裕もない。ましてやシステム障害が勃発すれば、いつ何時であろうと支店に駆けつけなければならない。保養所施設の所有は、昭和の大企業ならではの優越感だったのかもしれない。
この厄払いの後も、さまざまな出来事が私を襲った。悲喜こもごもだった。そして、私は今もこの銀行を愛している。