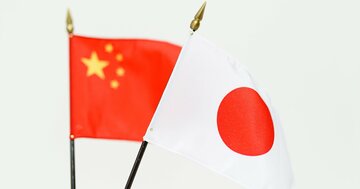写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
国防七校の教職者が
日本で産業スパイ
国立研究開発法人「産業技術総合研究所」の上級主任研究員、権恒道容疑者(59)が、2018年4月、自身が研究している「フッ素化合物」に関する情報を中国の民間企業にメールで送り、営業秘密を漏えいしたとして、警視庁公安部は15日、不正競争防止法違反(営業秘密の開示)で同容疑者を逮捕した。
読売新聞の報道によれば、漏えいされた研究情報は「フッ素化合物の合成に関わる先端技術」であり、地球温暖化対策などに役立つ可能性があるとされている。
権容疑者は2002年4月から産総研に勤務していたが、そもそも中国人民解放軍と関連がある「国防七校」の一つである南京理工大学の出身。そして、一部の期間では「国防七校」の一つである北京理工大学の教職を兼任していたと報じられているほか、フッ素化学製品製造会社「陝西神光化学工業有限公司」の会長も務めていたという。
時事通信の報道では、権容疑者は2018年1月の全国科学技術大会で、地球温暖化を防ぐフッ素化合物の研究実績が評価され、「国家科学技術発明2等賞」を授与され、会場を訪れた習近平国家主席とも面会したという。
権容疑者の出身である南京理工大学や教職を兼任した北京理工大学をはじめとする国防七校は、中国の最高国家権力機関の執行機関である国務院に属する国防科技工業局によって直接管理されている大学であり、中国人民解放軍と軍事技術開発に関する契約を締結し、先端兵器などの開発や製造を一部行っており、その危険性は周知の事実だ。経済産業省のキャッチオール規制に関係する「外国ユーザーリスト」にも北京理工大学は掲載されている。