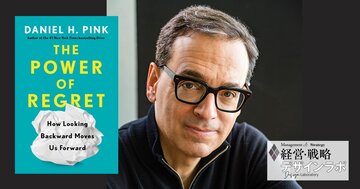Photo by Teppei Hori
Photo by Teppei Hori
4期連続減益という業績低迷期に旭硝子(現・AGC)のCEOに就任した島村琢哉氏。就任後、本格的な組織改革に着手し、東南アジアの拠点を強化。同時に、新規事業の成長も後押しすることで、「既存事業の深化」と「新規事業の探索」を同時に追求する「両利きの経営」の道筋をつけた。「両利きの経営」の提唱者のひとり、チャールズ・オライリー氏(スタンフォード大学経営大学院教授)らもこれを評価し、AGCを調査訪問。日本企業として初の「両利きの経営」の事例研究となった。島村氏に、AGCのグローバル経営におけるリーダー像や組織風土づくり、経営プラットフォームの構築の詳細を語ってもらった。(構成・文:奥田由意、編集:ダイヤモンド社編集委員 長谷川幸光)
他と違う「企業の存在意義」は何か?
原点に戻って再定義した
なぜ私たちAGCが、「両利きの経営」をするに至ったのか? 「両利きの経営」を推進するためには何が必要なのか?
実は、経営理論を学んでから「両利きの経営」を行ったのではなく、自分たちが置かれた状況の中で、もがきながらやってきたことが結果的に「両利きの経営」になっていた、これが正直なところです。チャールズ・オライリー教授には「理論を学んでいなかったのか」と叱られましたが(笑)。
人間には、ルーティンの仕事が目の前にあると、将来のための重要な仕事を後回しにしてしまう「グレシャムの法則」といわれる性質があります。安定的な収益を出せば出すほど、過去の成功体験にとらわれて、変革がしづらい。
そのため、成熟した企業というのは、なかなかイノベーションを創出することができません。
経済学者のヨーゼフ・シュンペーターがかつて、「イノベーション」を「新結合」と定義しました。既存の多様なものを組み合わせたり、これまでの私たちの考え方を変えたりすることで、新たな変化へ結び付けていく。「画期的な技術を開発する」ではなく、「目線を変え、考え方の発想を変える。すると、新たな『解』が見つかる」「誰もが見ているのに、誰も気付いていないことに、気付くこと」がイノベーションではないかと思います。
企業が30年間、存続できる確率は、わずか0.021%だそうです。一方で、世界に100年を超える企業は現在、約3万社あるといわれています。
では、企業が100年を超えて生存するにはどうすれば良いのでしょうか? これには3つの条件があるといわれています。