信孝家臣の斎藤玄蕃允(利尭)・岡本太郎左衛門(良勝)宛の10月18日付書状写に記されている。同書状は、実質的には信孝宛であり、勝家に向けてのものでもある。24か条にわたる長文で、最後の1条で葬儀のことに触れている。原本が確認されておらず、写のかたちで伝わっている。宛所や文言などの異同もある。写文書を総合して意訳する。
「上様の御仏事について、信孝様、信雄様に養子の秀勝から申し上げましたが、お返事もなく、また宿老衆も執り行う予定がありませんでしたので、これでは世間への体裁もよくないと判断しました。御存じのように私(秀吉)は小者一僕の身分でしたが、上様のお陰で国々を拝領する身分になりました。上様の御恩は須弥山よりも高いと存じており、身分不相応ながら御仏事を執り行いました。上様の後継者が六十余州を平定してからの御仏事であれば、追い腹を切っても恨みはありません」
信雄、信孝に葬儀のことを打診したが、返事もなく、勝家以下の宿老衆も執り行う予定がなかったので、秀吉が身分不相応ながら挙行した、という内容だが、実際には名代候補や勝家らを出し抜いて葬儀を行った言い訳に過ぎない。信長の葬儀を挙行した者が後継者とみなされることを睨んでのことである。
大徳寺での葬儀を境に
勝家と秀吉は決定的に決裂
秀吉は大徳寺で10月11日から17日まで法事を行い、葬礼は15日に挙行。秀吉はこの大イベントに莫大な費用を費やして、後継者をアピールした。当日の葬礼には、見物人が群集する関心の高さだった。葬儀の前日には、尾張から信雄、美濃から信孝が翌日の葬儀を中止するために上洛してくるという風聞があった。『蓮成院記録』には、9月2日、信長の葬礼を挙行する旨を公表したところ、滝川一益、丹羽長秀、長谷川秀一、柴田勝家、信孝の名代、および池田恒興らが上洛して中止しようとした、という噂があったが、異議なく挙行となったと記している。
真偽は不明だが、秀吉陣営の丹羽長秀、池田恒興も反対側に回ったとすれば、秀吉の独断で挙行したことになる。もっとも、長秀は名代として青山助兵衛(宗勝)ら3人を派遣して秀吉への体裁を繕っている。フロイスの書簡には「五畿内のほとんどの領主が参列し」た、とあるが、秀吉傘下の領主のことであろう。
勝家の対応ははっきりしない。前述のように中止を迫ろうとした風聞があったようだが、具体的な動きは確認できない。
本能寺の変後、光秀討伐で後れをとった勝家は、対秀吉戦略でも後手後手に回った印象である。主導権を握られたまま、賤ヶ岳の戦いを迎えた感すらある。清須会議以降の勝家の動向はほとんどわからない。逆に秀吉は、勝利したことも影響しているが、残存史料が勝家に比べると格段に多い。秀吉の生涯で最も脂が乗っていた時期であり、精力的な活動が見えてくる。結果的には、大徳寺の葬儀を境に勝家と秀吉は決定的に決裂したと見るべきであろう。
この頃の勝家の考えが分かる数少ない史料が、10月6日付の堀秀政宛の勝家覚書写である。5か条から成る。実質的には秀吉に宛てたものである。
1、勝家としては、秀吉と決めた約束に相違はない。
2、清須会議で決定したことが守られず、皆が不審に思っている。もともと秀吉と勝家は仲が良かったので、天下静謐のためにも腹蔵なく相談しよう。
3、勝家は、清須会議で配分された長浜城に付随する領地以外は一切取り込んでいない。
4、三法師様を岐阜城から移すことについては、信孝様にも丹羽長秀にもそのようにすることを伝えている。
5、本能寺の変後の混乱は一応は収まったが、まだまだ四方に敵がいるなかで、内輪揉めしている時ではない。上様がいなくても外敵を退治することが本筋である。上様は家康を助けるためにたびたび出馬されて武田氏を滅ぼした。北条氏は上様ご在世の時には命令を聞いていたが、変後は豹変し、家康と敵対している。織田家中が協力して北条氏を討ち果たせば、忠義であり、上様のお弔いにもなり、さらには天下の名誉である。しかし、そうしたことをせず、秀吉は自分の領地に新城(山崎城)を構築し、好き勝手に振る舞っている。これは誰を敵としての行動なのか。私(勝家)は人柄が悪い(「我人間柄悪候」)が、親しくして、上様がご苦労されて分国を治められた御仕置などを守って静穏にしていくべきところなのに、内輪揉めで敵に領国を奪われることは本意ではない。
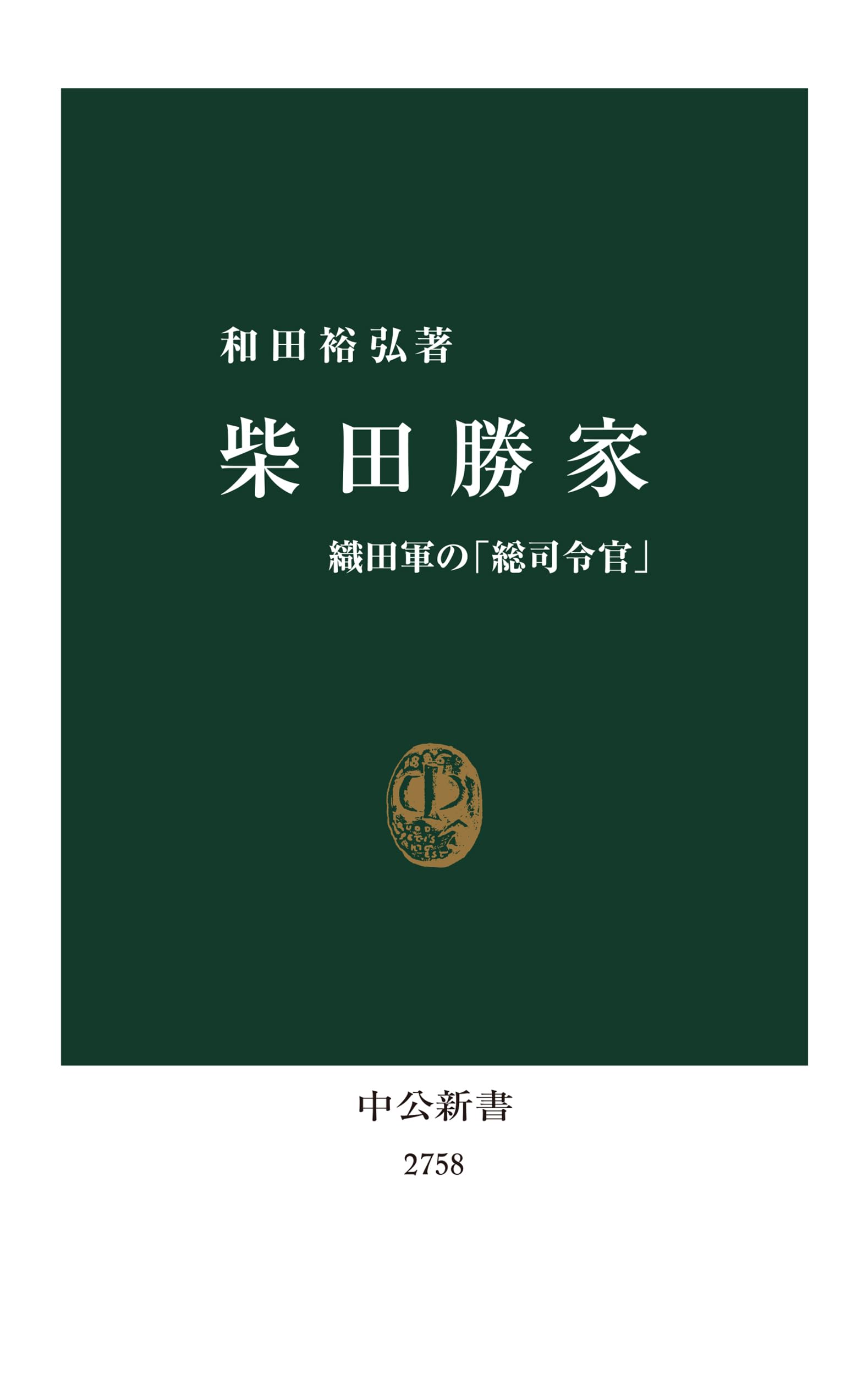 『柴田勝家―織田軍の「総司令官」』(中央公論新社) 和田裕弘 著
『柴田勝家―織田軍の「総司令官」』(中央公論新社) 和田裕弘 著
以上である。「我人間柄悪候」の部分は、先に記したように勝家が自分の人間性を卑下したようにも読めるが、「我人」(勝家と秀吉)の「間柄」が「悪」くなったが、親しくしていこうと呼びかけているようにも解釈できる。秀吉は本能寺の変直前の時点でも勝家配下の溝江大炊允(長澄)と連絡をとっており、勝家との関係は巷間言われているほど悪くなかったと思われる。しかし、この時点では秀吉の傍若無人な独断専行を非難し、秀吉がそういう覚悟であるなら「無念至極」と結んでおり、実際にはもはや修復不能と悟っていただろう。秀吉も10月12日付の書状で、勝家との関係修復を仲介しようという信孝の申し出を拒絶しており、対決は避けられない情勢になっていた。
勝家が最も恐れたのは、織田家の身内同士の争いである。勝家の書状にも「結句共喰にて」滅ぶことを憂慮している。しかし、野望に燃える秀吉から見れば、現状維持派の戯言に過ぎない。
秀吉は、清須会議で有利な状況を作り出したことで、織田家宿老の筆頭の地位はもちろん、織田家の簒奪を徐々に夢想し始めたのだろう。







