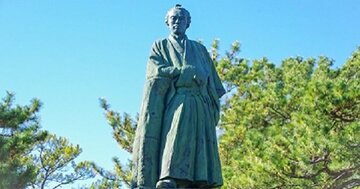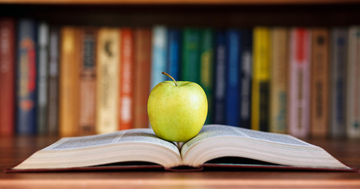12月15日に榎本は五稜郭で蝦夷地平定を宣言し、士官以上の選挙で総裁に榎本が、副総裁に松平太郎(元陸軍奉行並)が選出された。
一方、新政府は反攻準備を着々と進めていた。明治2年(1869)1月の段階で青森口の新政府軍は、陸上兵力で約3000人、海上からは3月18日から20日にかけて海軍参謀増田虎之助(明道。佐賀藩士)が率いる艦隊が宮古湾へ到着する。
4月6日、新政府軍の第一陣2000名あまりは、青森を出港。4月9日に乙部(現在の北海道爾志郡乙部町)へ上陸した。
乙部上陸以来、進撃する陸軍部隊への砲撃支援を行っていた新政府艦隊は、榎本軍が五稜郭周辺に追い込まれていくにつれ作戦正面を箱館湾口に集中できるようになり、5月に入ると箱館湾を舞台に連日のように戦闘が繰り広げられた。
蝦夷の地に見た夢よさらば
榎本の箱館占領は7カ月で終わった
五稜郭に追い詰められた榎本は降伏勧告を拒否するが、重ねての勧告についにこれを受け入れ、5月18日に五稜郭を開城した。榎本軍の鷲ノ木上陸以来、約7カ月にわたって繰り広げられてきた箱館戦争はこうして幕を閉じた。
人が歴史を学ぶにあたって最も慎むべきは全ての情報、全ての結果を知る全知全能の神となり、当時の人々を断罪する態度であると筆者は考えている。
その上で、榎本が敗者となったのは果たして歴史の必然だったのか、神の視点にならないよう気を付けながら考えてみたい。
奥羽越列藩同盟が成立した慶応4年(1868)5月初頭に時計の針を戻してみよう。事実として述べることができ、なおかつ恐らく榎本自身も認識していた前提条件は次のとおりである。
・旧幕府海軍は榎本が掌握しており、その意に反して行動する艦はない。
・徳川家処分がどのようなものになるか、情勢は予断を許さない。
・奥羽越列藩同盟は徳川家海軍の支援を望んでいる。
・関東、北越の戦況は新政府軍有利に進んでいるものの確定的ではない。
榎本が取り得た選択肢の一つ目が徳川家の恭順方針遵守である。榎本には不本意な選択肢だが、主家の方針と一致しているだけに行動の名分が最も立ちやすい。軍事的には徳川家が保有する品川、浦賀、そして横須賀で建設中の造修施設が利用可能となり、武器、弾薬、艦隊脱走後に榎本が確保に苦しんだ石炭も、幕府が構築した供給システムの恩恵に与かれる。ただし、この場合いったん全ての艦船を明け渡さなければならず、徳川家の新たな所領に応じて差し戻される約束の艦船がどれほどの数になるのか、そもそもこの約束は守られるか保証の限りではない。