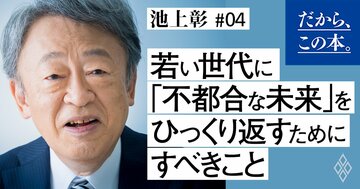こういう提言を市民が受け容れること、つまり、「善良で賢明な人々にはより大きな影響力を持つ資格がある、と市民が考えることは、市民にとって有益なのだから、国家がこの信念を公言し、国の制度に体現させることは重要である」とミルは論じている。
なぜ、このような趣旨の制度が必要かと言えば、それが実際に知性の確保に役立つばかりではない。無知と知性を同等に扱わないという制度の精神が国民に影響を与えるからである。また、複数投票が与えられるのは少数者に限定されていて、この仕組みで少数者だけで国政を左右することはないと想定されていた。
それでもなお、「善良で賢明な人々」の影響力確保のために、高学歴や知的職業への従事者に複数投票権を認めるというミルの主張を目にすると、おそらく多くの読者は違和感を覚えるだろう。筆者としても、平等選挙の精神を健全に保つためには、不公平感を与えることなしに、すぐれた人の知見を国政に活かす別の方法を探究した方が得策に思える。
その一方で、平等選挙の原則を一貫して重視するのであれば、いわゆる「1票の格差」と呼ばれている今日の事態についても、きちんと答えを出す必要があるとも感じる。そういう意味で、今もなお示唆的な議論だと言えるだろう。
他者に対する権力行使である投票を
秘密のうちに行うのは正しいのか
ミルが「制度の精神」との関連で取り上げているテーマで、もう一つ注目されるのは、秘密投票(バロット)の問題である。
イギリスでは、1872年に秘密投票法が制定されるまで、庶民院や地方自治体の選挙は、自分が支持する候補者の名前を声を出して示すといった方法による公開投票だった。
ベンサムや父親のジェイムズ・ミルなどの哲学的急進派は、公開投票は地元有力者の圧力や買収の温床であり、旧来の地主支配体制を支える柱の一つだとみなし、秘密投票を政治改革の重要な項目の一つとしていた。ミルも、支持の立場を維持していた。
ミルがこの立場を変えたのは、1850年代になってからである。フランス2月革命の後、ルイ・ボナパルトが制度上は民主的な選挙によって大統領に選出されたことが、少なからず影響していると推測される。
ミルによれば、秘密投票は「制度の精神、つまり制度が市民の心に与える印象が、制度の働きの中で最も重要な部分を占める事例の一つ」である。その印象とは、人に知られることなく自分自身のために自分の都合に合わせて投票してよいのだ、という印象である。こうした印象は、投票を私的な権利だとみなす誤解につながる。しかし、投票は権利ではない。それは信託(trust)である。ミルは次のように力説している。