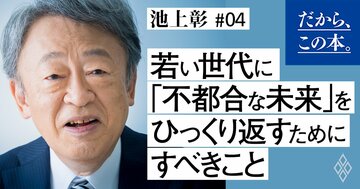『J・S・ミル 自由を探求した思想家』(中央公論新社)
『J・S・ミル 自由を探求した思想家』(中央公論新社)関口正司 著
権利の観念をどう定義し理解するとしても、人は誰も、他者に対して権力を行使する権利を(純粋に法律的な意味を別とすれば)持つことはできない。そうした権力はすべて、持つことが許されるとすれば、道徳的には、最も完全な意味で信託である。ところが、選挙人としてであれ代表としてであれ、政治的な役割を果たすということは、他者に対する権力行使なのである。
自分に権利のある家や債券を処分するとき、自由に思い通り処分してよい。権利の観念とはそうしたものである。投票も、権利であるなら同じように受け止められるだろう。
しかし、投票を家や債券と同様に自由に売ることは許されない。その意味で、投票は特殊な権利だと感じられている。この感覚は、鈍らせるのではなく、いっそう強化する必要がある。
投票の重要な意義は、たしかに自分の利益や自由を不当な侵害から守るのに役立つという点にある。しかし、投票は同時に、他者の未来も左右する。投票は社会全体に対する権力行使になる。
だから、投票は自分だけにかかわる自己決定と自己責任の問題ではなく、社会全体に対して責任を負うべき公共的行為である。投票者は、そうした権力を社会全体から信託されている。だから、投票を売ってはいけないのである。
ミルの考えでは、公開投票であれば、投票者は他者の視線を意識することで、投票の公共的理由について多少は考えざるをえなくなる。申し開きが立たないような利己的で浅ましい理由では、自分の体面が保てなくなるからである。人目を気にしたり見栄を張ったりといった同調志向の心理も、こういう公共的な効用がある場合には、ミルは活用に躊躇しない。
もっとも、公開投票が、ミルの期待しているとおりの効果を持つのかどうか、また、公開投票のメリットは、買収や強要を助長するというデメリットを上回るのかどうかといった点は、状況次第であるように思える。しかし、ここで目を向ける価値があるのは、その点よりも、制度の精神という問題の捉え方である。
投票制度の精神を問題にするとき、ミルが大前提にしていたのは、他者に権力を行使する権利は道徳的には絶対ありえない、という強い信念だった。だから、ミルは法律で定められた権利という文脈を除いて、権利という言葉は使わない。結論で賛否が分かれるとしても、じっくり議論する価値のある重要な問題である。