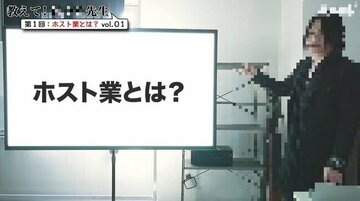西成で入居者をスカウトし
軽トラで連れて来る母親
ここで日雇い作業員やホームレスといった人たちに、母は、「住む家あるん?よかったらお姉さん、こう見えても家持っているからそこ住んでみいへん? それからまた今後のこと考えたらええやん」と声掛けし、予め借りていた軽トラックの荷台に何人かを乗せて連れて帰る。そして、そのまま入居となる。
 特にハウスクリーニングを行わなくても、このまま住むという人がエクストリーム層には多い。家に居ることが少なく荷物さえ置ければそれでいいという発想だ
特にハウスクリーニングを行わなくても、このまま住むという人がエクストリーム層には多い。家に居ることが少なく荷物さえ置ければそれでいいという発想だ
貧困ビジネスやNPOという言葉がない時代の話だ。ときにその筋の人に絡まれたり、警察から疎ましい目で見られるたりすることは、母と一緒にいた当時小学生だった俺の目にもわかった。
だが、そこはやはりまだ若い女性、また子どもの目から見ても美人だった母ならではの特権だろう。「ごめんなさい、誰にご挨拶したらええかわからんへんかってん。すみません」と母がにっこり微笑めば、最後はその筋の人も警察も、「ちょっと挨拶さえあればそれでええんや」で済んだ。そうした人たちの中には、「困ったことがあったら、いつでも俺に言うてや」と欠損した指を晒しつつ、名刺を差し出してきた男性もいた。
フリーランスで働いていた母同様、俺も本業こそフリーライターで、出版社からつけてもらった「経済ジャーナリスト」なる肩書で格好をつけているが、その実、収入は不安定で、カネの心配は尽きない。また、浮き沈みの激しい世界だ。今はよくてもこの先どうなるかわからない。そんな俺を心配して、母はよくこう言っていたものだ。
「お金貸してあげるから家を買いなさい。価格100万円くらいでいいの。それを生活保護受給の方に貸すの。家賃は行政から支払ってくれるから。しばらく我慢したら、貸したお家があなたの代わりにお金を稼いでくれるわよ――」
しかし当時の俺は、何冊かの投資指南書や経済解説本を世に出した後だったこともあり、金融畑の書籍著者として調子に乗りまくっていた。だからFXや日経ミニ先物といった投資商品こそが、投資の王道を行くと信じていた。