ロシア人独特の「トスカー」が
ウォッカを求めてしまうのか
●ジョーク「離婚」
モスクワのバー。友人がイワンに言った。
「おい、ボリスの奴、離婚したらしいぜ」
「ほう、なぜ?」
「あいつは本当に大酒飲みだからな。それで嫁さんがついに愛想を尽かしたらしい」
それを聞いたイワンがバーテンダーに言った。
「おい、ウォッカを10杯」
●ジョーク「パスポート」
EUは加盟国の総意として、ロシア政府にこう要求した。
「ロシア人のパスポートには、本人確認のため、泥酔時の写真を使用すること」
●ジョーク「毎日」
問い・ロシア人が1年で最もウォッカを飲むのが少ない月とは?
答え・2月
ウォッカの発祥地については、ロシアの他、ウクライナやポーランドも自称しており、熱い議論が繰り広げられている。互いに譲れないことのようであるらしい。
広大な国土を持つ多民族国家であるロシアでは、文化的な幅も広い。強い酒が好まれるのは、北方の酷寒地域が中心である。「緯度が高くなれば、アルコール度数も高くなる」という言い回しもある。ウォッカを飲むと、身体が内側から温まる。
一方、イスラム教徒が多く暮らす地域では、宗教的な戒律から飲酒率は低い。
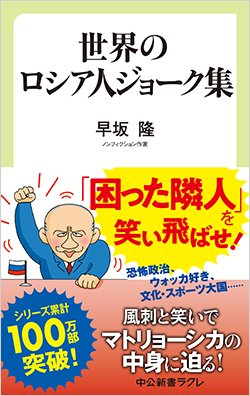 『世界のロシア人ジョーク集』(中央公論新社)
『世界のロシア人ジョーク集』(中央公論新社)早坂 隆 著
プーチン政権は過度の飲酒に対する総合的な政策を進めている。アルコール販売及び広告の規制、課税強化、飲酒運転の撲滅などである。
ロシア語に「トスカー」という言葉がある。これはロシア人独特の国民的資質を表すものとされ、「感情的な苦しみ」「特別な憂鬱」などと訳される。「ロシア人の哀しみ」「ロシア的憂愁」とでも言えるだろうか。これらの感情は緑色をしているとされ、「緑色のトスカー」という表現もある。
明治期の小説家で、『浮雲』で有名な二葉亭四迷(本名・長谷川辰之助)はロシア語に長じていたが、彼は「トスカー」を「ふさぎの虫」と訳した。
ロシア人が強い酒を求めるのは、「ふさぎの虫」のせいだろうか。それとも、ただのだらしなさか。







