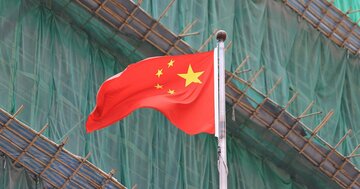日本大使公邸占拠事件の取材で見た
「フジモリ一家」の意外すぎる素顔
 大統領時代のフジモリ氏 Photo:AFP=時事
大統領時代のフジモリ氏 Photo:AFP=時事
9 月11日、ペルーのアルベルト・フジモリ元大統領(86)が死去しました。
1996年12月、在ペルー日本大使公邸占拠事件が起きたとき、私はペルーに取材に行き、フジモリ一家と行動を共にした経験があります。スペイン語どころか、英語もまともにできない私は、以前からフジモリ一家と親交のあった写真家の蓮尾真司氏に同行をお願いして、大統領のインタビューために慌ただしく飛行機に乗りました。
当時は『月刊文春』編集部に在籍。公邸では日系人中心に約600人が人質にされていましたが、フジモリ大統領は身代金と引き換えに人質を解放することには絶対反対でした。当時は、日本政府も必死に解決を求めていました。
ただ、私はこの事件やフジモリ氏個人のことより、せっかく海外で珍しい日系大統領が登場したという外交チャンスを生かせず、南米を中心とした世界的戦略を打ち立てられなかった日本の政治家たちのフジモリ氏に対する残念な扱いについて、振り返りたいと思います。
ペルーには飛行機で約20時間。蓮尾氏へのフジモリ家の信頼は厚く、なんとフジモリ大統領が所有する家の一軒に宿泊を許されました。金持ちの大統領だからといって、何軒も家があるわけではありません。いつテロに遭うかわからない国で、毎日同じ家に泊まるのは危険。そのため数軒の家を所有し、毎日宿泊する家を変えているとのことでした。
ペルーといえば、インカ帝国。マチュピチュ遺跡など観光地のイメージがありますが、首都リマはペルーの全人口約3000万人のうち1000万人が居住する、一大工業・商業地域です。雑然とした街並みで、当時は驚くべき治安の悪さと貧困ぶりを見ることになりました。
周囲はボロボロの車しか走っていません。「お金がないなら、中国やタイみたいに自転車にしたらどうなんですか?」と聞くと、大統領の側近が笑いながら答えました。「自転車なんて簡単に盗まれるでしょ」。
確かに、日系人の家を訪ねたところ、すべて三重の鉄トビラで守られていました。入り口で最初の扉を開けて、狭い小部屋に入り、誰何されて名前と写真が照合されると次の扉が開き、また狭い部屋に入ってもう一度確認されたあと、ようやく三つ目の扉が開き、家に入れます。鉄扉は頑丈で、一人で動かすのも苦労するくらいです。
中流階級以上の家は広い庭と農場が周囲にありますが、高い塀で囲まれ、中は簡単には見えません。塀の扉を気軽に開けようものなら、何匹ものドーベルマンがすごい表情で吠えながら、走ってきます。その家の当主の案内でしか、家には入れないのです。