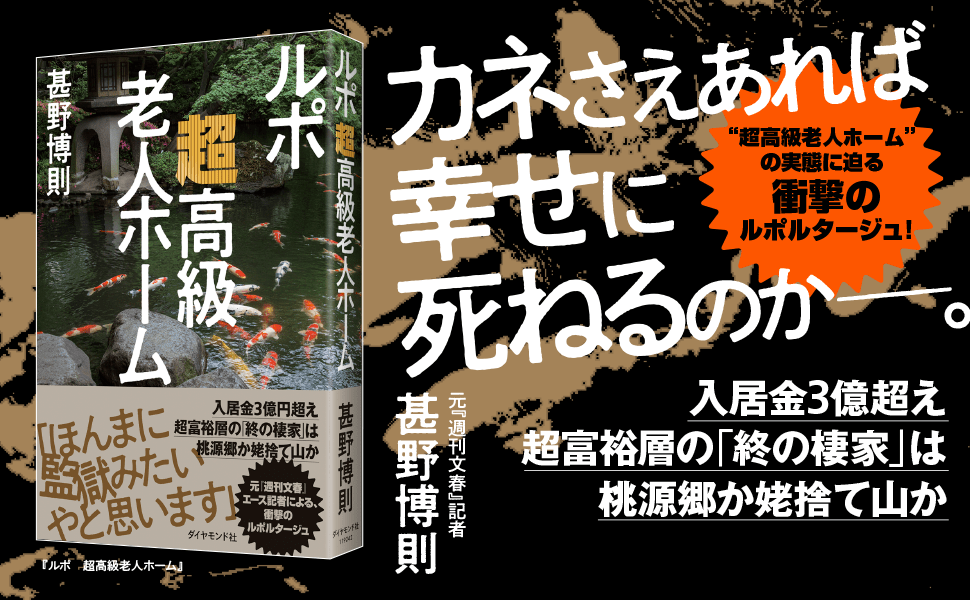極端すぎる「身体接触」
かつてのヤクザは自宅と事務所が分けられておらず、見習いたちは、親分の住居で暮らし「部屋住み」の若い衆となった。親分の身の回りの世話一切をするのだが、その程度が度を超しているのだ。
風呂で身体を洗うのは若い衆の役目だが、場合によっては背中を流すどころではない。全身をくまなく洗う。身体を拭くのも、洋服を着せるのも若い衆がする。過剰な身体介護や生活援助は、現代のヘルパー業務にかなり近い。
もちろん個人差はあり、べたべた接触されるのを嫌がる親分もいる。現代ではかなり減ったのだが、昭和の暴力団ではこれがスタンダードとされていた。
荒くれ者を調教し、従順な若い衆に再教育するためには、極端なコミュニケーションが有効だったのかもしれない。
文献を読むと、幕末から明治にかけての任客・清水次郎長や江戸時代後期の博徒であった国定忠治の時代にはなかったようで、権威主義が暴走し、いびつな生活補助がヤクザの慣習として定着したと推測される。
「ヤクザは言葉を信じない」
喫煙の習慣が一般的だった頃は、取材でもその片鱗がうかがえた。
親分が煙草を吸おうとすると若い衆が煙草を差し出す。親分が受け取ってくわえる。子分は素早くライターを差し出し、その煙草に火を点けるのだが、古い世代の暴力団はさらに過保護だ。
若い衆が自分でくわえ、息を吸いながら火を点け、その煙草を親分に渡すのである。
「飲み物の回し飲みと同じで、相手が口にした煙草を吸うのが親愛の情を表していた。口ではどうとでも言えるから、ヤクザは言葉を信じない。絆があって特別な仲だというなら、はっきり分かるよう形にするということ」(『仁義なき戦い』に登場した独立組織幹部。故人)
だから覚醒剤の流行時も、注射器でシャブを回し打ちして、みんなで肝炎になったんですか?……とは訊けなかった。
ただし、普段からこうした生活を送っていれば、いざ介護生活になっても、若い衆が対応すればいいだろう。実際、当番制で自宅に通い、親分の介護をしていた組員はいる。
1966年、北海道生まれ。日本大学芸術学部除籍。雑誌・広告カメラマンを経て、ヤクザ専門誌『実話時代』編集部に入社。『実話時代BULL』編集長を務めた後、フリーライターに転身。実話誌、週刊誌を中心に、幅広くアウトロー関連の記事を寄稿している。著書は『サカナとヤクザ』(小学館)、『潜入ルポ ヤクザの修羅場』(文春新書)、『ヤクザと原発』(文藝春秋)など多数。