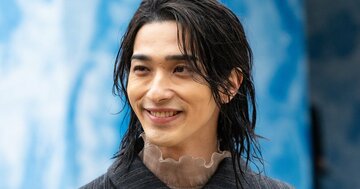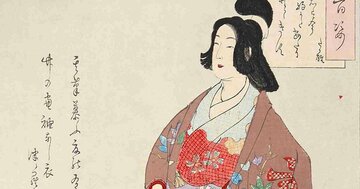質素倹約からバブリーに
蔦重が感じた江戸の変化
蔦屋重三郎は吉原という特殊な町で本屋稼業をスタートさせた。
本屋としてのみならず、彼の人生にとっても吉原は切っても切れない重要な存在となる。
そこに寛延から宝暦(1751~64)、明和(1764~72)、安永という時代のうねりが重なっていく。
重三郎が誕生した明くる年の寛延4(1751)年、八代将軍徳川吉宗が逝去する。
吉宗は延享2(1745)年、嫡男家重に将軍職を譲っていたものの、大御所として政治の実権を握っていた。吉宗こそは「享保の改革」の旗振り役、綱紀粛正を掲げ、タガの緩んだ幕政を締め直してみせた。彼は倹約を守り美麗を好まず、浮費を省くことを信条に掲げ、この指針を庶民にも強要してきた。
だが、吉宗逝去で時流は変わる。寛延はわずか3年余で宝暦に改元、質素倹約令は日を追ってなし崩しとなり、窮屈だった日々に別れを告げようという機運が急激に盛り上がった。
さらに宝暦11(1761)年、重三郎が数え12の時に家重は世を去り家治が将軍職に就く。
家重、家治の時代に凄まじい勢いで頭角を現したのが田沼意次だ。
紀州藩の足軽の子として生まれた田沼は家重の小姓から大名、家治の側用人という異例の出世を遂げ、安永元(1772)年に老中にまで駆け上る。
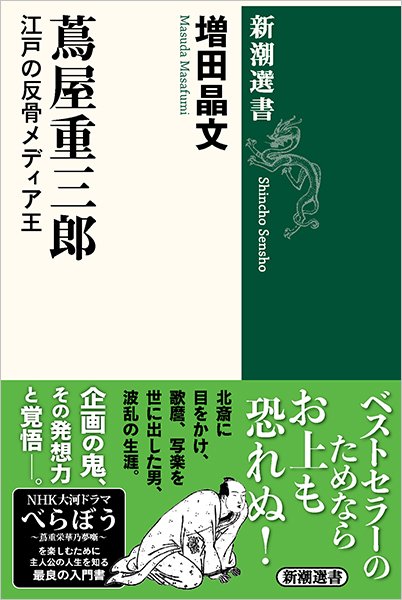 『蔦屋重三郎 江戸の反骨メディア王』(増田晶文、新潮選書)
『蔦屋重三郎 江戸の反骨メディア王』(増田晶文、新潮選書)
田沼は重商主義を推し進めた。その結果、商人は莫大な富を得て武士をも脅かすほど存在感を増す。世の中は奢侈になびき、江戸の街にもイケイケドンドン、バブリーな風が吹きつける。
吉原でも豪遊する富商が目立つようになってきた。吉原にとっての不遇の時代は終わり、悪所に不夜城の妖しい輝きが戻った。
少年から青年期にかけての重三郎はそんな世情を肌で感じ、つぶさにみつめながら成長する。