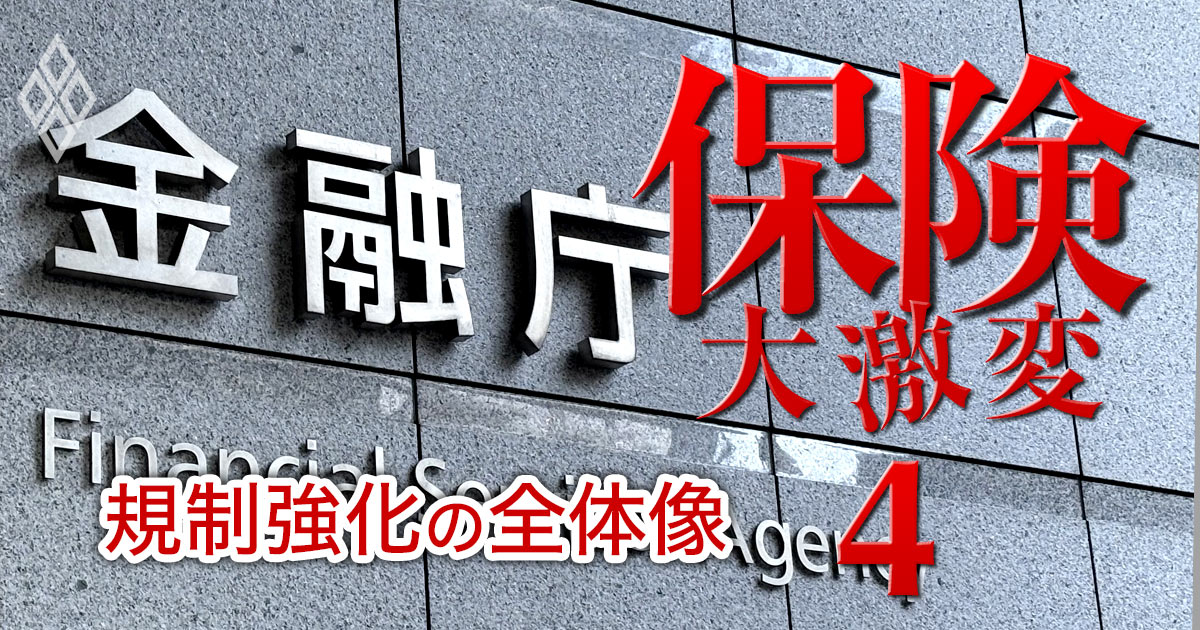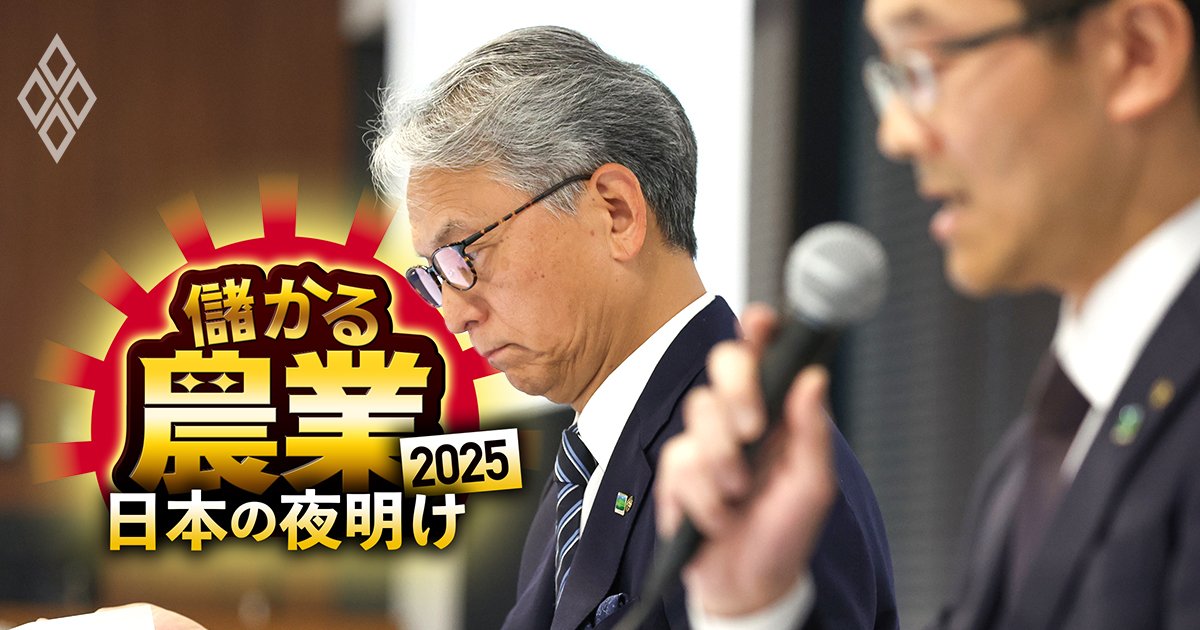これが「米価高騰」に大きな影響を与えていることは容易に想像できよう。
確かに、新米が出回った昨年9月、スーパーの棚にはコメは戻ってきた。しかし、それはあくまで「先食い」の結果であり、表面的な問題の解決にすぎない。民間在庫の「40万トン米不足」は絶賛継続中なので、米の取引に関わる人たちの多くは「去年の今頃に比べてだいぶ少ないな」という品薄感がある。
そうなれば当然、取引価格も上がることは言うまでもない。そこに加えて、商売人としてはまた昨年夏の米騒動のようなことが起きてもいいように、リスクヘッジとして「いつもより多く在庫を抱えておくか」となるのでさらに価格は釣り上がる。結果、我々の手元に届くときは、「5キロ4500円」なんて目を疑うような高値になってしまうのである。
国民の目を背けたい農水省
絶対に「コメ不足」と言わないワケ
こういう構造的な問題がある中で、「投機筋がお茶碗32億杯分のコメを買い占めているぞ!」と言われても正直ピンとこない。というか、「農水省にとって都合の悪い話から目を背けさせるために、卸業者に罪をなすりつけているんじゃないの?」と穿った見方さえしてしまうのだ。
なぜかというと、今回の米価高騰は「農水省にとって都合の悪い話」が大いに関係しているからだ。それは今回、「40万トンの米不足」を引き起こしてきた減反政策についてだ。
「おいおい、そんなもんは2018年にとっくに廃止になったよ」と失笑する人もいるかもしれない。しかし、農水省は減反政策廃止後も、主食用米の全国の生産量の「目安」を示しており、米から転作する農家に補助金まで出して、主食用米の生産量を絞っているのだ。
そして、この動きは近年加速していた。例えば、21年秋の主食米の収穫量は702万トンだった。需要はだいたい年間700万トンと言われているのでトントンだ。しかし、それが翌22年秋になると30万トンも落ち込んで、670万トンになる。「主食用米の作付面積が125万1000ヘクタールと21年産より5万2000ヘクタール減ったことが背景にある」(日本経済新聞 2022年12月16日)からだ。