鉄道を支えてきた軌道回路は
CBTCにとってかわるのか
西武鉄道の実証実験は、車上装置による速度・距離算出や列車検知機能、踏切機能など、システムを構成する基本的な機能について、1年弱の時間をかけて入念に確認したものだ。ただ、今回用いたシステムをそのまま実用化するのではなく、「走行試験での検証結果、鉄道各社の動向などを踏まえ、次世代信号システムの方式を決定」するとしている。
「鉄道各社の動向」とあるように近年、各社はCBTCの導入計画を相次いで発表している。その中でもいち早く技術開発に着手した東京メトロは、昨年12月7日に丸ノ内線でCBTCの使用を開始した。2026年度に日比谷線、2028年度に半蔵門線への導入を予定しており、これに関連して、半蔵門線と相互直通運転を行う東急田園都市線は2028年度、また、同線に乗り入れる大井町線も2031年度に導入を予定している。
CBTCは2030年代に向けて都市鉄道にとどまらず普及していきそうだ。西武鉄道傘下の伊豆箱根鉄道は昨年10月、地方鉄道向けのCBTCの開発を2024年度内に完了し、2031年度を目標に大雄山線へ導入すると発表した。
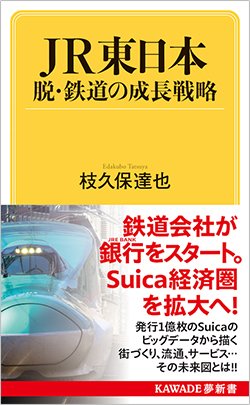 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
また、同12月には、北九州高速鉄道(北九州モノレール)がCBTCの技術的な安全性評価を終え、導入に向けて検討を進めると発表した。実現すればモノレールへの導入は国内初となる。
そしてもうひとつカギを握るプレーヤーがJR東日本だ。同社は無線式列車制御システム「ATACS」を2011年に仙石線、2017年に埼京線へ導入しているが、2031年までに山手線・京浜東北線、2036年までに首都圏全域への導入を目指している。
ATACSがCBTCに含まれるかは議論の前提によって結論が異なる難しい問題だが、軌道回路から無線通信への転換を「Communications-Based Train Control」と定義すれば、広義のCBTCと考えてよい。列車保安装置にとどまらず、踏切や連動装置(ポイントなどの制御)の制御、運行管理システムとの連携など、さまざまな機能を包括したシステムの総称がATACSであり、CBTCの一形態である。
ただ、各社が独自のCBTCシステムを開発することになっては、相互直通運転が盛んな首都圏では車両に複数の機器を搭載しなければならなくなり、コスト削減の効果が薄れてしまう。そこで国土交通省は2019年に「都市鉄道向け無線式列車制御システム(CBTC)仕様共通化検討会」を設置し、共通化の方向性を検討した。
2021年に発表されたとりまとめは、仕様の完全な共通化は普及や更新の自由度を下げるとして、さまざまなシステムの導入を前提に、異なる路線においても制御が可能となるよう、地上と車上で交換する情報の種類、形式を共通化し、直通を考慮した設計とすることを提言。現在、開発・導入が進むCBTCはこれを踏まえたものとなっている。
設備のスリム化、省力化、コスト削減が求められるのはJRから大手私鉄、地方鉄道まで一緒だ。140年にわたり鉄道を支えてきた軌道回路は、ついにCBTCにとってかわられるのか。2030年代に向けた技術開発、導入準備が加速しそうだ。







