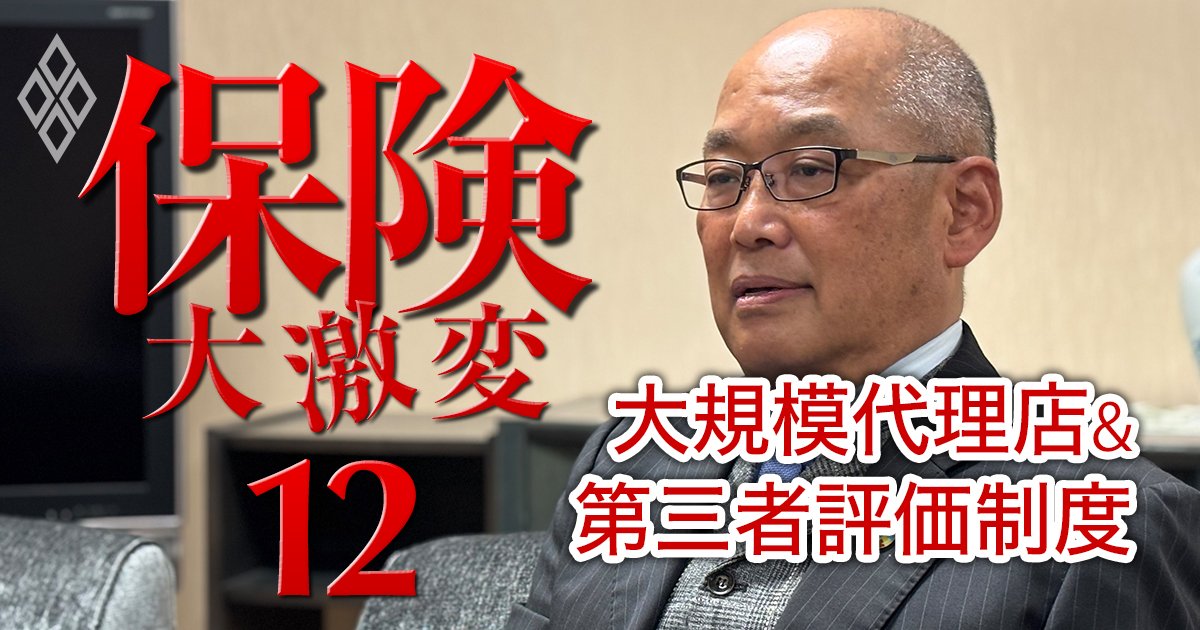トランプを手玉に取ろうとするプーチン
プーチン氏からすると、米国的な価値観で主義主張を押し付けてくる民主党の大統領よりも、交渉の余地があるトランプ氏の方が相手をしやすいことは間違いない。それに、トランプ氏は何を言い出すか分からない予測不能な人物だ。米国の外交の原則である、西側諸国の安全保障や民主主義を変える可能性もあるトランプ氏は、むしろ好都合なのだ。
東西冷戦時代から諜報活動の最前線にいた百戦錬磨のプーチン氏からすれば、「トランプの妄想に取り入って、手玉に取ってやろう」と思っているフシは大いにある。
強権的な指導者しかいない!ロシア史
両国のリーダー像には大きな違いがある。米国では子どもの頃から「リーダーシップが大事」と言われて育つ。片や、ロシアでは「リーダーシップを発揮しない方が安全」といわれている。米露のリーダーシップの違いを理解するには、歴史的な経緯を知ることが不可欠だ。
ロシアはロマノフ朝のロシア帝国の時代から、ソ連時代、ソ連崩壊後を含めて、西側的な民主主義を経験したことがない。ほぼ一貫して、強権的な指導者が国家統治してきた(一部で啓蒙君主といわれる皇帝はいたが、強権的であったことはおおむね当てはまる)。
加えて、ロシアは19世紀半ばまで奴隷に近い「農奴」が存在した国である。当時、各国に貧しい農民はいくらでもいた。が、農民の大多数が、牛や馬のように売り買いの対象になっていた国は多くない。米国でも移民が奴隷として運ばれた歴史はあるが、ロシアでは自国内の大半の農民が奴隷と同じように人身売買されていた点は、他の西欧諸国とは大きく違う。
国土が広く多くの国と隣接しているため、統治のためには強権が必要な面もあったのだろう。農奴が制度として廃止されても、「圧倒的に強い指導者」と「弱い庶民」という構図は残った(ただし、先祖が農奴でも国家指導者になったスターリン書記長など階層間の流動性はある)。
一方で、人権侵害が続くことに反発した民主的な動きが高まったことも、もちろんある。トルストイのような人道主義者や、ナワリヌイ氏のような反体制指導者が登場した。その意味では、社会の矛盾を深く思索する哲学的な人材や、身を危険にさらしても社会の変革に尽力しようとする人材は存在する。
しかし、社会全体の体制としては、強権的な政治がほぼ間断なく続き、弱い庶民は反抗のための牙を抜かれてしまっている。