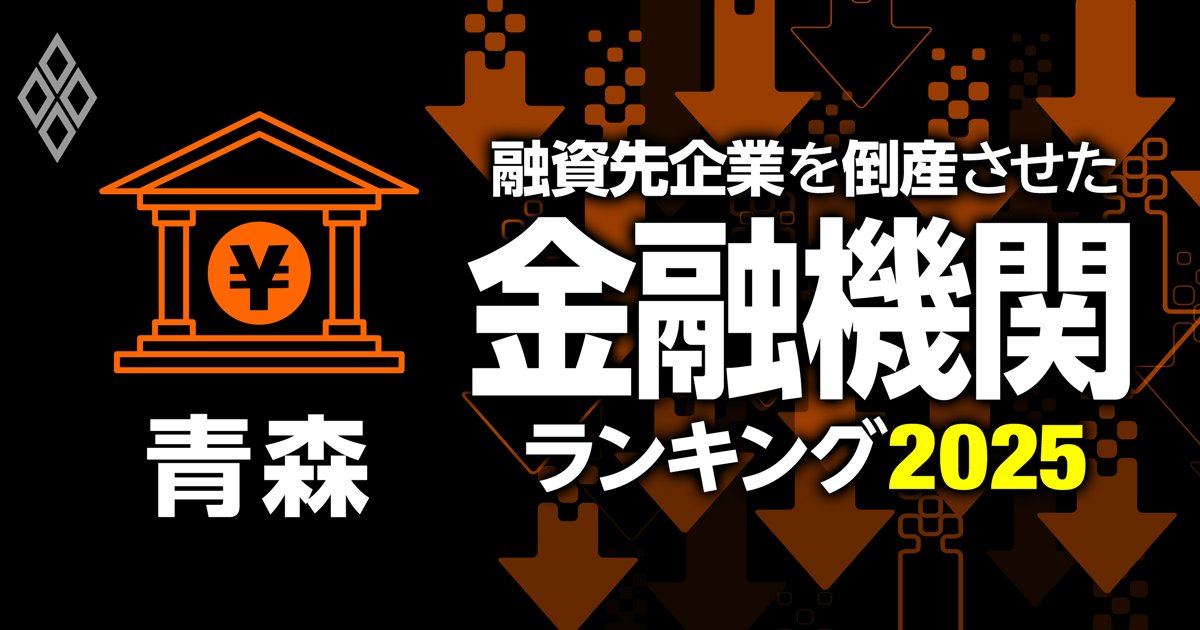この物語は明治期を舞台にしており、主人公・竈門炭治郎は「炭売り」を生業としている家庭の長男で下に5人の弟や妹がいる。
竈門家の父は病弱で、母や子どもたちみんなで看病をしていたが亡くなってしまう。そこで、炭治郎が一家の大黒柱として働いて家計を支え、幼い弟や妹も母を手伝って暮らしていた。
つまり、国民皆保険や年金・介護保険という制度がない時代、父親が病気になった竈門家が存続できたのは、「6人の子ども」が「労働力」と「社会保障」として機能していたからなのである。
だから、竈門家のような貧しい家ほど子どもをたくさん持った。貧しいということは栄養状態が悪く、子どもが飢えや病気で死んでしまうリスクが高い。1人や2人では心許ない。つまり、かつて日本人が5人も6人も子どもを持ったのは、子どもが可愛いわけでもなく、子育てに生き甲斐を感じていたわけでもなく、ごくごくシンプルに自分自身が生きていくための「労働力」と「社会保障」のためだったのだ。
少子化を加速させたのは
「高度経済成長」と「社会保障」
しかし、戦後になると日本人にとっての「子ども」というものの意味が徐々に変わっていく。
それがよくわかるデータがある。実は戦前の「貧乏子沢山」という傾向は戦後も少しだけ続いていて1947年には合計特殊出生率は4.54もあった。しかし、ここからフリーフォールのように急落してわずか10年で2.04(1957年)まで一気に落ち込む(内閣府「選択する未来 -人口推計から見えてくる未来像-」)。
この水準が1975年あたりまで続くことを踏まえれば、1947年から1957年の出生率の落ち込みは「異常」だ。この10年の間で、日本人に「子どもを持ちたくない」と思わせる強烈な出来事があったと考えるべきだろう。
そこでよく言われるのが「高度経済成長」だ。戦後の焼け野原から復興を果たして、日本人がどんどん豊かになっていったので、「子どもを持ちたくない」と思う若者が増えたというのだ。