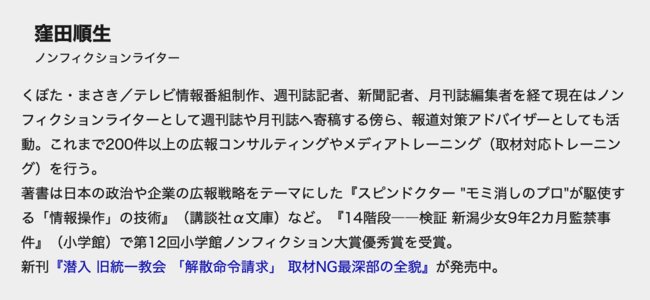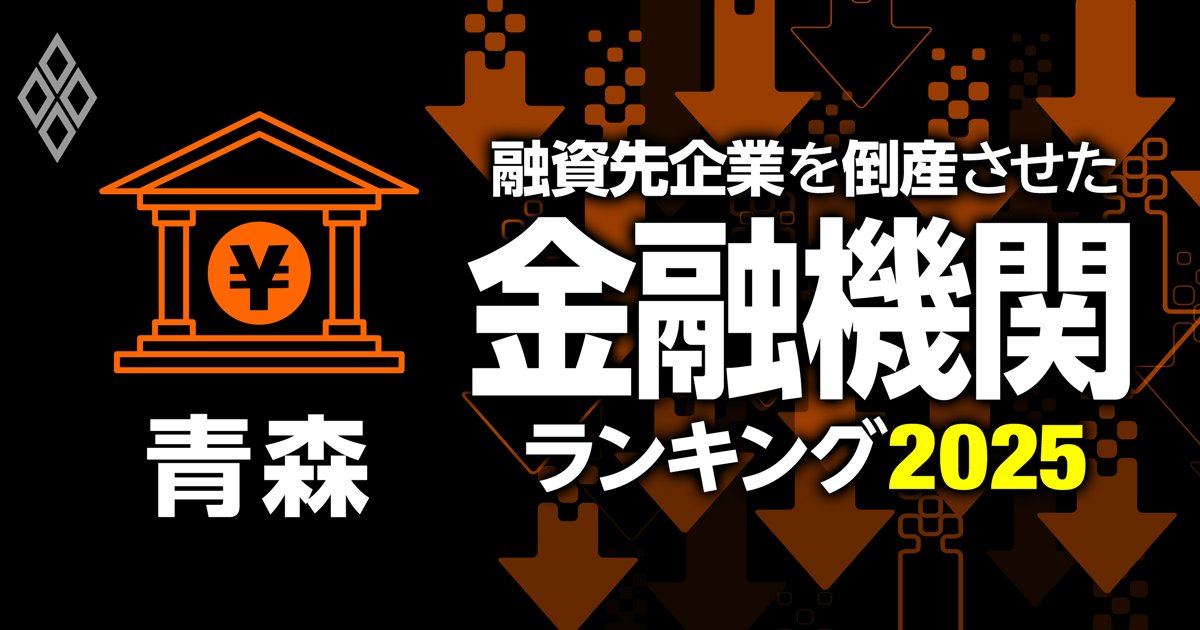1959年になると国民年金法が成立して、1961年には国民皆保険もスタートしていく。戦前まで日本の子どもたちに求められていた「親が病に伏せたら代わりに働いて治療費を稼ぐ」「寝たきりになった親を食べさせて、身の回りの世話をする」という役割を国が担ってくれるようになるのだ。これによって、「生存戦略としての子ども」というものの存在意義は完全に消失した。
こうなってくると、もはや子どもを持とうというのは、「子どもが好き」「子どもが生き甲斐」という精神的充足感を得たい「経済的に余裕のある人」だけになってくることは言うまでもない。
かつて子どもたちがやっていた「社会保障」は確かに国が肩代わりにすることになったが、そのために国民は社会保険料を負担することになったからだ。
もちろん、成田氏のように経済力のある人はこんなものは屁でもない。しかし「格差」が広がってくると、社会保険料を払ったらカツカツで、とてもじゃないが、子どもを持って養育費や教育費などを捻出し続けることはできないという人も雪だるま式に増えていく今がまさしくそうだ。
こういう日本の現実を冷静に直視している若者が、「子どもを育てたくない」と感じるのは当たり前である。
例えば、日本の社会保障費は約138兆円。2040年には190兆円となる予測だ。
一般会計が110兆円を超えたとか、やれ緊縮財政だなんだと騒いでいるが、もはや我々の医療・年金はそういうレベルを超えているほど「膨張」をしている。この厳しい現実を見れば、これからの若者たちはこれまで以上に「重い負担」を背負わされることはわかりきっている。「自分のことしか考えていない」のではなく、「子育て最高!」「子どもを持つのは究極の暇つぶし」なんてことを言って人生を謳歌する「余裕」がないのだ。
これまでの日本社会は「子どもをつくらないのはバカだ」「子どもを持つ幸せを知らないのか」という精神論と社会の同調圧力によって、なんとか一部の若者たちに「子どもを持つ」という選択をさせてきたが、もはやそれは限界だ。
若者が子ども持たないのは「バカ」だからではなく、こういう異常事態になるまで社会保障などの問題から目を背けて、問題先送りを続けてきた大人たちの方が「バカ」だからだ。
まずはその厳しい現実を直視しないことには、いつまでたっても若者たちはこの国に希望が持てないのではないか。
(ノンフィクションライター 窪田順生)