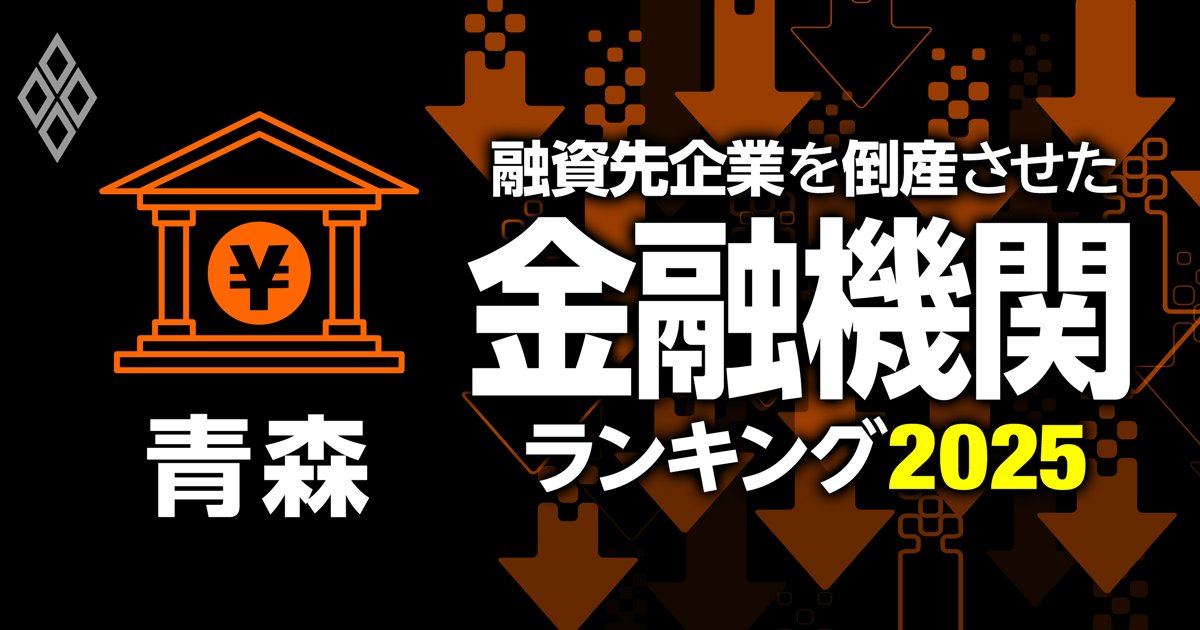ただ、これは令和日本の議論とまったく矛盾をする。今の日本の若者は「貧しい」から子どもを持ちたくないということを、さまざまな専門家が主張している。そのため、政府も若者に対して結婚や出産を促す経済的な支援をしている。
この理屈でいえば、高度経済成長がスタートして、「明日は今日よりもっといい日になる」と未来に希望を抱くことができた当時の若者はどんどん子どもを持とうとするはずだ。しかし、現実はその真逆で「子ども持ちたくない」という若者がドカンと増えた。
実はこの不可解な現象は先ほど述べた「戦前まで子どもは労働力だった」という事実を受け入れると、すんなりと説明できる。
実は1947年に労働基準法ができた。この法律では「児童労働」を全面的に禁止している。つまり、戦前までの貧しい家庭の生存戦略の柱だった「子どもにも大人のように働いてもらう」ということができなくなってしまったのである。
そうなれば、「子どもを生みたくない・育てたくない」という若者が増えて合計特殊出生率が低下していくというのは容易に想像できよう。
貧しい家庭にとって、労働者ではない子どもは単なる「食いぶち」だ。5人も6人もいればただでさえ苦しい家計はさらに困窮する。誤解を恐れずに言えば、「児童労働」を禁止したことによって、子どもは経済的に余裕のある家庭の「贅沢品」となったのである。
この「出生率の低下」に追い打ちをかけたのが、戦後から日本政府が推進してきた「避妊推奨キャンペーン」だ。
戦時中まで日本では避妊が禁止されていた。「学徒出陣」を見ても分かるように、子どもは「兵力」だったので、「産めよ増やせよ」が国策だったのだ。しかし、それが戦後に180度方針転換された。
「国が一転して避妊を推進。助産師などが避妊方法を指導して回り、避妊具を配ったのです。背景にあったのは人工妊娠中絶の急増です。1953年には、年間100万件を超えるまでに。数ある避妊具の中でも、手軽で効果を実感しやすいコンドームが人気を集めました」(NHK はなしちゃお! 〜性と生の学問〜 24年2月8日)
このように「児童労働の禁止」に「コンドームの普及」というダブルパンチで1950年代は合計特殊出生率が急落していった。つまり、令和の日本を疲弊させている「少子化」というのは、実は敗戦直後からスタートしている構造的な問題なのだ。
そしてこの「人口減少トレンド」にトドメを刺したのが、「社会保障」だ。