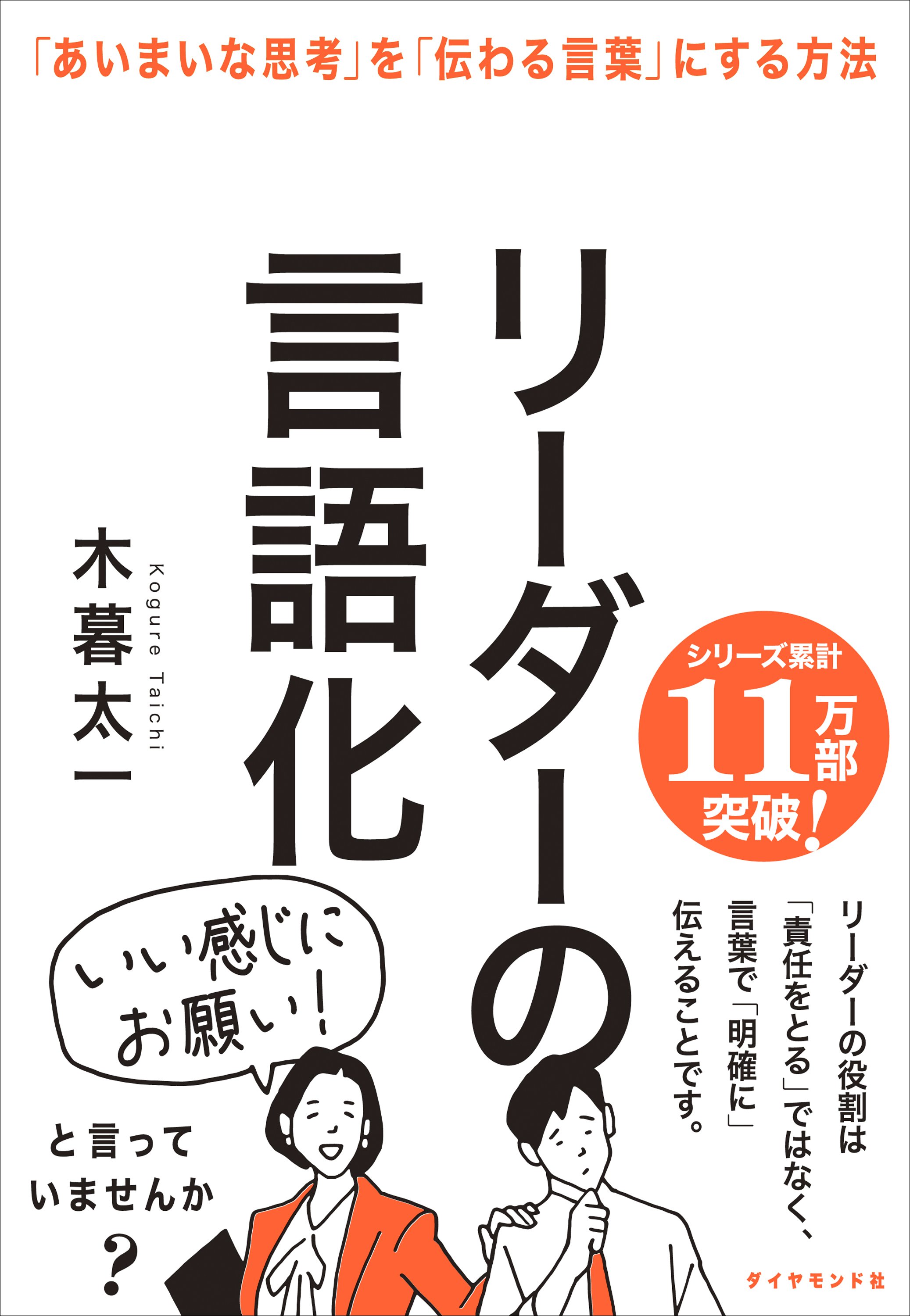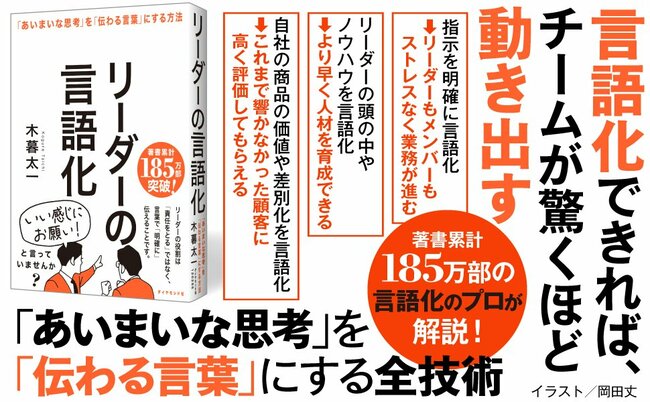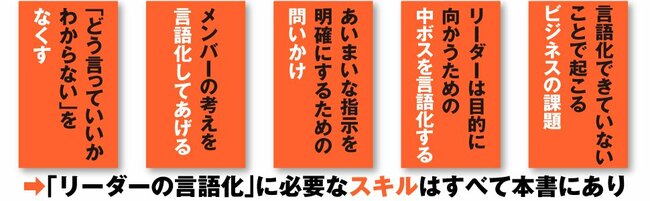「よかれと思って」を認めるフィードバック法
より効果的なフィードバックのためには、まず部下の「よかれと思って」を言葉にし、認めることから始めるべきです。
その上で、その「よかれ」の前提を修正するアプローチが有効です。たとえばこういう流れです。
1. 「よかれと思って」を言葉にする
「この報告書、データを詳しく載せようとしてくれたんだね。読者に正確な情報を伝えようとした意図がよく伝わってきます」
相手の良い意図を推測し、言葉にして認めます。この段階では、「相手が何を意図していたか」を正確に当てる必要はありません。重要なのは、「よかれと思ってやった」という前提で接することです。
2. その「よかれ」の前提を修正する
「ただ、この報告書の目的は◯◯なので、詳細データよりも△△の方が重要になります。なので、△△を中心に据えてみてほしい」
相手の意図を認めた上で、別の視点や優先順位を提示します。これにより、単なる「ダメ出し」ではなく、「視点の修正」というより建設的なフィードバックになります。
改善前:
「このプレゼン資料は情報が多すぎて分かりにくいです。もっと簡潔にまとめてください」
改善後:
「このプレゼン資料、全ての情報を伝えようと丁寧に作ってくれたんだね。とても熱心に準備してくれたことが伝わってきます。ただ、クライアントの時間は限られているので、今回は彼らにとって最も重要な3点に絞った方が効果的だと思うんだよ。どの情報が最も彼らの関心を引くだろう? 君はどう思う?」
なぜこのアプローチが効果的か
この「よかれと思って」を認めるフィードバック法には、いくつかの大きなメリットがあります:
1. 心理的安全性を保てる
「自分の努力や意図が認められた」という感覚は、フィードバックを受け入れやすくする土壌を作ります。否定されたと感じれば防衛本能が働きますが、意図が認められれば、改善点にも耳を傾けられるようになります。
2. 学習効果が高まる
単に「何が間違っていたか」だけでなく、「なぜそれが期待と合わなかったのか」という理解を深めることができます。これにより、同じ間違いを別の形で繰り返す可能性が減ります。
3. 関係性が強化される
「あなたの意図を理解しようとしている」というメッセージは、信頼関係の構築に繋がります。リーダーが自分を理解しようとしてくれていると感じれば、部下も同様にリーダーの意図を理解しようと努力するでしょう。
ハラスメントを減らし、効果的な指導を行うためには、単に「行動だけを冷静に指摘する」だけでは不十分です。相手が「よかれと思ってやったこと」を言葉にし、その「よかれ」の前提を修正するアプローチが必要です。
この方法なら、相手のプライドや自尊心を傷つけることなく、建設的な変化を促すことができます。さらに、「あなたの意図を理解している」というメッセージは、信頼関係の構築にも繋がります。
真のコミュニケーションは、相手の行動だけでなく、その背後にある意図や思いにも目を向けることから始まります。部下への指導で悩んでいるリーダーの方は、ぜひこのアプローチを試してみてください。