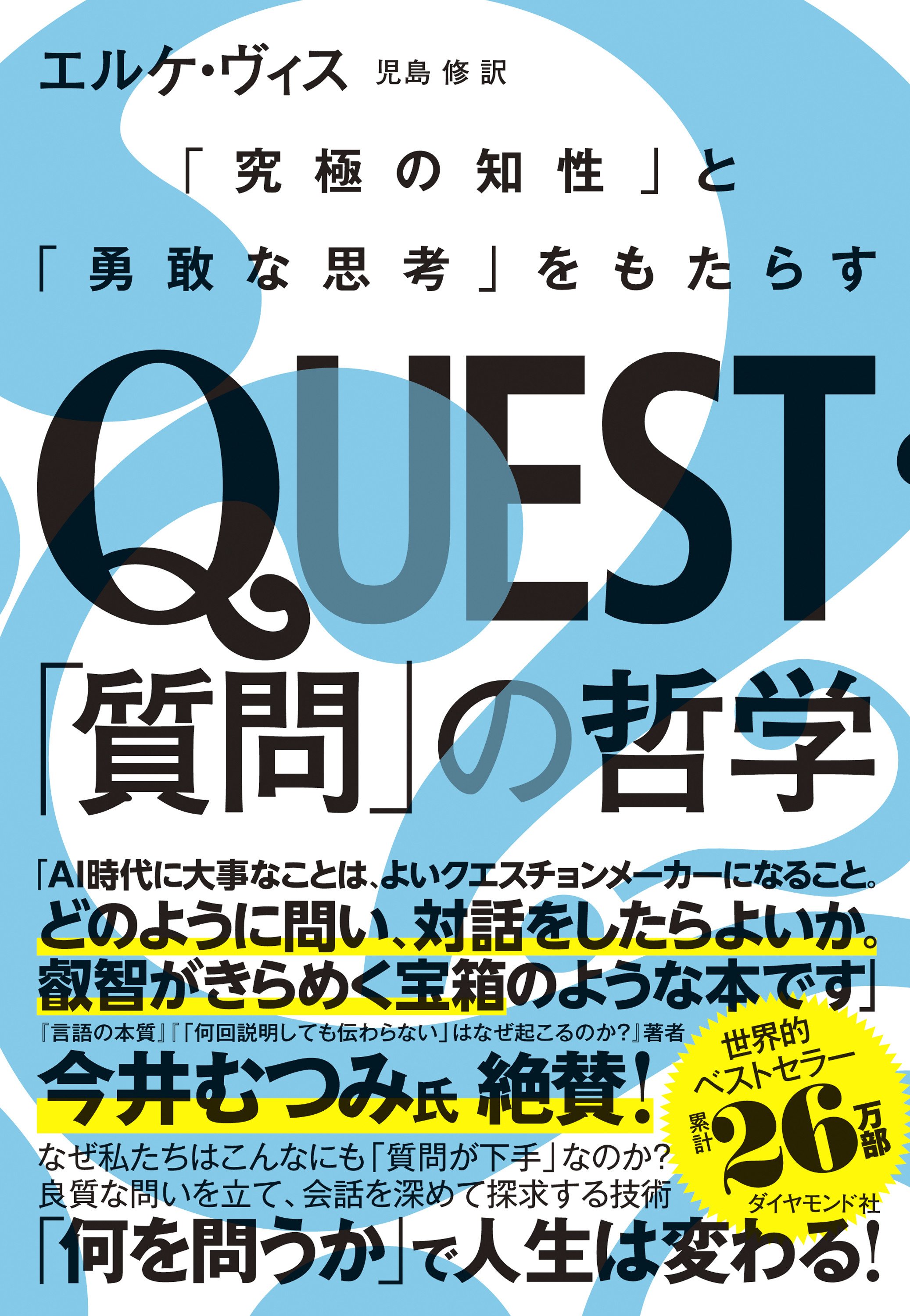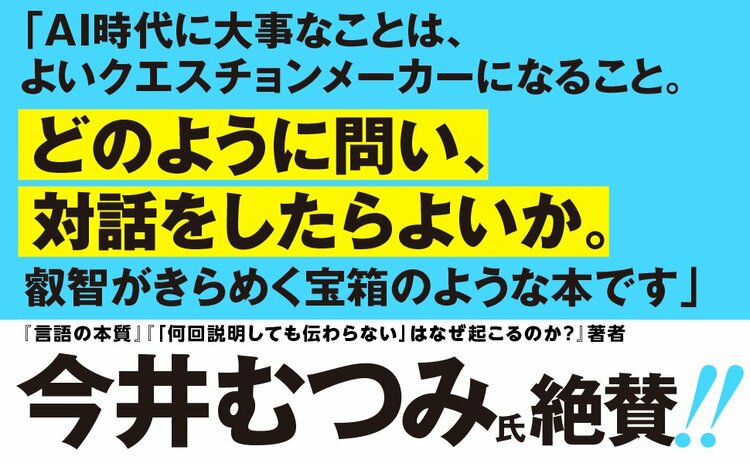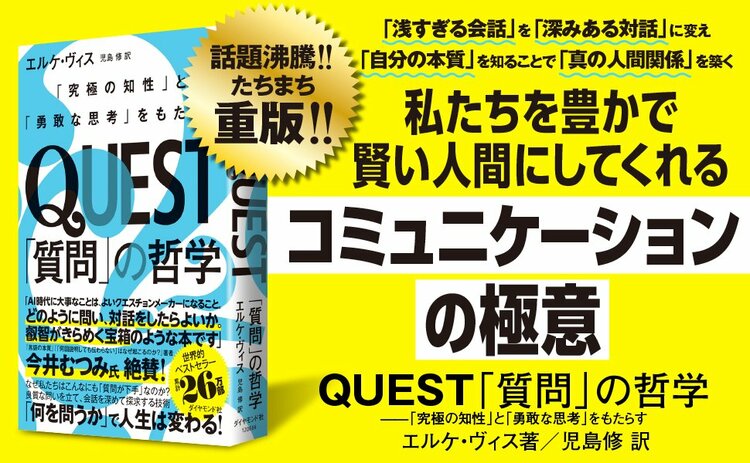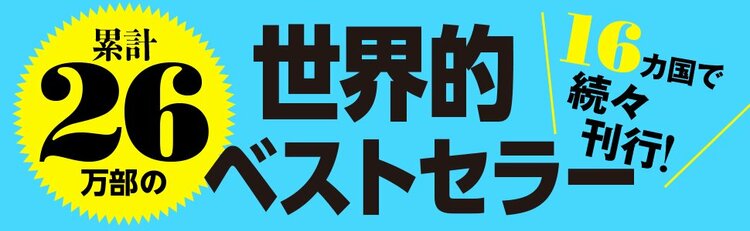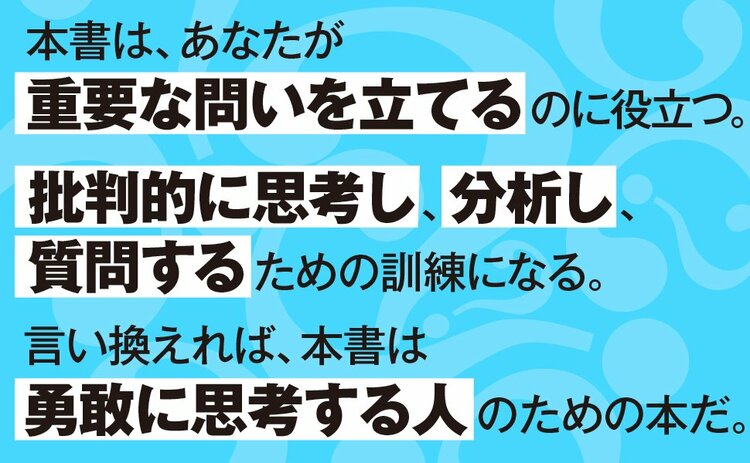「いつも浅い話ばかりで、深い会話ができない」「踏み込んだ質問は避けて、当たり障りのない話ばかりしてしまう」上司や部下・同僚、取引先・お客さん、家族・友人との人間関係がうまくいかず「このままでいいのか」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
世界16カ国で続々刊行され、累計26万部を超えるベストセラーとなった『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』から「人生が変わるコミュニケーションの技術と考え方」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
子どもの質問に真摯に向き合う
私は昔、質問魔だった。いつも「どうして?」と尋ねては、親を困らせていた。
「ママ、どうして空に大きな風船があるの?」
「人は気球が好きなのよ。高いところから世界が見られるから」
「どうして人は高いところから世界を見たがるの?」
「たぶん、景色がきれいなんでしょうね」
「私たちも同じことができる? 大きな風船で空に上がれる?」
「できるけど、私たちには無理よ」
「できるのに、どうしてやらないの?」
「ええと……つまり……できないって言ったらできないの!」
私はありきたりの答えでは満足しなかった。ある質問をしたら、すぐに次の質問をする準備ができていた。与えられた答えの前後左右にも答えが欲しかった。
私に質問攻めにされると、両親はいつも「とにかくそういうことなの!」という言いわけに頼っていた。
それは子どもをあしらい、際限のない質問をかわすための便利な常套句だった。
「質問するのは必ずしも相手に喜ばれるわけではない」ということを、子どもたちにさりげなく伝えるメッセージにもなっていた。
もちろん、親の気持ちは理解できる。
子どもの探求心を大切にし、育てようとすれば、相当の時間と忍耐が必要になる。
だがそれでも、そうするだけの価値はある。
子どもたちの質問に真摯に答え、子どもたち自身にも考えさせ、想像力をかき立てるような質問をすることに、親は時間をかけるべきだ。
柔軟に考え、探求心をもち、テーマや主題をあらゆる角度から検証し、答えを導き出す─。
どれも子どもが自然に身につけていく能力だ。
しかし現代の教育システムに放り込まれると、有望な若い芽はすぐに枯れてしまう。
小学校から中学、高校、大学、社会人へと進む中で、深い質問をしたり、哲学的で探求的な態度を取ったりすることは重視されていない。
私は、深い質問をし、哲学的に考えることを教育方針の基本にしている小学校があることを知らない。しかし、これらは間違いなく重要なライフスキルである。
批判的に考え、自分や他人の意見に疑問をもち、多角的な視点を取り入れることができれば、相手と良いつながりをもつための方法を知る、心の機微がわかる大人になれる。
そして現代社会では、何よりもこうした人々がかつてないほど求められている。
(本記事は『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』の一部を抜粋・編集したものです)