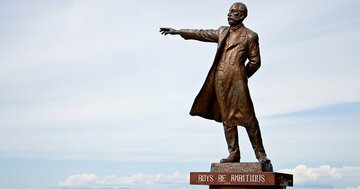人間は他者に好悪の感情を抱いたり、予断と先入観を持ったりする生き物です。私の教員人生を振り返ってみても、「何が」話されているのかではなく、「誰が」話しているかによって、真偽の判断をしたり、賛成・反対の意見を表明したりする光景を幾度となく見てきました。同様な主張であったとしても、A氏なら認めるも、B氏ならば認めない。気に入らなければ、発言をさえぎって一方的に反論したり、徹底的に非難したりする。それはある意味、醜い姿。
もちろん日常の言動や仕事への取り組み方などから、人物評価が作り上げられていくことは、否定できません。自己中心的な行動や独断専行は嫌われる。小手先の処世術や手抜き三昧は直ちに見抜かれる。天網恢恢(かいかい)疎にして漏らさず。自業自得であり、一度立った悪評を覆すのは至難の業。信用されない輩の言説は受け入れられないのもやむなし。
ですが、どのような人物であったとしても、とりあえず話を聞くことは寛容の精神かと。私心や打算から発したものか否か、根拠や理由には正当性があるか否か、意図や真意はどこにあるのか等々を確かめるためにも、注意深く話に耳を傾ける。時間が惜しいかもしれませんが、可否判断はそれからでも良いのではないでしょうか。虚心坦懐(たんかい)に聞く意識は、自己の心情との葛藤です。
「人間は見た目が9割」は真実か?
ヘッドハンターが語る印象評価
大学教員時代、キャリア教育や就職支援のあり方について、ある企業経営者を通して紹介してもらったヘッドハンターに、貴重な助言を多々いただきました。中でも心に深く残ったことが2点あります。
まず、「候補者」と初めて接触した際の第一印象が評価に大きく影響するという点です。
「人は見た目が9割」「ビジネスの80%はファーストインプレッション(第一印象)」などの言葉は、これまで幾度も耳にしてきました。コミュニケーションにおいて重要な要素は、見た目などの視覚情報55%、声の調子や話す速さなどの聴覚情報38%、話の内容などの言語情報7%であるとした、米国の心理学者が唱えた「メラビアンの法則」も知られているところです。