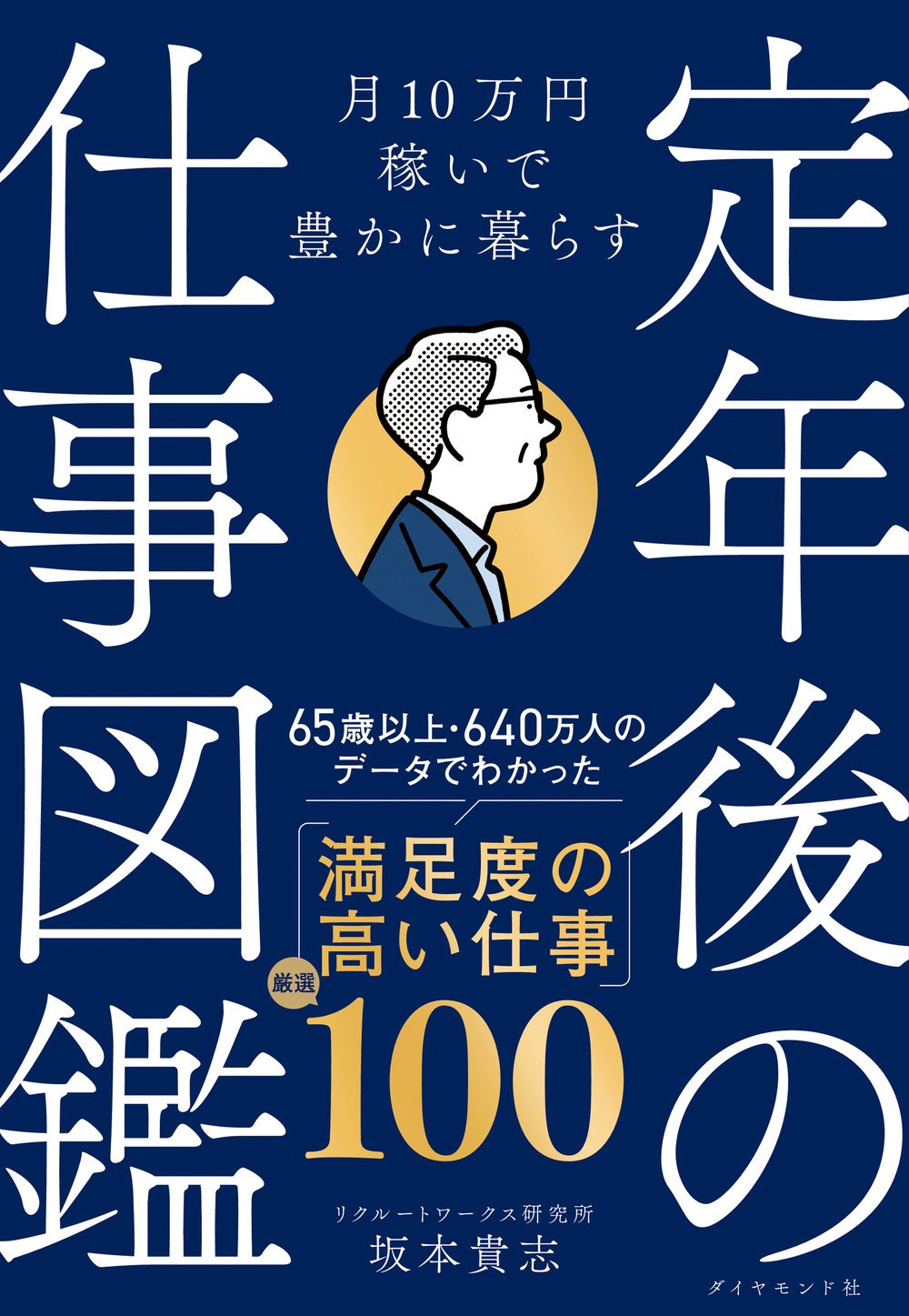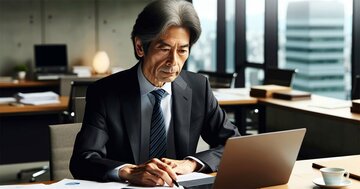「60歳以降の仕事人生にも、ガイドが必要だ」――そう語るのは、リクルートワークス研究所の坂本貴志さん。高齢期の就労・賃金を専門とする坂本さんが、65歳以上・640万人のデータを分析し、まとめた書籍が『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』です。
定年退職=引退だった時代は終わり、いまや「定年後の仕事探し」を自分自身で行う時代がやってきました。本書では、実際に働いている人のデータを参照しながら、19カテゴリ、100種類の仕事を紹介。現役時代とは全く違う仕事選びのコツについても解説しています。
※この連載では、本書より一部を抜粋・編集して掲載します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
本書で紹介する職種の選定にあたっては、まず総務省「国勢調査」をもとに各職種の就業人数とその中における65歳以上の就業者が占める割合を算出し、高齢期の就業者が一定の数と割合で働いている職種を割り出すことで、「就業しやすい職種」19のカテゴリを特定した。
その後、特定した職業の中で医師や弁護士、エンジニアなど特殊な資格や長期の就業経験を要するものを除いたうえで、シニアからでも始めやすくかつ無理なく働ける職業(つまり満足度の高い仕事)を選び、掲載を行っている。
さらに本書では、各職業について、総務省統計局から総務省「就業構造基本調査」のオーダーメード集計を入手したうえで、各職種の年齢別の就業人口、高齢者比率、女性比率、65歳以上の就業者の週労働時間、年収、就業・雇用形態を算出している。
定年後の仕事、勤務時間が最も長いのは「農業」
1位は「農業」。農業は、「65歳以上の就業者が多いランキング」で1位となっており、今回調査したデータによると、100万人以上が従事している。具体的には次のような仕事がある。
[農業従事者]
野菜、果樹、穀物、その他の作物を育てて収穫・選別・出荷をする。農家は家族経営が中心で、親や親戚から経営資源を継承することが多い。兼業農家として働くケースや、農業以外の職業に従事したのち親の高齢化などに伴って入職するケースもある。
就業には独立就農する方法と農業法人に就職する方法があるが、大半が自営業で、体力が続けば高齢期まで働くことができる。家族から田畑を継承せず未経験で就農を目指す場合は、都道府県ごとに設置される新規就農相談センターや、「新・農業人フェア」などで就農に関する相談をすることができる。
一定の要件を満たす新規就農者に対しては市町村が支援措置を講じる制度もある。パート・アルバイトとして短時間で働きたい場合は、規模の大きな農園で収穫など一部の作業をサポートする仕事もある。
[植木職人・造園師]
公園や企業、個人宅などで庭や植え込みを美しくととのえ、樹木を健全に育てるために植木の剪定・伐採、草刈り、芝刈り、庭園の造成などを行う。
造園や土木に関する経験・資格があると就職にあたって有利に働くが、補助的な仕事の需要もあり、必ずしも高度な専門性を要するわけではない。シルバー人材センターを通じて紹介される仕事としても比較的多く見られ、植木の剪定の仕方などの技能講習を開催する自治体もある。
[酪農・その他養畜従事者]
家畜の世話や飼育小屋の清掃、繁殖・育成・搾乳、飼料の栽培などを行う。農業と同じく家族や親族から経営資源を継承することが多く、新規就農の場合も継承者のいない農畜従事者から継承する。
雇用されて働く場合は、農業法人や酪農ヘルパー利用組合に所属する。短時間で働きたい場合、牧場で餌やりや搾乳など一部の世話を補助する仕事がある。このほか、動物園で動物を飼育する仕事や昆虫を飼育する仕事もある。※酪農家が休みを取る際に代わって必要な作業を行う。