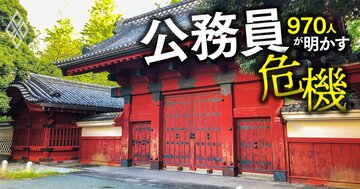自治体のマンパワーは限界
地方行政体制は大きく変化する必要がある
私は、現在の地方行政体制が将来も今と同じ形で可能かどうか考え始める時期にあることを国会で問題提起しました。このままいけば、今世紀末には、日本の人口が半分になってもおかしくはない。特に地方では、生産年齢人口が減少します。となると、1700ある市町村から成る現行のシステムは成り立たなくなります。
(生産年齢人口が、2020年から40年までの20年間で約1300万人減り、6200万人ほどになると予測されている)「2040年問題」もある。数十年先の話だったとしても、今からどのような仕組みに移行していくかを議論しなければいけません。
例えば、将来の一つの仮定ですが、私の地元の愛媛県だと、松山市など大きな市と県と国がどうあるべきなのか、という問題意識です。
そこで、デジタル化が鍵になります。仕事が省略でき、広域で行政サービスを展開しやすくなるからです。ただ、デジタル化を進めるには(ITに強い)人が必要です。有能な人をどう確保するか考えなければいけません。
――土木などの技術職の公務員はすでに人が足りていません。
デジタル化などで人手不足を補いつつ、技術系の職員はある程度、(複数の自治体などで)共通で働いてもらう必要があります。
――改革に向けて、どのような手を打っていますか。
総務省の「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会」に、今回は(人口減少時代の地方自治体の在り方について)深掘りしてほしいと頼みました。今までのようなありきたりの議論をしている余裕はないのです。
 2025年4月1日の総務省入省式で、新人職員らに訓示する村上誠一郎総務相 写真提供=総務省
2025年4月1日の総務省入省式で、新人職員らに訓示する村上誠一郎総務相 写真提供=総務省
――一方で、知事、県議会議員、市議会議員など、既得権を失う人がいるので、都道府県庁不要論には抵抗もあります。
現実的に、ある地方の村は、役場が28人定員なのに対して、14人しか職員がいない。一部の地域では、すでに問題が顕在化しつつある状況になっているのです。
人員不足や将来の体制の在り方について、国、県、市町村が、協力して問題に取り組むことが必要となるでしょう。
――国、県、市町村が枠を超えて協力するのはいいアイデアですが、県知事からは「まずは国から改めるべきだ」という声も出ています。
私が言ってるのは今日明日のことではありません。何十年か先の話であって、次の世代のことについて責任が持てるよう、長期的な視点で一緒に考えてもらいたいのです。
――地方に身を切る改革を求めるだけでなく、国会議員の数も減らすべきだとお考えでしょうか。
極端に言えば、(選挙区だけ残して)比例代表はなくしていいという議論を展開する人たちもいます。いずれにしても、国も地方も、今のパターンがいつまでも続くということはあり得ないのではないかということです。
Key Visual:SHIKI DESIGN OFFICE, Kanako Onda