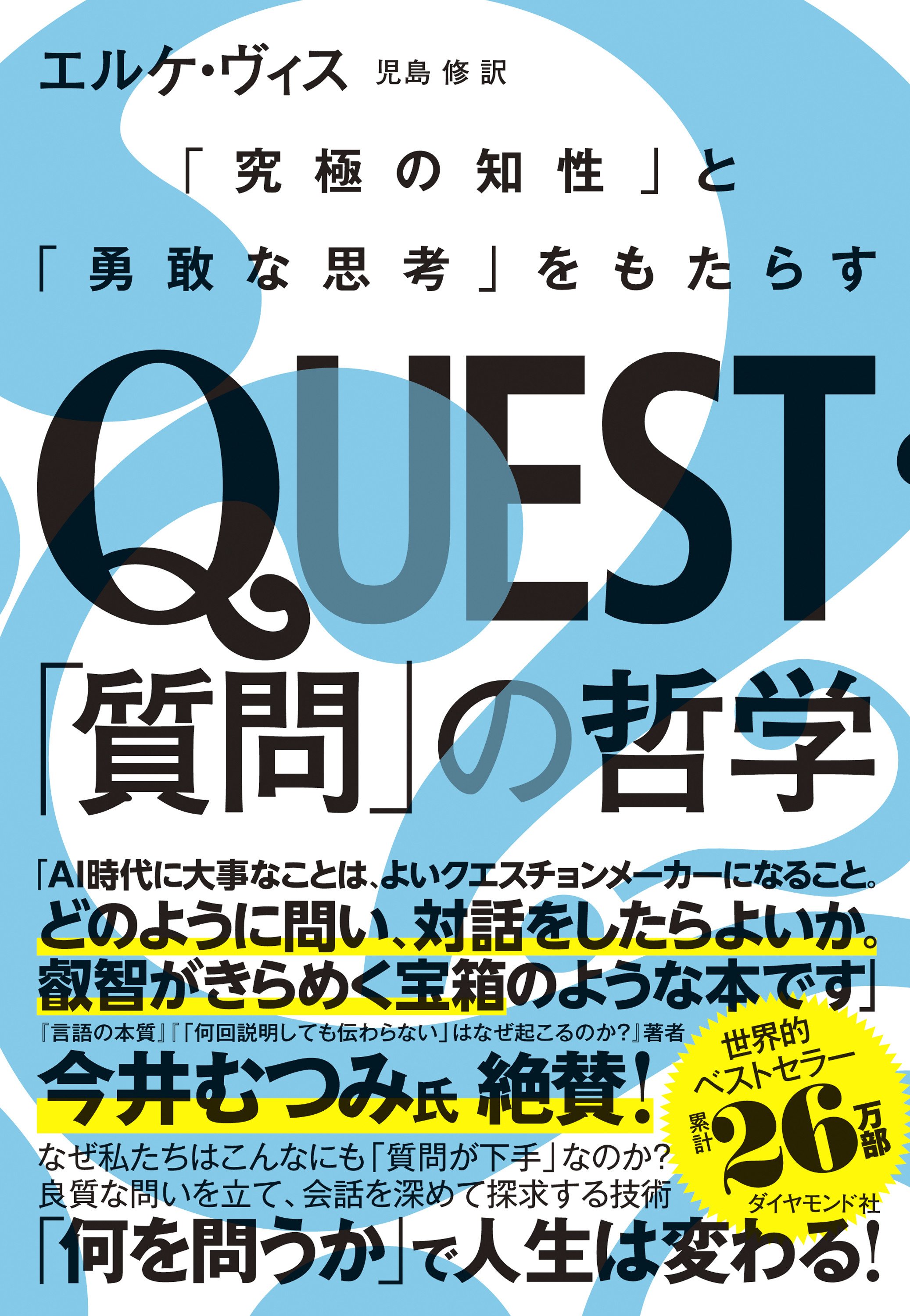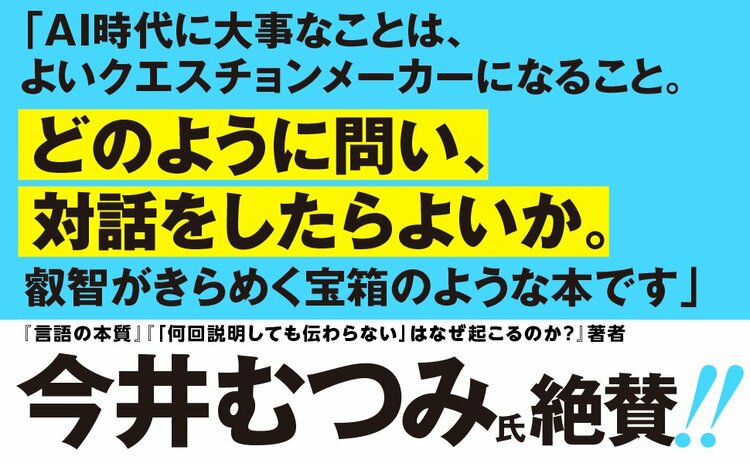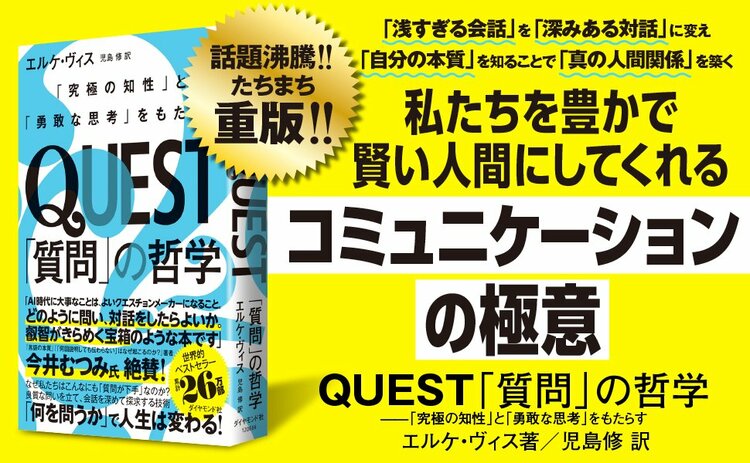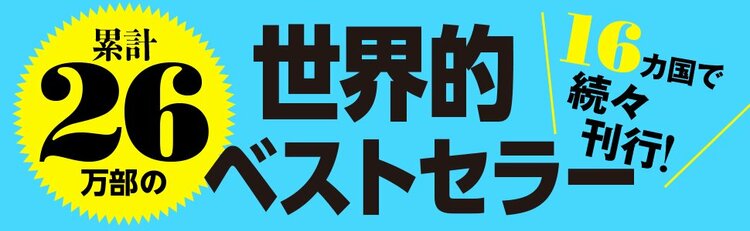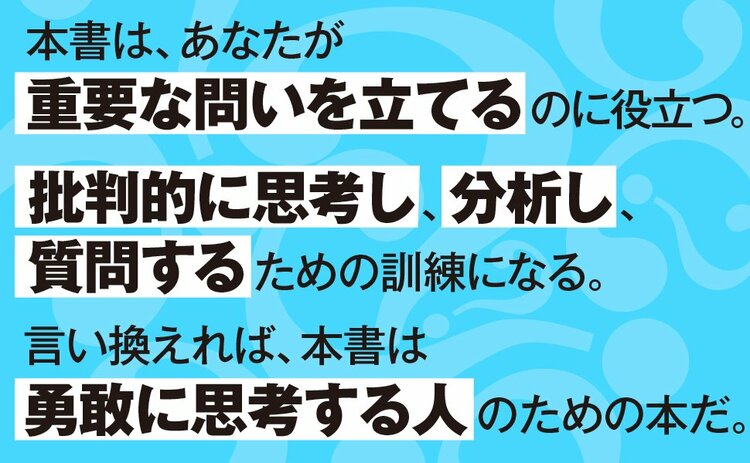「いつも浅い話ばかりで、深い会話ができない」「踏み込んだ質問は避けて、当たり障りのない話ばかりしてしまう」上司や部下・同僚、取引先・お客さん、家族・友人との人間関係がうまくいかず「このままでいいのか」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
世界16カ国で続々刊行され、累計26万部を超えるベストセラーとなった『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』から「人生が変わるコミュニケーションの技術と考え方」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
私たちは理性ではなく直感で意見している
私たちは、「誰もが自分自身にとっての真実を主張する権利がある」と考えている。
「それがあなたの意見なら、あなたにはそれを主張する権利がある」「あなたにはあなたの真実があり、私には私の真実がある」というふうに。
「誰もが自分自身の真実をもっていて、周りはそれを真剣に受け止めなければならない」というのは、現代社会の大きな価値観になっている。
オランダの全国紙トロウのインタビューで、哲学者のダーン・ルーバースは次のように述べている。
多くの人が、自分の発言や先入観は特別に保護されるべきだと考えているが、それは大きな誤解だ。
表現の自由は、政府との関係において市民に与えられる政治的権利である。
親子の関係や、市民同士の関係とは違う。この自由には、自分の意見に疑問をもち、他者からの批判を受け入れる意思も含まれている。これが討論の本質なのだ。
しかし最近の研究によれば、反対の証拠を突きつけられると、人は自分の意見にさらに固執するようになるという。
フランドル地方出身の哲学者で生物学者のルーベン・メルシュは、著作の中でこの仕組みについて考察している。
彼はそのために多数の心理学的実験を分析しているが、その中には道徳心理学の専門家であるニューヨーク大学のジョナサン・ハイトによる、次のような思考実験も含まれている。
姉弟のジュリーとマークは、一緒にフランスを旅行している。どちらも大学の夏休み中だ。
ある夜、海岸近くの小屋に泊まっていた2人は、セックスをしてみたら面白くて楽しいのではないかと思いついた。
少なくとも、お互いにとって新しい経験になるだろう。
ジュリーは避妊薬を飲んでいたが、マークは念のためコンドームを使った。
どちらも行為を楽しんだが、もう二度としないと決めた。
その夜のことは2人の特別な秘密だ。
この経験を通して、ジュリーとマークはさらに親密になった。
ハイトはこのストーリーをさまざまな人に提示し、ジュリーとマークの行動についてどう思うか尋ねた。
誰もが否定的で、間違っている、不道徳だといったレッテルを貼った。
だが、説得力のある根拠を示せた人はいなかった。
客観的に言えば、犯罪は行われておらず、近親交配の危険もない。
どちらも同意していたし、誰にも危害を加えていない。
つまり、回答者たちの確信的な意見は、知識や事実ではなく、単なる直感に基づいていた。
メルシュはこうした例を用いて、私たちの直感が理性に勝ることを示している。
人は、事実や数字が自分の判断と矛盾していても、自分の視点や感情、信念を守り続けようとする。
「私たちは、酔っぱらいが街灯柱につかまるように事実を使う。つまり、照明用としてではなく、サポート用として」。
私たちは常に自分が正しいと証明されたいと思っているので、自分の視点に合うように目の前の情報にフィルターをかける。
「私たちは現実を疑わない。その代わりに、自分が聞きたいことを告白するまで現実を拷問する」。
(本記事は『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』の一部を抜粋・編集したものです)