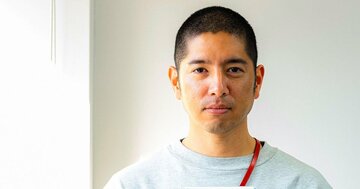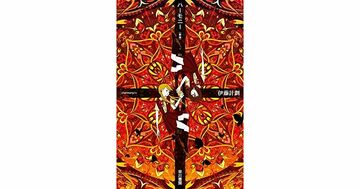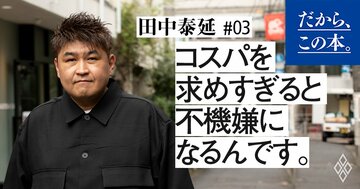まず、「役に立つ」はいつだって目的を必要とする。
「役に立つ」のは常に何かのためなのであって、目的のない「役に立つ」はありえない。「役に立つ」は「目的―手段」というペアの形でしか存在できない。
そして、このペアは時間の順番が決まっている。目的はいつだって手段よりも先、つまり未来の側にある。「未来の目的」に向けて「現在という手段」が存在する。
だから、もし「これって役に立つの?」と問う側にまわってしまうと、現在という時間は、未来の目的のための手段になってしまう。
「前のめり」の強迫意識
現在の手段化。それは、『急に具合が悪くなる』を著した宮野真生子の言葉を借りれば「未来のために今を使っ」てしまうことだ。
臨床哲学者の鷲田清一は、この現代人の様子を「〈前のめり〉の時間意識」と表現した。鷲田によれば、「前のめり」の時間意識は近代経営のあらゆる場所に浸透している。
少し長くなるが、鷲田の2冊の本から引用する(pro-というのは、「前」を意味する英語の接頭語だ)。
“企業においても個人においても未来における決済(プロジェクトの実現や利益の回収)を前提にいまの行動を決めるという意味では、ひとに〈前のめり〉の未来志向の姿勢をとらせる”
(以上、鷲田清一『だれのための仕事―労働vs余暇を超えて』P23より)
(鷲田清一『老いの空白』P64より)
(鷲田清一『だれのための仕事―労働vs余暇を超えて』P24より)
「〈前のめり〉の時間意識」を鷲田が指摘したのは、もう約30年も前のことだ。
ビジネスの世界では、目的を達成するのは速ければ速いほどいい。
だから、身体はどんどん前のめる。
そして未来に手を伸ばすほど、足元がおろそかになる。
「分配される時間」と「生成される時間」
生産性の概念、つまり「少ない時間でより多く」という考え方を内面化した僕たちは、プライベートでも時間を無駄にすることへの恐怖に取り憑かれてしまう。このしんどさにどう向き合ったらいいのだろう?
少しだけ、時間を戻したい。
うつの下降期、不眠のくせに無茶な登山を繰り返していた頃、僕は妻に「登山がいよいよできなくなったので、湯治(温泉療養)にいかせてほしい」とお願いした。アクティブバカである。「自分の行動によって治す」という考え方を僕はまだ捨てきれずにいた。
湯治先に着いた僕は、「温泉につかり部屋でゴロゴロ」を2、3回繰り返した。すぐ飽きた。ダメだ、暇すぎる。もっとも、暇が苦手だから今こんなことになっているのだが。
館内をぶらついていたら、書棚に本が並んでいるのが目についた。もう本など読める状態じゃなかったがそれでも職業柄、足が止まった。
すると、その中の1冊に不思議とすっと視点が定まった。『時間についての十二章』。
目立つタイトルではない。内山節という著者名にも見覚えはなかったが、なぜか手に取った。あり余った時間が当時もっとも切実なテーマだったからかもしれない。
なんと、読めた。驚くべきことに50ページほど読めた。なぜ驚いたかというと、当時は宿のチェックインの会話すら苦痛でしょうがなく、数行しかない「宿泊者への注意書き」すら、何度読んでも意味が理解できないほど、脳がお休み状態だったのだ。
著者の内山は、群馬の山奥で畑を耕し釣りに興じる、文字どおりの「在野」の哲学者だ。彼の時間論はとてもユニークで、まず近代社会が常識とする「24時間を全員が等しく分配されている」という前提を明確に否定する。そして時間は「分配」されているのではなく、「生成」されてゆくものだと主張する。
時間を自分がつくり出すなんて考えてみたことすらなかった。24時間が全員に等しく与えられているという前提を疑ったことすらなかった。けれど、村で生きる内山によれば、「自分とお隣さん」「自分と川」「自分と畑」など、異なるもの同士それぞれの関係性のなかで時間は生成されていくらしい。
「分配された時間」を生きると、とたんに「この時間をいかに効率的に使うか」という競争に巻き込まれる。この「効率的な時間」への強迫観念は、鷲田の「他人に、あるいは社会に、遅れてはならないという、わたしたちを恒常的におそう強迫的な意識」とほぼ同じものだ。
「時間は、与えられたものとしてすでにあるのではなく、生み出していくもの」という180度の視点の転換。分配される時間と、生成する時間。なぜだか読めたその50ページに、僕は一生の付き合いになる言葉を見つけたのだった。
ただし、後日談がある。しばらく経ってから、僕はあらためて『時間についての十二章』を手に取った。すると、ないのだ。あれだけ衝撃を受けた「分配」と「生成」という言葉がない。内山は同様のことを「消費される時間」と「創造される時間」と表現していた。「分配」と「生成」は、僕の誤読だった。
うつのどん底で、「創造」なんて何もできなかった自分が、無意識に覚え違えたのかもしれない。理由はわからないが、僕は、内山本人の言葉ではないことを断ったうえで、「消費と創造」を「分配と生成」と読み替え、この本の後半で突き詰めて考えてみたい。何もできない、あるいは役に立てないことに苦しむ人間を、救い出す言葉として。
僕たちはもっとゆったり生きるはずだった
“私たちには時間がない、あふれんばかりに勝ち取っているのだが”
『加速する社会』という本には、こんな刺激的なキャッチコピーが踊る。テクノロジーに囲まれた現代を生きる僕たちは、本来時間を持て余していてもおかしくない。だからこそ、経済学者のケインズは週15時間だけ働く未来を夢想したはずだ。『加速する社会』の著者であるハルトムート・ローザも、テクノロジーは本来、時間の「欠乏」じゃなくむしろ時間の「利得」をもたらすはずだ、と書いている。
そう、僕たちはもっとゆったり生きるはずだったのだ。でも、実態はその真逆を行っている。
いったい、なぜこんなことになっているのか。