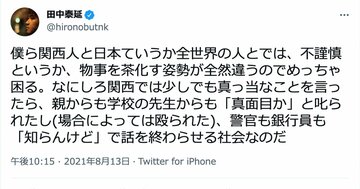《役所の中でどんなことばを遣おうがそんなことはどうでもいいんです。それはウチ向きの話です。お客さんいててのソト向きの仕事なんで、用紙がないという声を聞いたら、用紙ありますよ、とこちらから持って行きます。お客さんが情報をくれない限り動けないのです。》
《方言の入り込み方も違ってくると思います。我々は納税者からしたら来てほしくない嫌な相手です。中小企業の社長や小売の経営者からしたら自分の財布に手を突っ込まれるようなもんです。でも個人の懐に入り込む時に方言を使うのは有効な手段です。ビジネス上の共通言語は、ずっと商売されているかたを対象とするので、関西弁です。話の枕でいかにうまくコミュニケーションをとってどんな人間関係を築くかです。》
《ですから、冒頭に『どうでっか?もうかりまっか?』『ぼちぼちでんな』という会話をするのは普通です。半日かけて通常のお金の流れを把握して、イレギュラーの箇所を書類から見つけるのですが、方言を使ったほうが本当のことを言いますね。『どうしてですか?』より『あんた、言ってること、違うやん?なんででんねん、社長?なんでこんなことしまんねん?』というふうに、意図して方言を使います。》
大阪国税局の調査力がすごいのは
大阪弁の力が強いから説
商売人の共通言語を使いながら相手を怒らさないように会話を継続し、税を納めてもらう方法はビジネスそのものといえるだろう。
《むりやり追徴して会社を潰したらだめなんです。灰色の部分などは相手にも言い分があります。(追徴の)100見つけたら、(全部払って会社が潰れる場合など)『50は今払うてや。50(期間損益のずれなど)は今度しっかり儲けて(納税)し直してや』と関西弁で入って、同じビジネスの土俵で勝負してビジネスのセンスの範囲内で話をつけていかないと相手は納得しません。納得させて正しい方向へ導くというか、納得ささなあかんところが他の行政と違うところでしょう。》
《租税法律主義ですから、負けてあげるとかひどく取られることもないですが、ある意味一番融通のきく役所やと思います。方言で相手の世界で情報収集して調査を進めていく役所ですね。ちなみに大阪国税局は調査能力が一番高いんです。それは関西弁という商人とのコミュニケーションツールを持っているから、方言が効いているのかもわかりません。東京は権利意識が強いから標準語で法律でバシバシ割り切る。税の世界の文化の違いでしょうか。》