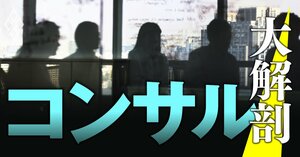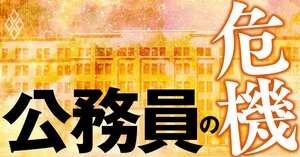中学・高校の学習範囲でも
小学生の知識で解ける
玉木 そうなんです。25年の理科の入試問題では、「ボイル・シャルルの法則」を扱いました。気圧の問題で、片方に真空のタンクがあり、そこに酸素を1グラム入れる。タンクとつながった試験管があり、その酸素を温めると気圧が高くなり、水面が上がる。
これはボイル・シャルルの法則で中学以降に学ぶ内容なので、小学生は知らない。けれども、そのシチュエーションと温度が何度の時に水面が何メートルになっているかを示した表は資料として付記しておく。25度上がると何メートル、15度上がると何メートル……と、何メートルずつ上がったのかが表になっているので、その規則性に気づくことができたら答えが導き出せる。
渋田 ボイル・シャルルの法則を知らなくても小学生の知識で解けるようになっている。
玉木 そうです。子どもは法則を知らなくても、その表を見て自分の頭の中で「ああ、こちらの数字がこうなっているとき、こちらはこうだから、温度と気圧に関係性があるんだな」と推理して、問題を解くことができる。自分の頭を使って与えられた事象から推理推測していけば、法則を見出だせる。これが洗足の授業の根幹にあり、そこに連動しているのが入試問題なんです。
第1回入試問題〈理科〉
解答用紙
解答例
採点者所見
(※本記事の外部配信先では過去問を閲覧・ダウンロードできない場合があります)
渋田 大学入試が変化している影響で、こうした思考力を試す中学入試問題が増えていると言われていますが、洗足の場合は、もともと洗足がやっていた教育に、大学入試が追いついてきたのではないかと思います。
玉木 そうですね。洗足の特徴は各教科の担当が、入試問題を好き勝手に作っているのではなく、学校として、授業の中でこういうことをやらせたいという一本の芯があり、その強いメッセージ性を各教科の手段を使って発信するという形になっています。四教科共通の理念のもとに各教科の問題がある。
渋田 教科横断型の入試も出てきていますが、すでに授業でも入試問題でもそういうことをしているわけですね。入試で出た問題を授業で扱うこともあるのですか。
玉木 あります。国語は特にそうです。本校のオリジナルテキストの「洗足国語」のテーマは、入試で出した説明文的文章と深い部分でつながっています。
渋田 一貫した学びということですね。作問者と教科の担当が同じだというのが洗足の中学入試の本質ですよね。塾の模試は模試を作っている人と教えている人も違うし、それが入学後に関わっているわけではないですものね。
玉木 入試問題をしっかり理解したうえで、「こういう問題を出すような教育を受けたい」と思って入ってきてもらうのが理想です。
よく、保護者から、「模試での偏差値が足りないから、やはり洗足に入るのは無理でしょうか」と相談されるのですが、「模試はあくまで模試でしかありません。洗足の入試では、入学後の学習の可能性を見出したいと思って問題をつくっているので、過去問を解いてみて志すかどうかご判断下さい」とお願いしています。