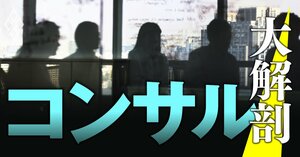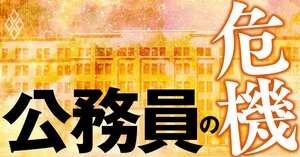「迷わせる教育」が
もたらす成果
渋田 洗足学園といえば、今や東大に28人現役合格という過去最高の実績を出されています。進学実績ばかり取り沙汰されて、「『ガリ勉』させられるのではないか」「管理がきついのではないか」というイメージを持たれるかもしれないのですが。
実際は、勉強しろと言うだけで、多感な年齢の女の子たちが勉強をするわけもなくて、根本的に納得しなければなかなかうまくいかないですよね。
玉木 進学先の選択の根っこは、まさに洗足のキャリア教育にあるんです。一言で言うと「いろんな選択肢を持って思いっきり迷ってもらう」ということです。キャリア教育が、進路に、そして、進学先としての大学進学実績にもつながりますが、根本はキャリア教育です。
渋田 「ちゃんと迷う」というのは非常に重要な経験ですよね。要は1つの答えを突き詰めるのではなく、いろんな可能性を模索した上で、答えが見つけられないくらいまで選択肢を広げる。
玉木 そうなんです。校長の宮阪が就任して、改革に着手したことの一つに「哲学対話」の導入があります。これは迷うことの好例です。対話なので、ディスカッションやディベートのように、議論の中でひとつの答えに収斂させていくことが目的ではない。結論は見出さない。
大前提として他人の言うことは否定しないというのが対話のルールなので、自分とは違う価値観を持った他人の意見を聞くことによって、自分の考え方が本当に正しいのか疑問を持ちつつ、相手の考えもいいねと認めていくと、ますます迷う。
渋田 どのようなテーマで対話をするのですか。
玉木 例えば、「幸せとは何か」を中1の最初と高3の哲学対話で採り上げます。もちろん両者の対話のレベルは違うのですが、みんな迷っているという点では共通している。
ある人はお金だといい、ある人は時間だといい、ある人は、愛情や共感だという。確かにお金だけあっても、それを使う時間がなければならないし、いや、愛情や共感を得られなければ、結局ひとりで何かしても虚しいよね、とも思う。
渋田 6年間たっても迷い続けている。
玉木 幸せが何かという問いの結論には、ちょっとやそっと議論したくらいでは到底行き着かないと中1も高3も気づくんです。それは非常に大きなことですね。