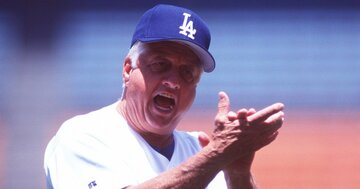仕事を任せられなかった
私の考えが変わったきっかけ
私が先述のアパレル専門店チェーンの大型店の店長に就任して間もないころ、休み明けに出勤すると、店内が理想とかけ離れた状態になっていて、思わず「なんでこうなるんだ…」と心の中でつぶやき、ため息をついたことが何度もありました。
とくに、新商品の入荷があった翌日は大変でした。本来、入荷した商品はすぐに店頭に並べるべきですが、ストックスペースに放置されていたり、店舗の隅に目立たない形で陳列されていたりすることが頻繁にありました。大型店ですから、商品の入荷点数が通常店の倍以上と多く、来店客数も倍近いので、副店長やスタッフだけでは、現場を回しきれない状態になるのは致し方ないところもありました。
そういう状況が続く中で、当時の私は仕事を部下に任せることを諦めてしまいました。私自身の休みの前日には、伝達事項を細かく書き連ねた「指示書」を作成するのですが、その内容は次第に膨れ上がり、巻物のような長さになっていました。それでも心配なので、電話で指示をしたり、店に顔を出したりしていました。
当時の私が、なぜ部下に仕事を任せられなかったのか?それは、部下がやった仕事が自分の求める合格点に達していないと思っていたからです。私にとっての合格点は、自分が行ったときと同じレベルになる100点を指し、それに満たなければ、任せられないと捉えていたのです。
その考えを変えるきっかけになったエピソードをご紹介しましょう。
店長として就任して2年目になったとき、1人の女性スタッフが入社してきました。彼女は、仕事の出来栄えはいつも70点ギリギリという状態でした。私が考える70点とは「大きなミスや致命的な間違いはないが、仕事の出来栄えは良くも悪くもない」という状態を指します。
そんな彼女は、私から見れば「突っ込みどころが満載」という状況でした。ところが、お客様からの評判はよく、販売成績はいつも上位でした。なぜ、「ギリギリ及第点」なのに、成績が良いのか?それは、不足している30点を、個性や強みでカバーできていたからです。そうすることで、お客様からは、合格点に達していると感じてもらえていたのです。
彼女を見ていて、これまでスタッフに対して100点を求めていたのを改め、大枠はできているとして、合格点を70点にしようと決めたのです。
「70点合格」にしてからは、休日に現場を任せることができるようになり、私自身のストレスも軽減されましたし、職場の雰囲気も良くなりました。
ただ、その後、すべてがスムーズに進んだわけではありません。どれだけ工夫や努力を重ねても、任せることが難しい場合もありました。
もちろん、時間を掛けて教育をすれば、部下は成長します。ただし、それは本人に変わりたい、成長したいという強い意志がある場合に限ります。部下にその気持ちがなければ、いくら教育をしても任せられる人材にはなれません。
人には得手不得手がありますし、興味を抱く対象にも違いがあります。もし、部下が「この仕事を任されたい」と望んでいなかったり、もしくは、何度か任せてみたが適性に合わないと判断した場合は、無理に任せようとするのは避けましょう。最後の選択肢として「任せることを諦める」という決断が必要な場合もあります。