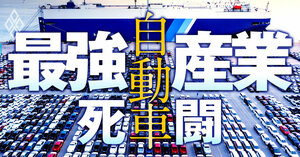部下と直接話せない上司は、管理職としての職務を果たせていない
Bさんが出社するようになってから1週間後に、Aさんとの面談がありました。
当初、今までのようにBさんと会話をすることを避けていたというAさん。「もしも、また泣かせてしまったら……と思うと、怖くて声をかけられない」というのです。しかしこのままでは、指導も指示もできず、正当な評価もできないわけなので、「管理職として職務を果たせていない」と指摘をさせていただきました。
では、Aさんはこれから、具体的にどうしたらよいでしょうか?
まずは、Bさんとの面談を設定することを提案しました。そして、このできごとの発端である指導の仕方について、「本来どうすべきだと思うか?」とAさんに尋ねました。
するとAさんは「自分の指導が雑だった。まずは、具体的なミスについて指摘をして、改善策を一緒に考えればよかった。それから、日々のコミュニケーションも足りているとはいえなかった。テレワークの弊害もあり、部下との距離感も少し遠くなっていたかもしれない」などと話してくれました。
「では、率直にBさんに伝えてみてはいかがですか?」とお伝えすると、「今さらな感じがする」と少し抵抗感はあったようですが、このままの関係性でいるよりはいいと思ってくれたようです。「評価のこともあるので、関係性を修復するためにも話をしてみます」と話していました。
その後、AさんはBさんだけでなく他のチームメンバーにも今まで以上に気を配り、部下を観察し、声かけをするようになったそう。それからはチームの雰囲気もよくなり、休憩時間の雑談も増えたということです。
「作成した書類に誤字が多いから確認してから提出してください」と部下に業務ミスを指摘したら「私だって一生懸命やっているんです!」と泣かれてしまった。これはパワハラ?
【解決ポイント】
明らかに業務上の指導・指摘でも、お互い人間ですから、相手のコンディションが悪いこともあるでしょう。例えばプライベートで問題があった日の翌日の指摘であれば、受け止めきれないこともあるかもしれません。毎日、アイコンタクトしながらあいさつ、そして一言声をかけてみましょう。日頃から部下の様子に気を配ることも、上司の大事な仕事です。
【パワハラ判定】
「上司の指摘により部下が泣いてトイレに駆け込む」という場面だけを切り取ってしまうと、周囲からはパワハラと思われてしまう場合もあります。しかし、厚生労働省の判断基準としては、以下のように表記されています。
☆厚労省の判断基準のポイント
• 「本人が不快に感じた=パワハラ」とは限らない
• 判断には客観性が必要(例:平均的な労働者が看過できないと感じるか)
• 個人の属性(年齢・経験・障害・外国籍など)や心身の状況も考慮される
今回のケースは、パワハラには該当しないと判断します。なぜなら、本人のプライベートの状況が影響していたことが大きく、もし、本人のメンタルが安定した状態であれば、特に問題は起きなかったのではないでしょうか。もちろん、日頃からの上司部下の関係性がどうであるかも考えて、慎重に判断することが大切です。