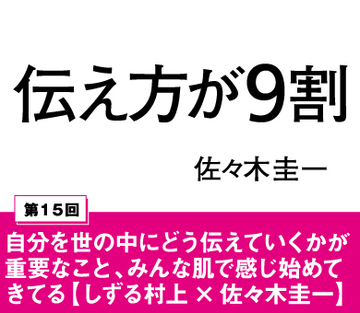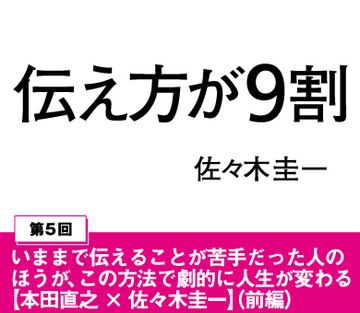しずる村上が大きく変わった転機
 佐々木圭一(ささき・けいいち)コピーライター/作詞家/上智大学非常勤講師 上智大学大学院を卒業後、97年広告会社に入社。後に伝説のクリエーター、リー・クロウのもと米国で2年間インターナショナルな仕事に従事。日本人初、米国の広告賞One Show Designでゴールド賞を獲得(Mr.Children)。アジア初、6ヵ国歌姫プロジェクト(アジエンス)。カンヌ国際クリエイティブアワードでシルバー賞他計3つ獲得、AdFestでゴールド賞2つ獲得、など国内外51のアワードを獲得。郷ひろみ・Chemistryの作詞家としてアルバム・オリコン1位を2度獲得。twitter:@keiichisasaki
佐々木圭一(ささき・けいいち)コピーライター/作詞家/上智大学非常勤講師 上智大学大学院を卒業後、97年広告会社に入社。後に伝説のクリエーター、リー・クロウのもと米国で2年間インターナショナルな仕事に従事。日本人初、米国の広告賞One Show Designでゴールド賞を獲得(Mr.Children)。アジア初、6ヵ国歌姫プロジェクト(アジエンス)。カンヌ国際クリエイティブアワードでシルバー賞他計3つ獲得、AdFestでゴールド賞2つ獲得、など国内外51のアワードを獲得。郷ひろみ・Chemistryの作詞家としてアルバム・オリコン1位を2度獲得。twitter:@keiichisasaki
佐々木 村上さんは、もともと伝えるのが上手だったんですか。
村上 いや、だいたい下手でした。
佐々木 本にも、かつて滑ってばかりいた芸人、という記述がありますね。
村上 それはやっぱり独りよがりだったんです。自分で勝手に面白いと思って、かっこいいイメージを作ったりして。憧れの芸人さんの真似をしたりとか。
でも、実際には、それでお客さんを笑わせたこともないわけですね。これで滑ったら、もう最悪なんですよ。ところが、お客さんがついてこられなかったんだ、とか、オレがやっているのはセンスが良すぎるんだ、みたいな、ものすごい痛い考え方があった時期があって。
佐々木 そうだったんですか。
村上 でも、やっぱり自分の中ではつらいわけですよね。滑って滑って、を繰り返したら、やっぱりウケたいってなるから、だんだんだんだん角が取れてマイルドになって。ただ、それでも、まだどこかで、あまのじゃくというか、ちょっと斜に構えた感じでいきたい、みたいなところはあったんですけどね。
でも、それは本当に自分が思っていたものでは、実はないんですよ。自分が生きてきた中で培ってきたというよりも、なんとなくかっこいいな、みたいなものが頭にあっただけなんです。それを無理に自分に落とし込めようとしていた。それはちょっと違うな、と気づき始めたところが、転機だったですね。
佐々木 そういう経験をちゃんと自分で積まれたんですね。
村上 やっぱりステップがあったわけです。渋谷の舞台に出て、そこから次はルミネよしもとの若手のところに出られる。その後もステップがあって。ひとつステージが上がるごとに、お客さんの層も変わるんです。
そうすると、それまでやっていた箱で見てくれていた人には通用したことも、次には通用しなくなったりする。興味がない人間をしっかり見ようなんて、思ってくれませんしね。そのときに見てもらおうと思ったら、コントの前提を変えないといけないわけです。
それでテレビに出るとなったときに、またひとつ変わった。それこそ、レッドカーペットがそうでしたよね。
佐々木 そうですね。
村上 流れてるんですよ、カーペットが。あれはすごい象徴的だなと思って。一分半くらいなんですけど、ショート、インスタントの中で、どんどんどんどん流れていく。ブームになりましたけど、あれはまたひとつの転機でした。
甘酸っぱい青春コントというキャッチコピーを最初に付けられたんですが、僕らが思っても見なかった方向性だったんですよ。でも、自分たちは本当はこうなんだ、なんてテレビで言えるような立場にない。だったら、ひとつのコマになろう、ピースになろうと思ったんです。そのキャッチフレーズでコントをたくさん作ったほうがいい、と。
そうやって、お客さんや視聴者のことを考えるようになってから、たぶん少しずつウケることができたんだと思う。