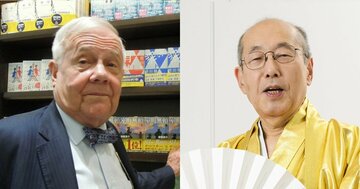新年早々の1月2日、ニューヨーク市場で、原油がついに100ドル超えを果たしました。一部報道では、ある金持ちが、なんと孫に自慢するために、100ドル手前で一進一退を繰り返していた相場に、損失覚悟で、巨額の買いを入れたとのこと。年間11兆円強(2006年度)、8年前と比べてすでに4倍の額に膨れ上がっている原油を輸入している日本からすれば、とても笑えた話ではないでしょう。
新年早々の1月2日、ニューヨーク市場で、原油がついに100ドル超えを果たしました。一部報道では、ある金持ちが、なんと孫に自慢するために、100ドル手前で一進一退を繰り返していた相場に、損失覚悟で、巨額の買いを入れたとのこと。年間11兆円強(2006年度)、8年前と比べてすでに4倍の額に膨れ上がっている原油を輸入している日本からすれば、とても笑えた話ではないでしょう。
日本は今、1970年代のオイルショック以来30年ぶりとなる“値上げ嵐”のさなかにいます。当時のような狂乱物価に比べればはるかに穏やかであるにせよ、広範にわたる石油由来製品の値上げが、消費者物価をじわじわと引き上げていることはいうまでもありません。
しかも、今回の物価上昇圧力の背景には、中東戦争やイラン革命が引き金となった過去2度のオイルショック時とはまったく異なり、世界経済の構造変化、すなわち桁外れの水準に膨張した投機マネーの存在とバイオ燃料ブーム、そしてなにより新興国経済の勃興があります。その結果、小麦や大豆などの穀物市場も軒並み記録的な高値に押し上げられるという、“資源小国”日本にとっては、極めて頭の痛い事態が進行中です。
今後の見通しも楽観できません。サブプライム問題処理の長期化に伴い、米国株などのドル資産を忌避した投機マネーが実体経済に裏打ちされた原油など商品市場へさらに流入することは避けられそうにないからです。下方調整局面が断続的にあったとしても、新興国経済が一気に冷え込まない限り、再び高値を目指す可能性が大。じわじわと静かに“川上インフレ”は進んでいくことでしょう。
本誌では今回、こうした“新型インフレ”懸念の高まりを踏まえて、「値上げが襲う」との特集を組みました。これは、言い換えれば、景気の行方を探る特集でもあります。
ただ、通常の景気特集が、指標重視の“大所高所”の分析にとどまることが多いのに対して、今回の特集はあくまで“小所低所”にこだわりました。なぜなら、値上げに襲われた庶民の生活、燃料・原材料費高に直面した中小・零細のあえぎ、さらには、企業間の価格転嫁交渉という現場にこそ、指標に現れない景気の行方のヒントが隠されていると考えたからです。そして、小所低所の事実の積み重ねから見えてきた結果は、けっして楽観できるものではありませんでした。
値上げ列島は今、景気後退の危機にある――それが特集取材班の出した結論です。
(『週刊ダイヤモンド』副編集長 麻生祐司)