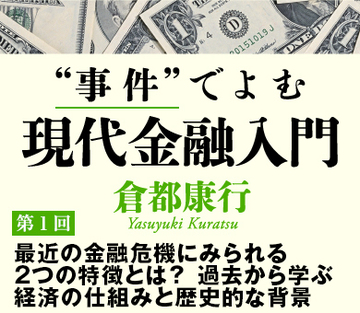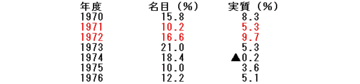察知していた欧州と
蚊帳(かや)の外だった日本
叡智を集めて構築されたブレトン・ウッズ体制により、通貨システムがひとまず安定化していたことで、各国はその制度の永続性を過大に評価し信じすぎてしまったのかもしれません。しかし、1960年代にはドル不安が高まり、システムの脆弱性は日増しに強くなっていきました。ドル不安を通じた金価格の上昇という現象も観測されはじめていました。
そんな状況で、アメリカの金兌換停止という決断が、本当に世界にとって「寝耳に水」だったかは疑わしいところです。特に欧州諸国が、ドル交換要請に対するアメリカの消極的対応に不信感を募らせていたことは間違いありません。
たとえば、1961年に設立された「金プール制」という制度があります。これは欧米7カ国が手持ちの金をプールして、ロンドンの金市場の操作を通じて金価格の安定を図ろうとしたものです。これは、明らかにブレトン・ウッズ体制の脆弱化をサポートする仕組みでした。
おそらく欧州勢は、この金プール制を通じて、金ドル本位制という通貨制度の崩壊は時間の問題ととらえていたと考えられます。残念ながら、極東の敗戦国であった日本にこうした制度への参加機会すらなく、金融情報戦で大きく遅れを取っていたようです。
スミソニアン協定後の
変動相場制は理想的か
さて、ニクソン・ショックの後、新たな水準での固定相場制への復帰が議論されました。その回答が、1971年12月にアメリカワシントンDCにあるスミソニアン博物館で合意された「スミソニアン協定」です。そこでは、金兌換停止のまま各国通貨をドルと交換する場合の新たなレートが確認され、円は16.88%切り上げられて1ドル=308円となりました。ドイツ・マルクやフランス・フラン、オランダ・ギルダーなど欧州通貨も、切り上げた水準でドルとの為替レートが決められました。なかでも切り上げ幅が最大だったのが円でした。
それぞれ通貨の変動幅は上下2.25%に設定され、金価格も1オンス=38ドルに切り上げられました。これで新たな固定相場制度に戻れると期待されましたが、アメリカが金とドルの交換を復活させない状況下では、不安定な相場推移が続くことになります。最初の投機のターゲットになったのは英ポンドでした。
スミソニアン協定で8.57%切り上げられたポンドには、当初から過大評価が指摘されていました。ポンドへの売り圧力が増すと、介入に耐えられなくなったイギリスは1972年6月に変動相場制に移行しました。そして投機の矛先は、ポンドから米ドルへと向かい始めたのです。こうなると、スミソニアン体制の維持は難しくなるばかりです。
1973年にはイタリアの二重相場制への移行を契機に、スイスが介入を停止、円も変動幅に収まらなくなって変動相場制へと移行するなど、通貨体制の綻びが拡大しました。最終的には同年3月に、ドイツなど主要国も変動相場制への移行に踏み切ったのでした。その結果、スミソニアン体制は1年半ももたずに幕を下ろすことになりました。