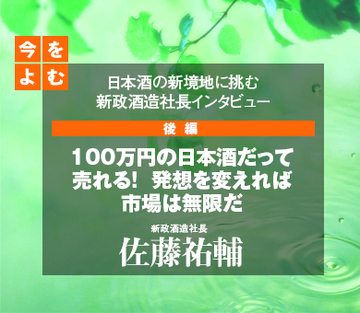大石 マスの心に届いたと実感して得られる高揚感は格別ですし、それを追い求めるんですけど、桜井さんがおっしゃるように、最初からマスの声を聞こうとする姿勢ではダメだと思います。ドラマでも、まずは自分と対話することで、何をどう描きたいか、マスに何を伝えたいかが見えてくる。それをプロデューサーやディレクターなどと突き詰めて、映像として作っていきます。
桜井 まず自分自身に問うという点は、まさに日本酒造りと同じですね。色々あるでしょうが、現代のドラマ作りにおいて難しさはどんな点にありますか。
大石 苦しいなあと思うのは、ドラマ作りにおいて自分のテイストや狙いをブレンドしていくバランスでしょうか。テレビという媒体は、番組が気に入らなければ、リモコン操作ひとつでチャンネルを変えたり電源を切ることができます。作り手はそれを前提として、保守的な視聴者にもわかりやすく、かつ新しいものにアプローチしていかなければなりません。だから、受け入れてもらいやすいドラマに仕立てながらも、その中に大石静らしい私の生き方に合った台詞を1時間に1つか2つ、さりげなく散りばめていくという感じでしょうか。
桜井 視聴者にどうアプローチするかという難しさがあるわけですね。それはテレビ局側の自主規制という側面はないんですか。
大石 たとえば約40年前の向田邦子さん脚本のドラマなんて、濡れ場のような直接的な表現はないのですが、非常にアナーキーでエロチックで、でもそれが受けていた。当時のドラマには時の総理大臣に対する批判も普通にあったし、それと比べると最近のドラマはセーブしていますよね。当時は、テレビが登場してまだ20年ほどしか経っていない黎明期で、“テレビはかくあるべし”という定型もなかった。そういう何でもアリという時代のお陰もあったと思います。
日本のドラマも米国のように
海外展開ありきの製作になるか?
桜井 単純な比較はできませんが、米国のドラマはかなり映画的というか、斬新で挑戦的な企画も少なくない印象です。出張中、ホテルに戻ってテレビをつけたら引き込まれて、つい夜更かしして観てしまったという経験も多いなぁ。
大石 米国のドラマはかなりの予算を注ぎ込んで、医療ドラマで全方位から撮影できる手術室の大がかりなセットを組んだり、大量のエキストラを使っていたりします。これは、最初から全世界に発信する前提で製作されているからこそ、できることです。韓国あたりの作品も、自国マーケットが小さいぶん最初から海外発信を狙って作っていて、日本を含むアジア市場を中心に広くプロモーションしていますね。