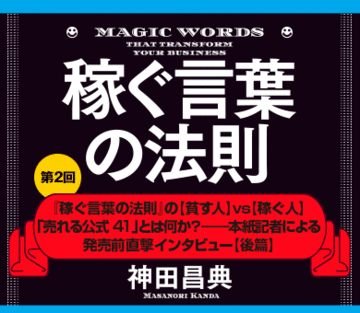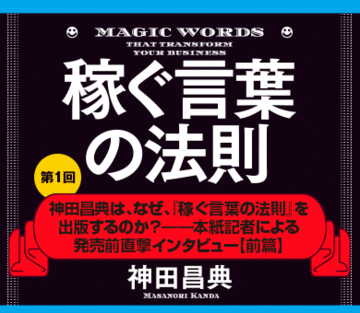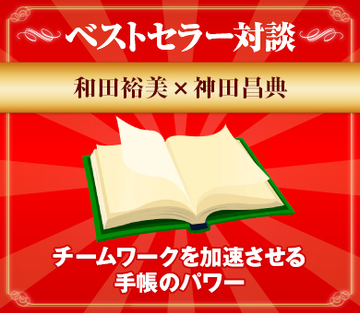1999年12月に、見るもまぶしいピンクの装丁で一世を風靡した『あなたの会社が90日で儲かる!』。「ビフォー神田昌典」「アフター神田昌典」といわれ、「ビジネス書の産業革命」を起こした神田昌典氏。あれから、はや17年がすぎた。
『非常識な成功法則』『起業家の告白』など数々のベストセラーを連発するだけでなく、監訳者として、 “黄金のクラシックシリーズ”3部作『ザ・コピーライティング』『伝説のコピーライティング実践バイブル』『ザ・マーケティング【基本篇】』『ザ・マーケティング【実践篇】』などの名著を世に広めた。
特に、『ザ・コピーライティング』は、436ページ・税込3456円ながら、アマゾン「この15年で最も売れたビジネス書ベスト50」にもランクインされた名著だ。
そんな神田氏の待望の新刊『稼ぐ言葉の法則――「新・PASONAの法則」と売れる公式41』が、本日2月13日(土)、ついに発売!
『稼ぐ言葉の法則』には、1999年に開発されて以来、17年間書籍化されてこなかった「PASONAの法則」が、「新・PASONAの法則」として収録されているらしい。
そして、もうひとつの目玉が、「【貧す人】vs【稼ぐ人】売れる公式41」だ。神田氏が「公式集」を出版するのは初だという。
つまり、最新刊には、「本邦初」がダブルで収録されていることになる。
神田氏は言う。
「今回の本は、マーケティング、マネジメント、リーダーシップ、アントレプレナーシップ(企業家精神)、アドミニストレーション(管理)、営業、起業ノウハウなど、ビジネス書20冊分プラスMBA課程2年分のノウハウをオールインワンの発想で、192ページの一冊に詰めた」
どんな思いで、すぐに使えるノウハウと深淵なメッセージを一冊にとじ込めたのか?
リリース前に、アマゾン総合3位(ビジネス・経済1位)となり、2月16日の「日経新聞」に掲載予定の『稼ぐ言葉の法則』。担当編集者が、神田氏の事務所を直撃した。
高価格ながら、累計6万部を突破した
“黄金のクラシックシリーズ3部作”
 神田昌典(Masanori Kanda)
神田昌典(Masanori Kanda) 経営コンサルタント・作家。株式会社ALMACREATIONS代表取締役。日本最大級の読書会「リード・フォー・アクション」主宰。上智大学外国語学部卒。ニューヨーク大学経済学修士、ペンシルバニア大学ウォートンスクール経営学修士。コンサルティング業界を革新した顧客獲得実践会を創設(現在「次世代ビジネス実践会」)。のべ2万人の経営者・起業家を指導する最大規模の経営者組織に発展。わかりやすい切り口、語りかける文体で、従来のビジネス書の読者層を拡大。「ビフォー神田昌典」「アフター神田昌典」と言われることも。『GQ JAPAN』(2007年11月号)では、「日本のトップマーケター」に選出。2012年、アマゾン年間ビジネス書売上ランキング第1位。著書に、『あなたの会社が90日で儲かる!』『非常識な成功法則【新装版】』『口コミ伝染病』『60分間・企業ダントツ化プロジェクト』『全脳思考』『ストーリー思考』『成功者の告白』『2022――これから10年、活躍できる人の条件』『不変のマーケティング』『禁断のセールスコピーライティング』、監訳書に、『ザ・コピーライティング』『伝説のコピーライティング実践バイブル』『ザ・マーケティング【基本篇】』『ザ・マーケティング【実践篇】』などベスト&ロングセラー多数。
編集 私は、これまで、神田昌典さん監訳のジョン・ケープルズ著『ザ・コピーライティング』、ロバート・コリアー著『伝説のコピーライティング実践バイブル』、ボブ・ストーン+ロン・ジェイコブズ著『ザ・マーケティング【基本篇】』『ザ・マーケティング【実践篇】』などの“黄金のクラシックシリーズ3部作”を担当させていただきました。
3部作計4冊の総ページ数は「2000」を超え、相当苦労しながらつくりましたが、おかげさまで、すべて3000円以上の高価格ながら、シリーズ累計6万部を突破しました。本当に有り難うございます。
神田 あの3部作は、寺田さんの「執念」でつくったものでしたね。
編集 特に、ジョン・ケープルズの名著『ザ・コピーライティング』は14刷4万部超と群を抜き、Amazon.co.jpの「この15年で最も売れたビジネス書ベスト50」にランクインしました。私自身、いまだに、コピーを考えるときのバイブルになっています。
この本については、あの「広告の父」デビッド・オグルヴィが「この本は間違いなく、いままでで1番役に立つ本である」と言っていますが、これがウソ偽りない。
私が編集者になって担当した書籍が『稼ぐ言葉の法則』で121作目になりますが、『ザ・コピーライティング』ほど役立った本はありません。
思えば、この原書『TESTED ADVERTISING METHODS
「今こそ、どうしても監訳をお願いします!!」
と訴え続けてきたことが少し報われました。
神田 まさに、その執念が、読者の眠った感性を呼び覚ましたのではないでしょうか。