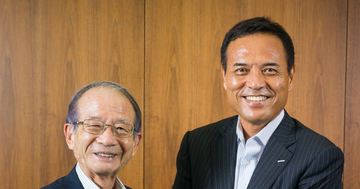質問をし続ける方法を見つけ出せ
疑問や質問が重要だということについては、これだけ有利な証拠が揃い、アインシュタインからスティーブ・ジョブズまで、だれもがそれを支持している。それでも、ビジネスの現場では疑問を抱いたり質問をしたりすることが重んじられることはなく、学校では教えられず、日常生活でも利用されていない。いったいなぜだろう?
一つの理由として考えられるのは、問うという行為はあまりに基本的で直感的なものであるため、それについて考える必要がないから、ということがある。
「私たちは生まれたときから問い続けている」。こう語るのは米国学校改革の潮流の一つ、「スモール・スクール」運動の先駆者、デボラ・マイヤーだ。
たしかに、就学前の子どもは気楽に、平気でさまざまな質問をする。最近の研究で、イギリスの4歳の女児は、一日で平均390回の質問を母親にすることがわかった(ちなみに、4歳の男児はこれよりもはるかに少ないとのこと)。
つまり、この年齢の女の子にとって質問は呼吸のようなものと言えるのではないだろうか。質問は、生まれながらの、生活における基本中の基本の、だれもが当然のこととして受け入れている行為であり、そして子どもでもできる行為なのだ。
けれどもおそらく、その4歳の女の子がその後の人生の中で、光り輝くその瞬間ほど直感的に、独創的に、そして自由に質問をするときは二度とやってこないだろう。よほど非凡な子でないかぎり、質問のピークは4歳のときに訪れる。
この興味深い事実は、それ自体がさまざまな疑問を誘発してくれる。
Q:4歳の少女が5歳や6歳になると、どうしてそれほどものを尋ねなくなるのだろう?
Q:それが彼女や彼女をとりまく世界にどのような影響を及ぼすのか?
Q:もし、アインシュタインの言っているように問うことが重要であるのなら、質問をし続ける方法を見つけ出して、4歳以降の質問の低下傾向に歯止めをかけるべきではないか?
その一方で、「4歳」が例外的に質問の多い年齢なのだ、という考え方もあり得る。人は4歳のときだけ、ベゾスやジョブズのような稀な人たちの仲間入りをできるけれど、4歳を過ぎると皆平凡に戻ってしまう、というわけだ。だとすると、別の疑問も湧いてくる。
Q:問い続ける子どもと、やめてしまう子どもがいるのはなぜか?(遺伝によるのか、それとも学校教育、あるいは家庭教育の影響なのか?)
Q:質問をする人とそうでない人を比べると、どちらが得をしているだろうか?
ビジネスの世界と質問は、一種の愛憎相半ばする関係にある。ビジネス・イノベーションの「教祖」クレイトン・クリステンセンは(彼自身も質問の達人だが)、「質問を発することは、多くのビジネスリーダーから非効率と見られている」と指摘している。ビジネスリーダーは行動したい気持ちが強く、自分たちが取り組んでいることに疑問を抱く余裕などないと感じている、というのだ。
そして、リーダーの地位にいない場合、質問をすると自分のキャリアを傷つけることになるのではないか、と心配する人が多く、そしてその心配はえてして杞憂ではない。
会議室で手を上げて「なぜですか?」と声を上げることは、周りの人から勉強不足だと思われたり、場合によっては反抗的、あるいはその両方と取られかねないからだ。