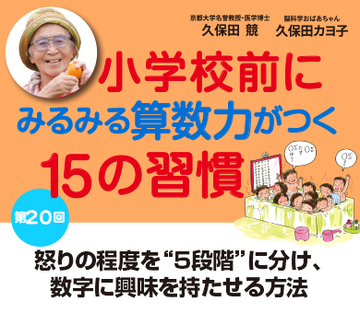記事検索
「数学」の検索結果:2201-2220/2844件
第14回
【森岡毅×佐渡島庸平】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをV字回復させたスゴ腕マーケターと「マーケティング」について語り合った【第1回】
これまで「勘やセンス」に頼りがちだったエンターテイメントの世界をマーケティングの力で成長させることは可能なのか――。まさにユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)をマーケティングの力でここまでにした森岡氏と、仕組みによって作家の世界を広げることに挑戦している佐渡島氏との語らいは必然的に熱いものとなった。

無料公開第2弾 第4回
【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(4)
1つであれ複数であれ分析対象の範囲が決まったら、次はどのような変数を分析すべきかを考えていこう。基本的には一度の分析でアウトカムは1つ、一方、説明変数の候補はいくつあっても構わないし、あればあるだけ最終的な分析結果がリッチなものになる可能性が高い。
![【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(4)](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/2/4/360wm/img_2424295561493df236d175692cd7bcdb452979.jpg)
【無料公開第2弾 第2回】
【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(2)
いわゆるIQやSPIの能力検査などに代表される一般認知能力が高い者は、採用後の業績もある程度高いと考えられる。このような状態を統計学では「一般認知能力と業績が相関する」と表現する。
![【新刊無料公開】『統計学が最強の学問である[ビジネス編]』第2章 人事のための統計学(2)](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/7/9/360wm/img_7998c021c4f8b8f8a50c5a55c7d68f70332090.jpg)
小学1年生から高校3年まで、全行程でゆとり教育を受けた「究極のゆとり世代」が、今年、2016年から初めて社会人となった。「ゆとり世代」と言えば、空気読めない、コミュニケーションとれない、利己的で仕事ができないと、散々なイメージだが、使い方さえ間違えなければ、実は有能である。

第154回
基礎研究のように、懐妊期間が長く、大規模で広範囲に行う必要のある投資は、公的部門が主導すべきだ。その場合、投資資金の財源は、税金ではなく、将来に見返りがあることを考えると、国債が適切である。

近年、東京大学を目指す中国人エリートが絶えない。なぜ、中国人エリート層はわざわざ東大留学を目指すのか。実際に、東大で学んでいる中国人留学生たちにインタビューを重ねると、意外な本音が明らかになってきた。

第41回
算数教育を一変させる大発見をご存知ですか?
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き??最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!算数力アップの秘訣を一挙公開!
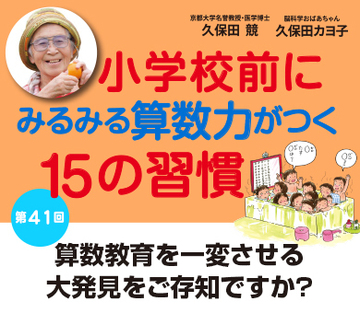
第217回
北京大学、清華大学の滑り止めが日本のトップ大学——。東大、早慶を目指し、中国の成績優秀者が国境を越えて日本になだれ込んでくる時代になった。日本政府はこうした優秀な留学生を高度外国人材として日本に定着することを期待している。互いに補完し合える理想の関係が築けるのだろうか。
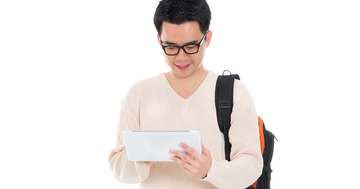
第1回
『GRIT やり抜く力』成功者を決める新しい共通項、次なるアメリカのリーダーはGRITな人
ニューヨークと東京を往復し、世界中の書籍コンテンツに精通するリテラリーエージェント大原ケイが、トップエリートたちにいま、読まれている話題の最新ビジネス書を紹介する新連載がスタート。第1回目は、すでに世界30ヵ国で出版が決まるなど大きな話題となっている、『やり抜く力』をご紹介!

気候変動をめぐって専門家の意見が割れている。地球温暖化が進んでいるとの主張が主流だったが、その前提を覆す新説が、天文学者らから相次いで発表されている。その真相やいかに。

第129回
営業、製造、研究開発、サービス、マーケティング…、あらゆる企業の活動においてデータの活用なくして効率化、最適化は図れない。それどころか、競争を勝ち抜くにあたってデータを活用できるかが死活問題としてのしかかっている。デジタルトランスフォーメーションともいわれるトレンドだ。そのデータ分析の基盤技術を提供するテラデータのユーザー会が9月11日から5日間、米アトランタで開催したカンファレンス「Teradata PARTNERS 2016」で、データ活用の現在、そして将来について探った。

第36回
算数・数学に強い子に育つ!「3」と「5」の使い方
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き??最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!算数力アップの秘訣を一挙公開!
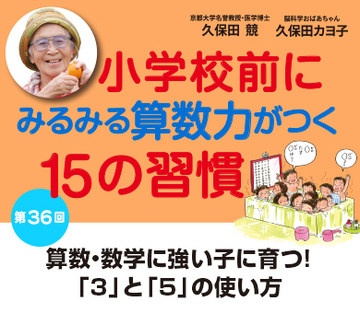
第35回
お風呂学習で絶対やってはいけないこと
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き??最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!算数力アップの秘訣を一挙公開!
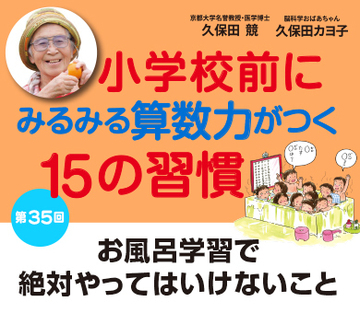
第33回
算数ギライを「算数好き」にするたった1つの方法
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き?? 最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!算数力アップの秘訣を一挙公開!
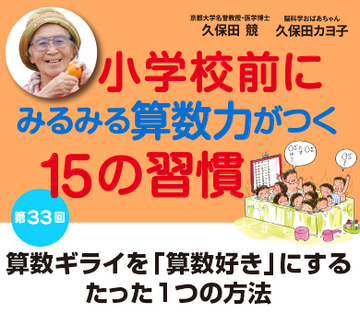
第4回
「思弁的実在論」とは何か?メイヤスーのもたらした実在論的転回
AI、遺伝子工学、フィンテック、格差社会、宗教対立、環境破壊……21世紀最先端の哲学者が描き出す人類の明日とは?現在進行形の哲学は世界の課題をどのように捉えているのでしょうか。第4回は哲学・思想界の新たなスター、カンタン・メイヤスー「思弁的実在論」を概観します。
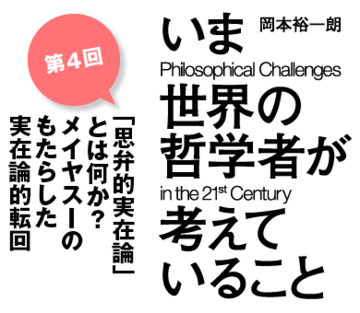
第11回
日常の業務だけでも手一杯なのに、ある日上司や社長から「今日から君は防災担当ね」と思いもよらぬ役を振られた。ご安心ください、方法はある。同様の課題に取り組んだある県とNPOの例を見ながら、「意欲薄い組織で防災教育を展開するコツ」を考えてみよう。

第8回
一流のプロフェッショナルは、それを自覚している、していないにかかわらず、例外なく「多重人格」であることに気がつくだろう。すなわち、一流のプロフェッショナルは、自分の中に「様々な人格」を持ち、仕事において置かれた状況や場面に応じて、「適切な人格」を前に出して対処している。

トヨタ自動車は今冬にも日本国内で第4世代「プリウス」をベースとした新型「プリウスPHV」を発売する。欧州メーカーも次々にPHVを市場投入しており、電気自動車との勢力図が大幅に変わることも予想される。

第32回
千葉県松戸市で市民有志が運営する学びの場「自主夜間中学校」をご存知だろうか。若者から中高年、在日外国人まで、中学校卒業程度の学力を身に付けられなかった人たちが集う場所だ。生きるために学びたい、と意欲を示す生徒の姿には「人間復興」の光が見える。

第20回
怒りの程度を“5段階”に分け、数字に興味を持たせる方法
2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!