組織・人材(14) サブカテゴリ
第337回
“基本”と“原則”は状況に応じて適用すべきもの 破棄してはならない
ドラッカーは、マネジメントにおいて致命的に重要な基本と原則が、どこにも明示されていないことに気づかされた。待っていても誰かがまとめてくれる気配はない。そこで、彼自身が書いた本が、『マネジメント─課題、責任、実践』だった。名著『現代の経営』を書いてから20年後の1973年のことだった。

第336回
組織は、そこに働く者が最高の仕事をすることを必要とする。そのためには、責任を持ってもらわなければならない。その責任を持たせるための処方が4つある。

第334回
トップたる者は自らが最も得意とすることを行わなければならない
ドラッカーによれば、成果を上げる人は、「外交的な人から内向的な人、おおまかな人から細かな人までいろいろだった」という。しかし彼らのあいだには、いくつかの共通点があった。そしてその筆頭が、なされるべきことを考えるという習慣だった。

第331回
自らのイノベーションの成果を常時評価していくことによって企業家精神を醸成する
自らのイノベーションを評価することは難しいことではない。行なうべきことは三つある。さらには、わが社が得意とするイノベーションの方法が明らかになり、不得手とする方法が明らかになる。

第330回
都立高校の野球部にとって「われわれの事業は何か」「われわれの顧客は誰か」
ドラッカーとは、現代社会最高の哲人である。同時に、マネジメントを発明したマネジメントの父である。かつ、“それぞれのドラッカー”である。

第329回
組織は本業に焦点を合わせ成果を上げて収入を得る他の仕事はアウトソーシングする
ドラッカーはこういう。「それは、いかにコストがかかっていようとも、トップマネジメントの内の一人として大きな関心を持たず、十分な知識を持たず、面倒を見ようとせず、重要とも思っていない領域である。それは、組織の価値体系の外の領域にある仕事である」。
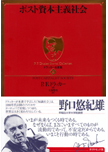
第328回
マネジメントたるものは自らの打率を知り上げていかねばならない
事業の将来は、投資、人事、イノベーション、戦略についての、今日のマネジメントの仕事ぶりによって左右される。しかもこの4つの分野において、打率を測定することは可能である。マネジメントは自らの打率を知ることによって、それを向上させることができる。

第2回
今回は、先進国に深く根付く「差別」というニューフロンティアの輪郭を切り取りたい。英国と日本は伝統的に文化が似ているが、人種、性別、異性婚などの多様性への対応は、英国のほうがはるかに進んでいる。なぜ日本は変われないのか。
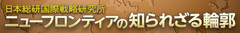
第327回
自己目標管理は全員のビジョンを方向づけ個の強みと責任を全開する
組織に働く者全員が、自らと自らの率いる部門が上位部門に対して果たすべき貢献、つまるところ、組織全体に対して果たすべき貢献について、責任を持たなければならない。
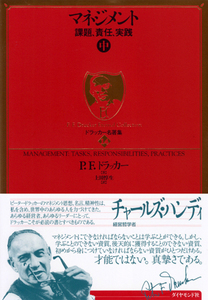
第326回
景気の変動にかかわりなく計画し発展していくために押さえておくべきこととは
景気循環から目を離してはならない。しかし、景気循環に焦点を合わせている限り、なにもできなくなる。そもそも今、景気循環のどこにいるのかさえ、いかなる経済学者にもわからない。景気循環についてなにかがわかるのは、循環の波が通り過ぎた後である。

第325回
公的機関が必要とするのは卓越した人材ではない六つの“規律”である
今ようやく日本でも、公的機関の見直しが急ピッチで進められている。しかしドラッカーは、すでに3分の1世紀前に、公的機関に成果を上げさせるための規律を明らかにしている。
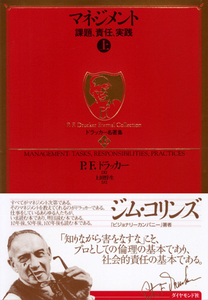
第324回
企業家精神を当然とするにはイノベーションの機会に注意を払わせる仕組みが必要
マネジメントの目を機会に集中させなければならない。人は提示されたものは見るが、提示されないものは見逃す。そこでドラッカーは、効果が実証ずみの、企業家精神浸透のための方策を三つ教える。

第6回
企業文化の変革に取り組んでいるのは、欧米企業だけではない。最近では、ブラジルや中国、インドなどの新興国の企業でも、経営トップのコミットメントの下、カルチャー・トランスフォーメーションが進んでいる。その1例を紹介する。

第323回
いつの間にか時代はモダン(近代合理主義)からポストモダンへと移行した
暗黒の中世にあって、一つの真理を得るならば、論理の力によって、もう一つの真理を得られるはずと考えた幾何学者がいた。とするならば、さらにそこから、もう一つの真理を得る。こうしてやがて、森羅万象、神の存在まで論理の力によって明らかにすることができるとした。

第5回
『巨象も踊る』で有名なルイス・ガースナーはいかにしてIBM改革成し遂げたのか、、同氏のカルチャー・トランスフォーメーションは、成功しているリーダーとそうでないリーダーの特性を分析するところから始まった。
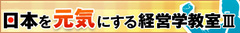
第30回
アベノミクス効果で株高なのに、国内法人は大幅な売り越しで、依然然、国債に資金をシフトさせている。一事が万事、日本ではリスクをとる者は評価されない。この姿勢を改めた時にこそ、日本経済は本当の成長軌道に戻る。

第322回
上司を高く評価せよ上司をマネジメントすることは上司と信頼関係を築くこと
ドラッカーは、上司との関係において、第一に行なうべきことが、上司リストの作成だと言う。上司とは、自分が報告すべき相手、自分に指示を出す者、自分の仕事と仕事ぶりを評価する者、自分が成果を上げるうえで必要となる者全員ある。

第3回
第2回目は、カルチャー・トランスフォーメーションの方法論を紹介する。企業文化を変革にするにあたっては、目に見えない水面下の要素に照準を合わせることがキーとなる。
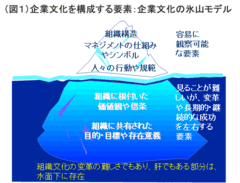
第321回
80歳のヴェルディのように失敗しようとも完全を求めて挑戦していこうと決心した
ドラッカーは、知識によって働く者にとって多少なりとも参考になるのではないかと言って、自らの経験をいくつか教えてくれる。その一つが、イタリアの大作曲家ヴェルディの最晩年の作品「ファルスタッフ」との出会いだった。

第2回
カルチャー・トランスフォーメーションという言葉を、初めて聞かれる方も多いだろう。日本語にすれば「企業文化の変革」。事業環境が大きく変化している日本企業こそ、いま取り組むべきテーマだ。
