
安東泰志
第74回
リーマンショックから8年、当局による規制が強化されると同時に、金融機関や投資家の側にも社会的責任を意識した投融資を行おうという姿勢が強まっている。果たして日本でもその動きは加速するのだろうか。

第73回
9月6日、最高裁で今後東京が国際金融センターたり得るかどうかにも大きく影響する重要な判決が下された。実は、筆者が代表取締役の会社が、この裁判の当事者(上告人)であったので、今回の事案について検証したい。

第72回
都知事選挙で圧勝した小池百合子氏の「東京をアジアナンバー1の国際金融市場として復活」という公約は目を引くものであった。この「東京国際金融市場構想」を実現するために何が必要かを考えてみる。

第71回
舛添前知事の辞職に伴う東京都知事選挙が7月14日に告示され、31日の投開票まで目が離せない。各候補者の公約を比較してみると、その主張内容や力点の置き方にはかなりの温度差がある。

第70回
安倍首相は消費税増税の延期を表明。一部で囁かれていた衆参同日選を否定した。安倍政権は、7月10日に投開票される参議院選挙で国民の信を問うことになる。アベノミクスの成果と課題を考えてみた。

第69回
三菱自動車が2004年のリコール隠し問題で経営危機に陥った時、筆者は取締役事業再生委員長として同社の再建に関与した。今回の不祥事は、当時から横たわっていた社内風土の問題が源流にあって発生したものであることは間違いない。

第68回
日銀は大規模な金融緩和を行ったが、「2年で2%」の物価上昇目標は達成できず、GDPの成長率も低迷している。実は物価を上げるだけなら、とても簡単だ。だが、それは極めて危険な道でもある。

第67回
シャープの再建にあたって、同社は鴻海の支援を仰ぐことを決議した。鴻海と産業革新機構の両案における受益者の違いに焦点を当てて、その妥当性を検証する。取締役会は株主に、鴻海案を選んだことの適切な説明ができるのか。

第66回
マイナス金利の導入は、量的緩和政策の限界を認めるものであるとともに、その効果は未知数と言わざるを得ない。そして、銀行のコストが転嫁される結果、“庶民泣かせ”の結果になる可能性が高い。

第65回
EUはギリシャへの第3次支援を綱渡りで乗り切ったが、ユーロの運命はドイツ次第だ。メルケル首相には、南欧諸国のみならず国内からも批判が高まってきた。もしユーロが危機に陥った場合、次なる世界恐慌が発生する可能性もある。

第64回
GPIFの7~9月の運用損失が約8兆円となったが、年金運用では短期の評価はあまり意味がない。より深刻な問題は、日本の年金がPEを積極的に組み入れていないことだ。それによって産業の新陳代謝が遅れ、運用リスクも高まっている可能性がある。

第63回
債権カットは、事業再生に際して必要であれば躊躇なく検討されるべき手段である。だが銀行など一部の金融債権者が同意せず先に進めないことが多い。最近、これに多数決原理の導入が模索されており、事業再生の救世主になる可能性がある。

第62回
日本の税制は、有能な人材や企業に極めて冷淡であり、起業家やエンジェル投資家のやる気を阻害している。背景には、横並びを是とし出る杭を打つ文化がある。この時代遅れな税制を見直さなければ、日本の将来はない。

第61回
金融と産業は国家の経済運営上、車の両輪だが、金融における東京の地位は年々低下している。成長戦略にとって決定的に重要な金融市場の国際化が後回しにされている背景には、日本独特の閉鎖的な文化がある。

第60回
「ローカル・アベノミクス」こと安倍政権の地方創生では、地域金融機関に大きな役割を期待している。しかし、そもそも地方にもアベノミクスが必要なのだろうか。そして、地域金融機関はその重責を担えるのだろうか。

第59回
プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)が、にわかに注目を集めている。背景には、相次ぐ企業再生事例での活躍や、資金調達側・運用側の変化がある。PEファンドは、産業の新陳代謝を通じて日本経済の発展に寄与する。
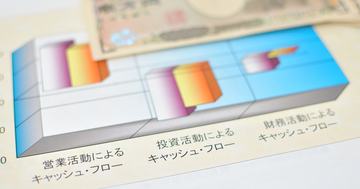
第58回
金融庁は、銀行の業務範囲を拡大する方向で議論を開始した。だがリーマンショック後の環境において、これ以上の拡大が本当に必要なのか。それは消費者の利便性、預金者保護、そして金融立国の趣旨にかなうのか。

第57回
盛んに議論されているAIIBの出資だが、この段階で参加表明する必要は全くない。中国の主導するAIIBはその成り立ち上、根源的な問題を抱えているうえに、日本企業が実利を得られるかも極めて疑わしいからだ。

第56回
政府は政投銀と商工中金の完全民営化を先送りする法案を提出した。のみならず、それら政府系金融機関の業務拡大を目指す内容だ。民間でできることへの官の介入は、市場規律を歪め、資本主義国家としての信認を失わせる。

第55回
経営陣と一般株主の間では、さまざまな場面で、時に深刻な利益相反が生じる。そうした場合に、株主利益の観点から冷徹に判断を下すのが独立社外取締役だ。その重要性は疑う余地がない。だが日本は利益相反に甘すぎる。
