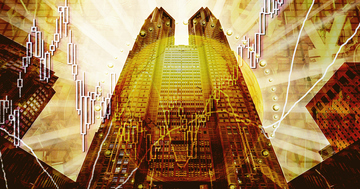安東泰志
コロナ禍で過剰債務状態に陥った企業は少なくない。ポストコロナで、こうした企業を再生し、日本経済を復興させるには、事業再生ファンドの活用が不可欠だ。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、より一層の景気悪化が懸念されている。その対策には、まず何よりも企業(雇用主)と雇用を守るために「資金繰り支援」が急務だ。その一方で、「ポスト・コロナ」を見据えた中期的には、地域のニッチトップ企業や社会的意義がある企業を優先して再生し育てていくという「企業再生版 トリアージ」の発想が必要となる。

国内最大の官民ファンドである産業革新投資機構(JIC)について、その存在意義や経営陣に対する高額な報酬等が話題となっている。これら問題点について解説する。

機関投資家と違って個人投資家は情報量が少ない。その間隙を縫うかのように、昨今個人投資家の利益を損なうような経営の意思決定がなされている例が散見される。例えば、さが美やソフトバンググループである。

第90回
2010年10月以来、約7年半続いてきた「安東泰志の真・金融立国論」だが、90回目の本稿が最終回。お付き合いいただいた読者の皆様に御礼を申し上げつつ、この90回の連載でお伝えしてきたことを一度整理しておきたい。

第89回
金融庁は昨年12月15日、新しい検査・監督の指針として、財務内容や保証・担保だけで判断するのではなく、事業内容や成長可能性も評価する事業性評価融資を重視する「金融検査・監督の考え方と進め方」を公表した。

第88回
「内部留保」という言葉は、いくつかの重大な誤解を伴って議論されている。本稿では、内部留保を巡る代表的な誤解について触れた後、その活用方法について考えてみたい。

第87回
東京都が策定し関係省庁や業界と協力して推進しようとする「国際金融都市・東京」構想について解説する。11月中旬、小池知事は、シンガポールにて東京版ビッグバンを宣言し、東京都のプロモーションがスタートした。

第86回
昨年小池都知事が就任して以来、意欲的に取り組んできた東京都の成長戦略の一つが「国際金融都市・東京」構想だ。そこで、今月と来月の2回に亘って、その内容を取り上げてみたい。

第85回
10月3日現在、まだ正式な公表前の段階ではあるが、小池都知事が代表を務める希望の党の政策、特に経済政策が「従来の自民党の政策とどう違うのか」について、知り得る範囲で開示してみたい。

第84回
金融界は、ここ数年、フィンテックの話題で持ちきりである。そして、ここに来て日本でもいくつかのフィンテック系ベンチャーが軌道に乗り始め、銀行界もようやく本格的に取り組みを開始している。

第83回
小池都知事は、6月9日の定例記者会見で「国際金融都市・東京」構想骨子を発表。昨年7月の都知事選挙で「金融先進都市」「環境先進都市」を軸とする「スマートシティ」を公約に掲げており、実現に向けた第一歩。

第82回
小池都知事は20日の記者会見で、市場移転問題について「築地は守る、豊洲は活かす」と述べ、事実上、築地再開発・再整備を軸とする方向性を打ち出した。筆者は今回の案は非常に理に叶ったものであると考える。

第81回
去る5月19日、東京都の「国際金融都市・東京のあり方懇談会」(座長:斉藤惇・KKRジャパン会長)は、都庁で小池知事同席のもと、5回目の会合を開き、昨年11月以来の議論の中間取りまとめを行なった。

第80回
東芝の再建に当たって、半導体子会社株を売却する必要は、本当にあるのだろうか。本稿では、東芝の再建のあり方の全体像を扱うのではなく、東芝が今の時点で半導体子会社を売却する必要があるのかに絞って考察したい。

第79回
豊洲移転の可否を決めるには、環境基準の問題だけでなく、豊洲移転後の市場の持続可能性という「金融的な視点」も必要である。本稿では、主に金融の視点から見えてくる現実について論考してみたい。

第78回
「国際金融都市・東京のあり方懇談会」で注目されたのが、懇談会の委員の1人である一般社団法人日本投資顧問業協会の岩間陽一郎会長による"EMP( Emerging Manager Program )"導入を後押しする主張であった。

第77回
昨年10月に公表された「金融行政方針」では、「日本型金融排除」と「フィデューシャリー・デューティー」という言葉が目を引いた。2017年の金融界のキーワードは、この2つになることは間違いない。

第76回
2016年10月11日、コーポレートガバナンスをないがしろにする残念な事件があった。この事件は、たまたま筆者が運営する投資ファンドが関係していたので、今年を振り返る意味でも、やや詳細に触れておきたい。

第75回
小池都知事は、定例記者会見で「国際金融都市・東京の実現に向けた検討体制について」と題して、公約であった「東京をアジアナンバー1の国際金融都市としての地位を取り戻す」構想について、その概要を開示した。