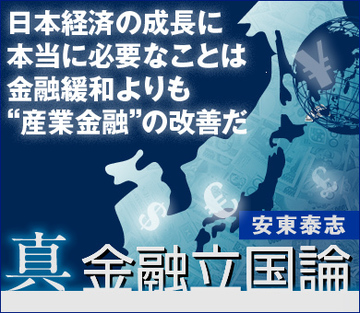安東泰志
第14回
規制業種における横並び体質はイノベーションの妨げとなる。産業金融の担い手の中で最も人材の層が厚い大手銀行がそのことに諦念を抱き変革を怠るならば、日本の前途はさらに厳しくなりかねない。
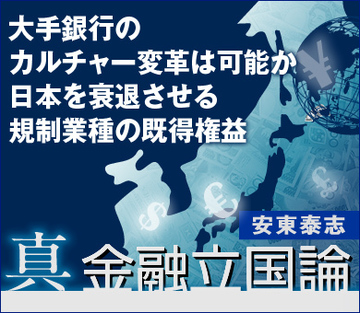
第13回
野田新首相の政治スタイルはまさに「中庸」になりつつある。それは、とりもなおさず09年の総選挙で民主党が掲げたマニフェストと現在の日本の状況に照らして必要な施策を「調和」させようという試みでもある。しかし、それは本当に意味のある試みなのだろうか。
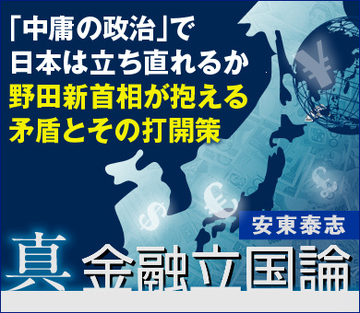
第12回
主にリーマンショックへの反省から、2013年から2019年にかけて、より厳格化された自己資本比率規制である「バーゼルⅢ」が段階的に導入される。この規制は銀行の投融資行動の変化をもたらし、産業金融のあり方に大きな影響を及ぼすだろう。
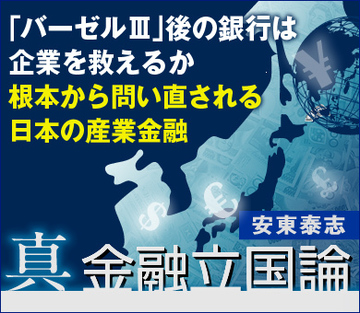
第11回
震災で被害を受けたのは直接的には被災地の企業だが、他地域の企業も需要低迷で経営難に陥っているケースが多い。したがって、手当てが必要な企業再生の範囲は被災地の企業だけではない。ただし、被災地の企業と、それ以外の地域の企業の再生は必要な対応が異なる。
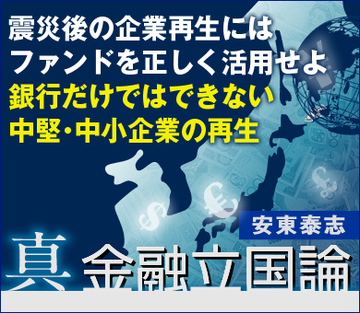
第10回
震災から3ヶ月を経ようとしているが、様々な面で軸足の定まらない対応が続いている。金融経済面だけで見ても、東電処理と二重債務者の問題は相変わらず議論が混乱している。いずれも初めに政治主導で「軸」を定めておけばこのようなことにはならなかったはずだ。
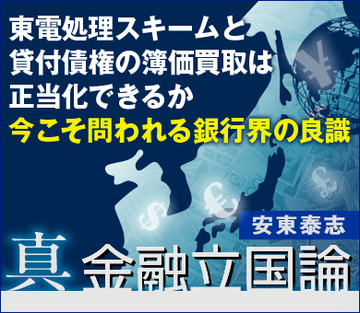
第9回
東電処理にせよ、二重債務者問題にせよ、まず国民負担によって債務者を救うような議論が先行し、本来コストを負担すべき者(社員・株主・債権者)たちの責任が棚上げされているように思われる。原理原則をうやむやにしたまま国民負担を強いれば、後世に悪しき前例を残すことになる。
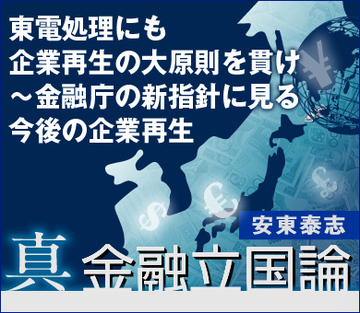
第8回
国債発行を抑えつつ復興事業を行なおうとすると、他の工夫が必要になる。「復興基金」は、そうした背景から政治家の一部で主張され始めているものと理解している。しかし、危険なのは、基金(ファンド)というものの本来の性格が正しく理解されないまま、公的部門の持つ貴重な家計部門の金融資産が流用されてしまうことである。
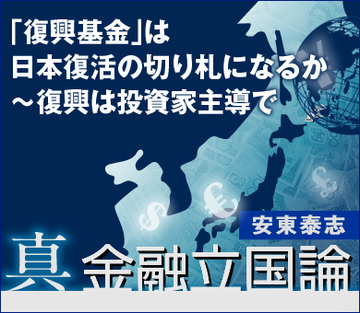
第7回
東日本大震災を受けて、復興支援に多額の予算を計上しようという動きがある。確かに、必要なものもあろうが、日本の財政状態を考えれば、極力財政出動を伴わない支援策を講ずべきだ。実際、企業金融面で予算を使わずともできる支援策はいくつもある。

第6回
郵政民営化の見直しが民主党・国民新党の公約であり、小泉・竹中路線は、格差を拡大したとして批判されている。基本に立ち返り、小泉・竹中路線の財政金融政策の目指していたものは何だったのか、それと比較して現政権の政策はどう評価されるべきなのかを考えてみたい。

第5回
民主党政権発足後、公的年金の運用方針について、国債中心の運用にこだわる長妻厚労相と運用先の多様化の必要性を説く原口総務相(いずれも当時)の間で主張の隔たりがあったことは記憶に新しい。公的年金を一つの例にしながら、国民の資産の運用のあり方を考えてみたい。
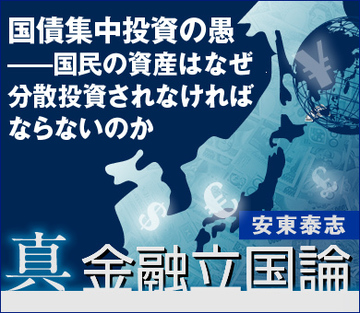
第4回
現在の日本において、真に成長戦略を考えるならば、それは常に高い利益率を目指して成長戦略を練っている民間企業に対しリスクマネーを直接投入し、これら企業の設備統廃合や成長投資を促進することだ。結論から言えば、それができるのは、PEファンドをおいてない。
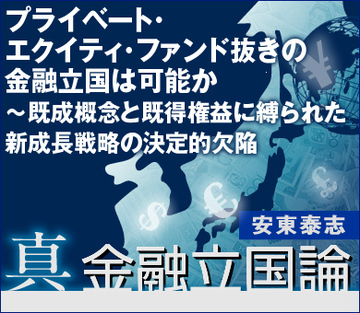
第3回
日本においては、リーマンショック後の今でもなお、金融機関のコングロマリット化、ユニバーサルバンク化が志向されている。しかし、この動きは、世界の金融規制の方向性とは正反対の方向を向いたものである
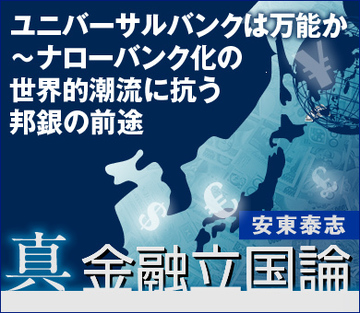
第2回
菅政権肝いりの「新成長戦略」は新金融立国の実現を掲げながらも、実態は既成の金融産業への配慮が先行するあまり、本筋を外した議論となっている。本筋とは、他でもない、産業金融の強化である。

第1回
日銀は金融緩和を続けているが、残念ながらそのお金は銀行システムの中にだけどんどん滞留している。日本の継続的な成長や雇用に必要な付加価値を生み出す肝心の民間企業にお金が回るようにするには、どうすればよいのか。