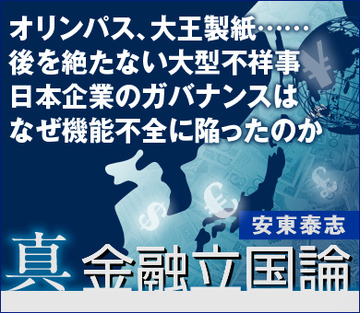安東泰志
第34回
安倍政権の新成長戦略が評価されなかった原因は、余りに総花的で全体像が体系的に説明されていなかったこと、何よりも産業の新陳代謝の鍵である「リスクマネーの供給」が、資金循環の改善の観点から具体的に語られていないことにある。
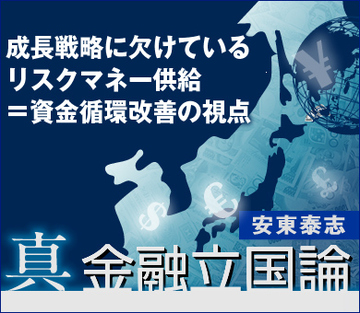
第33回
「異次元緩和」は、銀行の資産運用戦略に大きな影響を与える。銀行、特に地銀や信金は、無理な海外展開、長期国債の購入、上場株式への投資などは控え、国際標準の分散投資に徹することが現時点での最適行動である。

第32回
成長戦略というと、どうも各論に走りがちである。各論をバラバラと論ずる前に、民間企業主導の成長戦略の大きな柱は何なのかをしっかり考えておく必要がある。そこでで「成長戦略の5本の矢」を提案する。
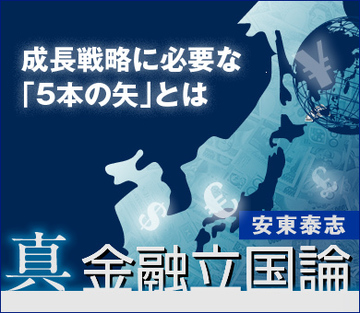
第31回
いよいよ、黒田新総裁が日銀の舵取りを担うことになる。目指すべきは産業の新陳代謝を進め、企業の活力を引きだすことによって需給ギャップを早期に埋めるという「良い物価上昇」だ。その実現の道を提案する。

第30回
アベノミクス効果で株高なのに、国内法人は大幅な売り越しで、依然然、国債に資金をシフトさせている。一事が万事、日本ではリスクをとる者は評価されない。この姿勢を改めた時にこそ、日本経済は本当の成長軌道に戻る。
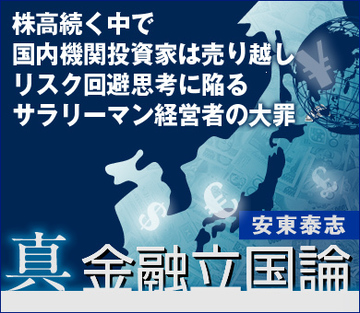
第29回
官主導で民間企業や産業を救済するスキームが次々に表面化。官僚は「官民」のスキームであることを強調するが、これは損失を国民に押し付ける隠れ蓑だ。国は民間独立系ファンドにシードマネーを得供する役割に徹するべきだ。
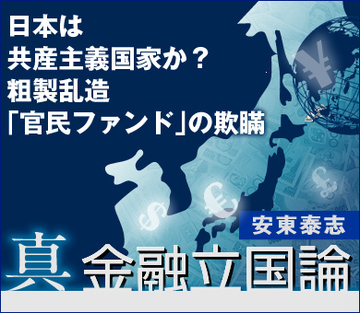
第28回
総選挙が目前に迫った。今回は政党乱立で政策を比較衡量することすら大変だ。そこで金融政策、成長戦略、起業促進・企業再生政策に的を絞って、論点を整理し評価を加える。
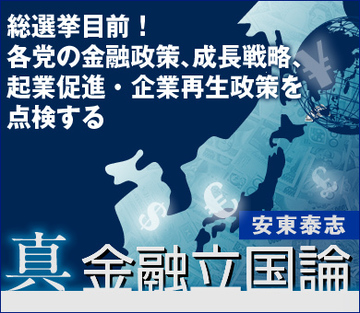
第27回
金融庁が銀行の出資規制の緩和の検討を進めている。出資規制の緩和は時代の要請にも、国際的な規制の潮流にも反している。それは「悪い規制緩和」の典型だ。
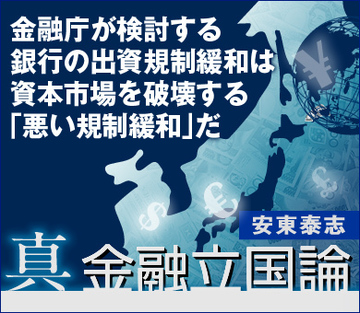
第26回
2009年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」が、来年3月にいよいよ期限切れを迎える。だが、現在、金融庁を中心に打ち出されている期限切れ対策は、再び問題を先送りするものだ。そこで金融円滑化法の「正しい」出口戦略を提示してみたい。
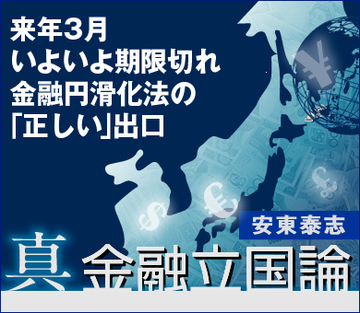
第25回
昨年秋に事件化したオンリンパスの「飛ばし」では、投資ファンドが悪用された。だが、投資ファンド=悪と決めつけるのは拙速すぎる。各段階で当たり前の検討が行なわれておれば、事件は防げる。オリンパス事件を手掛かりに投資家のチェックポイントを洗い出してみよう。

第24回
シティバンクが開催した株主総会で、役員への高額報酬案が否決されたことは記憶に新しい。金融業界を一括りにして高額報酬を否定することには反対だが、銀行に対する高額報酬規制は正しい方向だと考えている。その理由を述べる。
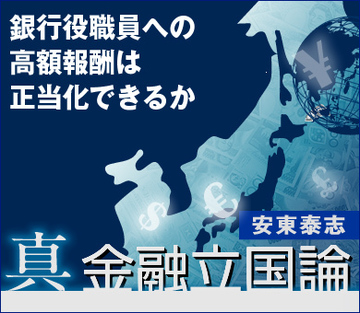
第23回
ERISA法は企業年金の加入者保護を徹底しただけではない。その根底にあるスピリットによって、アメリカの社会・経済の活性化に大きく貢献したことが分かる。日本の政治家・規制当局者がその精神から多くを学ぶことは多い。
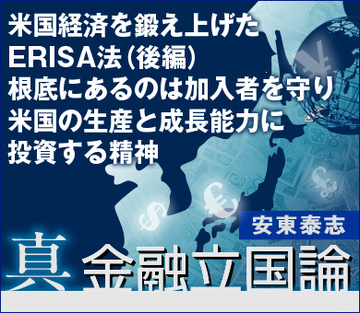
第22回
AIJ問題以降、わが国でも年金資産の運用について、様々な議論が交わされている。だがいずれも視点が低い。そこで2回にわたり米国ERISA法を基に、年金資産の管理・運用のあり方考えてみたい。今回は米国ではいかにして年金運用が国家戦略として位置付けられたかを見る。
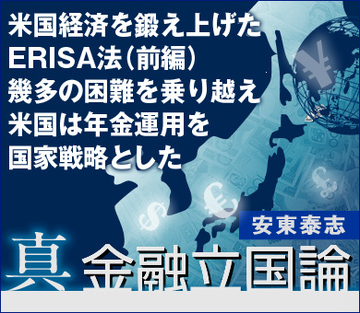
第21回
「金融立国を目指す」ことが国策であるなら、政府・金融当局が今、実際に目指している方向は明らかに間違っている。国際市場であるための条件は、市場参加者の多様性と十分な投資家保護。「利益相反天国」の日本はこの条件を著しく欠いている。

第20回
AIJ投資顧問事件が世間の注目を集めるなか、独立系の資産運用会社によるシンポジウムが開かれた。巷では単純な規制強化論が盛り上がるなか、我が国の資産運用に関する本質的な問題を突く議論が戦わされた。
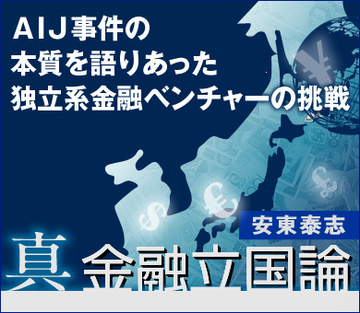
第19回
独立系の投資顧問会社・AIJ投資顧問が約2000億円もの運用資産を失った。新聞や監督当局は免許制や運用規制など規制再強化の方向に動いているが、それは問題の解決にはつながらない。大事なことは、投資家に対する忠実義務を果たす仕組みの確立と、投資家自身の成熟である。
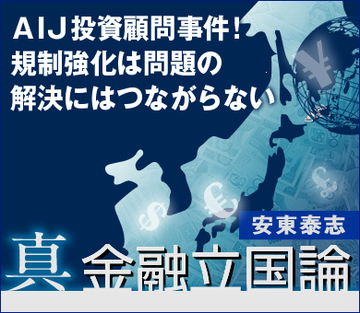
第18回
昨年12月に、法務大臣の諮問機関が「会社法制の見直しに関する中間試案」を公表した。この試案の主要ポイントに検討を加えてみると、コーポレートガバナンスの強化に頑強に抵抗する勢力の姿が浮かび上がってくる。
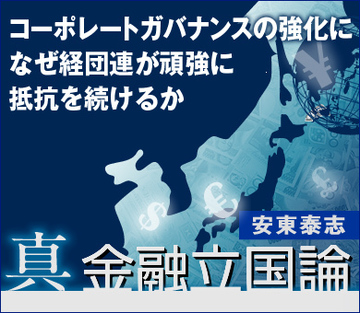
第17回
昨年末、金融庁が中小企業金融円滑化法のさらなる延長方針を発表した。同法の延長は問題の解決策になっていないどころか、弊害の方がはるかに大きい。ここでは6つに分けてその理由を述べてみよう。

第16回
先週のEU首脳会議の結論を見ても、ユーロ危機の抜本的解決への道は遠い。困難な経営環境が続くと予想されるなかで、日本の銀行はどう対応すべきか。日系企業、非日系企業への対応、銀行自身の運用に分けて考えてみよう。
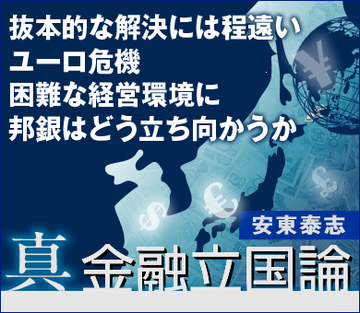
第15回
オリンパス、大王製紙と大きな企業不祥事が続いている。近年、日本でもコーポレートガバナンス改革の動きが強まっているにもかかわらず、なぜ不正は後絶たないのか。日本の企業統治体制が持つ構造的な問題を検証してみよう。