
深田晶恵
前回、今年の減税は過去イチ複雑な仕組みになっており、一方で減税額は“ガッカリ”な内容であることを解説した。今回は、年金収入で暮らす人に減税の影響がどう出るのかを見ていこう。減税も踏まえ、「年金の手取り額」を試算した結果、衝撃の事実が判明した。

「えっ…散々モメたのに減税額これだけ?」過去イチ複雑な今年の減税、“徹底解剖”したらガッカリなワケ
昨年の衆院選以降、「年収103万円の壁」見直しを巡って与野党で議論が繰り広げられた。紆余曲折あったが、「結局、今年の所得減税ってどうなったの?」というのが皆さんの一番知りたいことだろう。今回は、昨年の定額減税とも比較しながら、今年の減税額がどうなるのかについて見ていこう。

#4
就職氷河期世代の悲劇は年収が上がらないことだけではない。上の世代と同じ年収に達しても、税金や社会保険料の負担増で「手取り」が減っている。残酷な手取り格差の実態に独自試算で迫る。
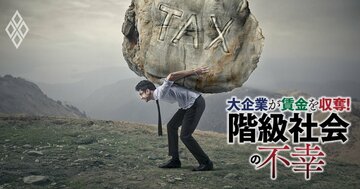
今年4月から高校の授業料についての国の支援制度が拡充される。来年4月には私立高校の就学支援金の限度額も大幅に引き上げられ、所得制限も撤廃となる。こうした支援の拡大を背景に、「子どもを私立高校に通わせるのもアリかも」と考えている人は多いかもしれないが、私立に通わせる選択をする前に“落とし穴”についてぜひ知っておいてほしい。

医療費控除の落とし穴について解説した前回の記事には大きな反響があった。今回も、確定申告のポイントについてお伝えしよう。申告書をミスなく記入し、控除を漏れなく使い切るための「5つのコツ」を伝授する。今年ならではの注意点もあるので、確定申告をする人はぜひチェックしておいてほしい。

確定申告シーズンがやってきた。会社員の中で申告が必要な人は限られるが、申告することで還付を受けられて得するケースもあるので、関心を持っている人も多いだろう。中でも、注目度が高いのが医療費控除だ。だが、そのルールを知らないと、大損しかねないので要注意。今回は気を付けたい医療費控除の「落とし穴」について解説しよう。
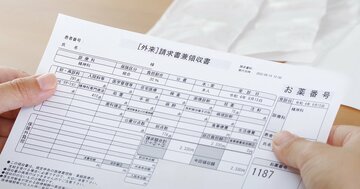
2025年最初の当コラムでは、「今年の手取りの年収」を見ていこう。手取り計算が大好きな“手取りスト”の筆者にとって、「今年の手取り年収」を試算するのは毎年の恒例行事だ。額面年収、家族構成別に72パターンの試算結果をお届けするとともに、手取りに影響を与える改正点をお伝えしたい。

年末年始は、久しぶりに親と顔を合わせ、今後の暮らしについて話をするいい機会だ。親が高齢の場合、同居を検討することがあるかもしれない。よくあるのが、父親の死後、子どもが母親との同居を開始するというケースだ。実はその際、住民票を親と同一にするかどうかが重要な選択であることをご存じだろうか。筆者の試算によれば、この選択は10年間で「100万円超の差」につながる。どういうことか、詳しく解説しよう。

クレジットカードの申し込みをしたり、ローンを組んだりするときには必ず「審査」が行われる。お金を貸しても大丈夫かどうか、その人の信用力を確かめているのだ。ただ、審査は通るか通らないかの二択。つまり、あなたの信用力が一般的に見て高いかどうかは分からない。そんな中、「自分の信用力」を指数化して知ることができるサービスが始まった。FPの筆者がさっそく使ってみたので、今回は信用力が決まる仕組みを解説するとともに、レポートしてみたい。

「年収106万円の壁」の撤廃が検討されていると報じられた。これは、社会保険加入の要件を緩和し、対象者を増やす「適用拡大」につながる変更だ。社会保険料の支払いが発生すれば、手取りが減る。ネガティブに捉える人も少なくないようだ。しかし、それでも筆者は適用拡大を進めるべきだと考える。その理由とは。

10月末に行われた衆議院議員選挙で、公示前から大きく議席を増やした国民民主党。同党が訴えたのが「手取りの増加」、具体的には「103万円の壁」の見直しだ。この「103万円の壁」とは一体何なのか。実は、年収にはこれ以外にもいくつかの壁がある。知っておくべき壁とは何か、実際の手取りにどのような影響が出るのか、見ていこう。

大手銀行などが、10月から住宅ローンの変動型の基準金利を引き上げた。実に17年ぶりの引き上げだったため、これから住宅ローンを組もうという人は「変動型で借りるべきか、それとも固定型か」迷ったかもしれない。今回は、住宅ローンで変動金利を選ぶか、固定金利を選ぶか検討する際に、必ず押さえておきたいポイントを解説する。

大手銀行などが、10月から変動型住宅ローンの基準金利を引き上げた。これを受けて、「うちの返済額にどれくらい影響が出るのかな」と気になった人も多いだろう。良いタイミングだと思って、住宅ローンの返済計画を見直してみるといいかもしれない。金利上昇よりも怖い“意外な落とし穴”が待ち受けている可能性がある。

年金に関して、多くの人が気になるのは、「将来いくらもらえるのか」「どうすれば年金額がどのくらい増えるのか」ということだ。働き方や受給開始時期などによってどのように年金額が変わるのか、「公的年金シミュレーター」を使えば簡単に試算できる。

住む場所によって年金の手取り額が異なる――。この衝撃の事実をみなさんに知ってもらうため、『「年金手取り額が少ない」都道府県庁所在地ランキング』を作成した。前回の「年金年収200万円編」に続き、今回は「300万円編」をお届けする。同じ額面収入300万円でも、自治体によって手取り額に大きな差があることが分かった。
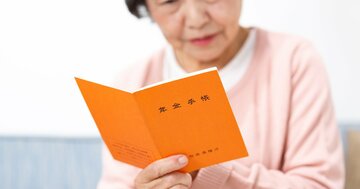
住む場所によって年金の手取り額が異なる――。この衝撃の事実は、意外と知られていない。では、実際にどのくらいの差があるのか。過去にも本連載で取り上げ、大きな反響を呼んだ『「年金手取り額が少ない」都道府県庁所在地ランキング』について、国民健康保険料や介護保険料の改訂を反映した「最新版」を作成した。年金年収「200万円編」と「300万円編」の2回に分けてお届けする。まずは「200万円編」をご覧いただこう。

8月5日の日経平均株価の下げ幅が過去最大を記録した。新NISAをきっかけに投資デビューした人は不安になったかもしれない。ただ、ここは冷静に今やってはダメなこと、やるべきことを押さえておこう。

厚生労働省が発表した「遺族厚生年金」の改正案が、SNS上で大炎上している。ただ、この改正案について誤解している人も少なくないようだ。年金制度は複雑で難しいが、正しい知識を持っておきたい。今回は、この遺族厚生年金の改正案について、ポイントを分かりやすくお伝えする。

株高という追い風もあり、新NISAが盛り上がっている。筆者のもとに相談に来る投資ビギナーもかなり前のめりだ。しかし、そんなNISAに興味津々な人たちは、非常にもったいない“残念な行動”をしていることがよくある。

将来のために年金の仕組みをきちんと知っておきたいと考える人は少なくないが、全体像を一から勉強しようとするのはおすすめしない。大事なのは自分のケースなので、「ねんきん定期便」で十分だ。今回はねんきん定期便のチェックポイントと、みなさん気になる「年金額の増やし方」を解説する。
